| R.Maunder Mozart's Requiem6 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | R.Maunder Mozart's Requiem5へ戻る |
| R.Maunder Mozart's Requiem7へ進む |
| 16 The ‘Confutatis' , and ’Amen' 様 「Confutatis」は、K620の一部、例えばAct IIフィナーレの第744小節以降、 Act 1 Finale.の第143-5および149-51節、を連想させる。それは、K 427の「Qui tollis」や Don Giovanniの最後から2番目の場面や、(弦楽器のユニゾンでの使用において)Rex Tremendaeとも似ていないことはない。 非常に正確なモデルはないが、ほとんどの場合、幸いなことに、オーケストラが何をすべきかはっきりしている。 モーツァルトの12段スコアは、そのうち8つの譜表を使用している。譜表スコアは、コーラスと弦のためにいつものように8譜表を使用し、2つの譜表は第26−9小節でのバセット・ホルンとファゴットに使用している。EyblerとSussmayrの両者は、 第1-6小節と11-15小節で、トランペットとティンパニを使っているが、A minorの調性でのDトランペットの利用には非常に限られた音域のため、あまり確信がない。 一方、K 427での「Qui tollis」やSanctus、あるいはK 620とK 527での独立したトロンボーンの使用は、おそらくモーツァルトが残りの2つの譜表を、トロンボーンのために残す意図があったことを示唆している。モーツァルトは通常、3本のトロンボーンパートのために、3つの譜表と音部記号を使用していたが、K 427の「Qui tollis」では、アルトとテノールのトロンボーンが、1つの譜面とアルト音部記号を共有していた。いずれにせよ、独立したトロンボーンは、この楽章では、トランペットやドラムよりも、その可能性が高いようである。 第1−5小節; 第10‐12小節におけるモーツァルトの第1ヴァイオリンは、上弦部がここでバスとオクターブになるように意図されていて、第4小節のヴィオラまでの、アイブラーのオクターブの一貫しない状況を変化させる必要はない。ジュスマイヤーはアイブラーを引き継ぎ、バイヤーは、2拍分、ジュスマイヤーより遅らせているが。 バセットホルンが第7-10と17-25小節で、ソプラノとアルトを支持すべきことは明らかなので、最大のコントラストを得るためには、バセットホルンは第1-10と17-25小節でサイレントであるべきである。 したがって、(最初からの)Eyblerの持続する木管楽器は間違っていて、ファゴットは(演奏するとすれば)、SussmayrやBeyerのバージョンのように、合唱をダブるくらいとし、あるいは、弦楽器とユニゾンでいくべきである。トロンボーンがどう演奏されるべきかは、状況による。なぜなら、モーツァルトは、ファゴットによってのみダブリングされた男声にあまり関心がなかったために、K620の 'Bewahret euch vor Weibertucken' の第18−21小節のように、ファゴットとトロンボーンの”両者”によるダブリングならば、受け入れられ得るのである。(バイヤーによれば、正しい構成は、 bassoon1 , alto trombone , and tenor trombone with the tenors , and bassoon2 and bass trombone with the bassesである) トロンボーンは声楽とダブらせるか、独立したパートとなるべきか?ヘス(p.104)が見ているように、ジュスマイヤーは、決心ができていない。 Eyblerは、彼がトロンボーンについてしようとしていたことを特殊化していなかったが、興味は持っていた。 ジュスマイヤーとは違って、アイブラーは、トランペットとティンパニを1番目と3番目よりも2番目と4番目のオフビートに入れて、ボイスエントリーを強調している。したがって、それらは(アイデアがあまりにも遠いものではないならば)、'Requiem aeternam 'の第1‐7小節に最初に使用された特徴的な「オフビート」伴奏パターンのスローバージョンを呈し、 'Confutatis'の第25‐39小節や'Lacrymosa'の始まりでは、モディファイされた形式で使われている。制限された利用可能な音符の範囲によって、Eyblerは第4小節を超えてこのパターンを続けることができなかった。しかし、このやり方がトロンボーンに使われた場合は、第1-5小節と(変更された形式の)と第10-15小節で続けることができる。さらにパターンは、自然に、第5‐6小節で必要と思われるフルコードに導く。このようなオフビートトロンボーンのモーツァルトの先例は、K620のAct1 Finaleの第16‐18小節に、特にK527の最後から二番目の場面でのCommendatoreの入りにある。 トロンボーンが独立したパートを持つことを考えれば、ファゴットのための選択は、サイレントにするか、弦楽器をダブリングするしかない。第7-10と17-25小節で最大のコントラストを得るには、明らかに後者が選好されるべきであろう(で、そうした)。 第6小節; 第3拍のハーモニーには、やや異なる2つの可能性がある。ともに、K 620の 'Der Holle Rache kocht im meinem Herzen'の第10小節をモデルとし、減三和音(レ♯‐ファ♯‐ラ)となっており、アイブラーとジュスマイヤーとバイヤーの弦楽器のユニゾンか、あるいはK619の'Die ihr des unermesslichen weltalls''の第91小節の6/3♯(=シ音上の三和音)である。  両方(K 620とK619)のこれらのモデルは、'Requiem aeternam'の第14小節(eis,Domine!)や'Dies irae'の第9小節(Quantusの前)のように、ソ音が第4拍に加えられている。(バイヤーは、誤って、第2拍にG♯を保持しており、第3拍における減七で上向する解決は、説得力がない)。 より適当なモデルは、K619 である。なぜならそれは、同じような内容で同じ音高だからである。四度は第4拍に付け加えられるべきであり、弦楽器は(アイブラーとジュスマイヤーとバイヤーのような)ユニゾンではなく、4声でなければならない。(第7小節の第1拍のユニゾンにもかかわらず。K619の第91−2小節が示すように)。 第7−10小節; Hessによるソプラノとアルトに対するバセットホルンを組み合わせる提案は、合っている。そして第6小節からの自然なフォローとなっている。ユニゾンヴァイオリンとの組み合わせは、「魔笛」のTaminoとDamenのアリア、” Zu Hilfe! Zu Hilfe!”の第79−87小節とほぼ正確なコピーである。そしてこれは、後期のモーツァルトのまさにその特徴なのである。それは、第1−5、10‐15小節と好対照である。 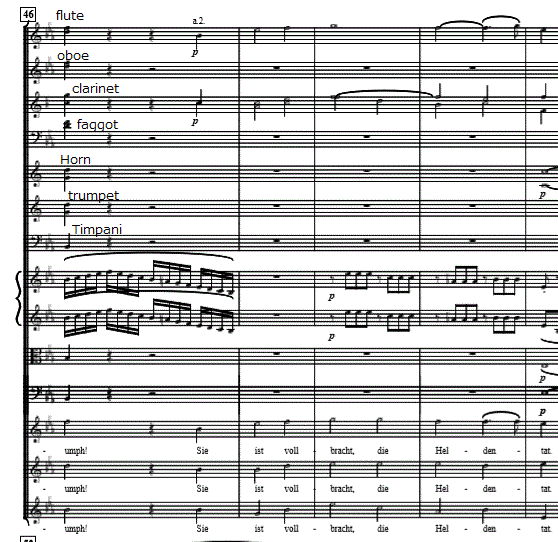 第10−15小節; 明らかに第1−5小節に対応しているが、パッセージはさまざまなやり方で変化している。 そして、2拍子になっている。前と同じ弦楽器の構成は、秩序立っており、特に、ジュスマイヤーやアイブラーのようなヴァイオリンよりオクターブ下にヴィオラを置くよりは、ヴァイオリンとユニゾンにする方がよい。 トロンボーンは第1−5小節のように始まるが、第11−12小節においては、より早いハーモニーの動きであり、第13−14小節においては、繋留の連続とその解決が、より持続的であるべきであるような暗示をしている。こうした理由で、第15小節のドイツの六和音の五度は、避けられねばならない。 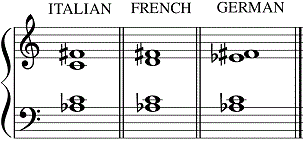 第16小節; ハ長調からイ短調へと戻る第6小節へのわずかな変化のみを必要とする。第6小節のように、第3拍の正しいハーモニーは、バイヤーのような6/4♯/3♭やジュスマイヤーの信じられない6/4♯/2♯ではなく、 第17−24小節; 第7−10小節でのように、バセットホルンは、ソプラノとアルトを支える。そしてここにおいては、ヴォーカルパートが休符の間でも、(バセットホルンによって)ハーモニーは埋められることになる。 第25−40小節; アイブラーの第2ヴァイオリンとヴィオラパートは、ジュスマイヤーとバイヤーにより、わずかな変化のみでそのまま使われているが、1、2か所は改善することができる。第26,30,34小節の最初のパターンをやめる理由は特にない( 第32小節の第3拍上の解決されていない四度、そして、第35小節の第1拍の二重の根音(ヴィオラのレ♭音)と、そのためになくなってしまった五度は誤りである(これらのミスは、ジュスマイヤーによって、ヴィオラがレ♭→ラ♭音へと訂正されている)。 しかし、アイブラーの第38小節の第2拍の七度の先取り音は、モーツァルトの(書いた)第1ヴァイオリンパートの動きからは、特に避ける必要はないように見える。そして、バイヤーよりもより良いヴィオラパートを書いている(モーツァルト自身は、第28小節の第2バセットホルンにおいて、正確に同じことをしている)。 木管楽器は、第26−9小節は、モーツァルトによってすべて書かれている。そして、それはそのまま第30−9小節にも容易に採用され得る。ジュスマイヤーは、モーツァルトのパートを変えてしまったことにより、当然の報いを受けている。そして特に、第25小節において、より早く木管楽器を持ち出してきてしまったことにおいて。第39小節(訳注;原本は29小節となっているが、間違いと思われる)と比べてみても、彼は、最後までより長く、小節全体に続けてしまっている。(バイヤーは、後者においてミスをしているが、アイブラーは、注意深くそれを避けている)。 トロンボーンは、明らかにこのセクションではサイレントであるべきである。K427 のKyrieの第27−9小節と比較して ‘ Lacrymosa' ‘ Lacrymosa'の最初のすべき仕事は、最初の8小節のおーけすとれーしょんを完成させることである。調性が二反長に戻り、すでにトランペットとティンパニをサイレントにしておく理由はなくそのために、モーツァルトの自筆譜の4段の空白の譜表は、 'Dies irae'や'Requiem aeternam'におけるように、バセットホルン、ファゴット、 トランペットとティンパニに割り当てられるべきである。トロンボーンは、ピアノパッセージを除いて、ソプラノ以外の3つの声楽声部のダブリング機能であるその本来の役割に戻る。 すでに第4章で述べたように、‘ Lacrymosa'はおそらく、‘ Confutatis'に引き続き、‘ Amen'フーガへと導く位の、短いものであったと思われる。こうした結論は、‘ Lacrymosa'が‘ Confutatis'と同じスピードであるべきことから支持される。新しい付点4分音符は、古いそれ(‘ Confutatis'のフェルマー付きの最終小節)と同じ長さになる点において。 ‘ Confutatis'の最後の小節は、こうした仮説を支持するように見える。さらにまた、アーメンスケッチもまた、付点に分音符がその前の付点4分音符と同じスピードであることが意図されているように思われる。 言い換えると、基本的音律は、 Confutatis'‐‘ Lacrymosa'ー‘ Amen'フーガの連続を通して同じなのである。それゆえ、モーツァルトのテンポ印‘ andante' at the start of the 'Confutatisは、さらに続けて適用される。 第1−2小節; モーツァルトの第1ヴァイオリンは、8分音符のそれぞれのペアの2番目が、おそらくは、続く8分休符への音を続けるであろうという事実を許容するだろう。こうした持続は、それが適宜解決した新たな和音と不協和音を形成する。 たとえば、第2小節の第1、3拍を見よ。第1拍は、聴き得るシ♭からラ音への解決そして第3拍はそれ以前のソ音への装飾された解決(ソミファ)である。 第3−4小節; ”捕捉”の効果は続く。ハーモニーはほとんど正確な、'Requiem aeternam'の第32小節の二短調への移調である。さらに、第4−5小節のソプラノは、明らかに、レクイエムのメインテーマから由来している。新たなファゴットパートは、それゆえ、'Requiem aeternam'を基礎としている。 第1−2小節の弦楽器パターンは確かに、続いてきている。第1ヴァイオリンは、声楽に合わせるためには、それぞれの小節の第3拍において、注意が必要である。ハーモニーや対位法のミスを避けるために。ジュスマイヤーの第1小節の転写の試みは明らかに間違っている。なぜなら、ソプラノの解決は、先取りされており、第4小節の第3拍(訳注;原著では1拍とあるが誤りと思われる)にて、ヴァイオリンとの間に醜いクラッシュがあるからである。さらに、第4拍では、お呼びでない九度がある。バイヤーはこの九度をそのまま使っているが、ジュスマイヤーとは異なり、適当に解決されていない。 一方、バイヤーは確かに、第7−8小節において、クライマックスのためにトロンボーンを使っている。ジュスマイヤーの第5−6小節における持続するトロンボーンと木管楽器は、もっとも極端な効果を生じている。 第5−6小節; ジュスマイヤーの第1ヴァイオリンは、バイヤーにも採用されたが、八分音符のそれぞれのペアの2番目上のバスを”覆っている”。彼はまた、(下の3パートの弦楽器において)第5小節の第3拍、第6小節の第1,3拍上の三度のない五度を形成している。Maunder版では、こうしたエラーを避けるようにデザインされている。そのために、強拍では、三度のない五度はないようになっており、それぞれの第1バイオリンのエントリーでは、適度にバランスの取れた和音となっている。さらに、内部パートでは、声部の独立した対位法を、可能な限り、取り入れている。 それゆえに、和声を完成させるための木管楽器は特に必要とはされず、それらはとにかくオミットされるのが一番よく、そのために、第7−8小節でのクレッシェンドのための準備は十分となる。 第7−8小節; ジュスマイヤーの第1ヴァイオリンパートは、第7小節で、十分に作用するが、第8小節においては、ドイツの六のバスとのダブリングを避けるために、(第1ヴァイオリンパートが)訂正されねばならない。バイヤーの訂正版は、完全に受け入れられるが、(バイヤーとは異なる私のやり方の)第2ヴァイオリンの非分割は、先立つテキスチャーのより正確なつながりを形成する。 第7小節のクレッシェンドと第8小節のフォルテは、明らかに、フルの管楽器のサポートを要求する。そして、最大音量のために木管楽器は可能な限り持続される。トランペットとティンパニはクライマックスで要求されるが、トランペットは木管楽器とともに持続され、第8小節の第4拍でのより大きな強調はさけられている。 私たちはここでいよいよ、モーツァルトの‘ Lacrymosa'の自筆譜の最後に到達した。いよいよこの楽章の完成をどのようにすればベストであるかを考えなければならない。ジュスマイヤー版は何ら助けにはならない。なぜなら、すでに第4章で示された通り、それはまったく彼の発明によるのであり、モーツァルト風素材を基礎にしていないからである。 第9小節の最初の和音はおそらく二短調なので、そして、第7−8小節後では合唱が短い休符を必要とするので、もっともリーズナブルな手順は、第1−2小節と同様の2小節分のオーケストラの小節を加えることである。そしてそれから後に、(そこまでで使われた)最初の3行の歌詞とほぼ同じ速度で、(Huic ergo parce Deus以降の)残りの3行の歌詞を設定する。モーツァルトの最初の8小節はそれゆえ、短い2つの楽章の最初の半分となる。 しかしながら、第9小節は、二短調でスタートしなければならないが、第1−2小節は単純に繰り返されることはできない。なぜなら、少なくとも第3−4小節の繰り返しについては、非常に強い期待が生まれているからである。しかし、第3−4小節の音楽は、新しい歌詞Huic ergo parce Deusには適合しない。 この期待外の繰り返しを避けるための唯一の方法は、第10小節を使って、異なった調性へと転調することである。‘ Lacrymosa'の第3小節のオーケストラパートの繰り返しに対して、 'Requiem aeternam'の第19−20小節がここで移植されることになる。そこでここではヘ長調へと転調することになる。 今やヘ長調へと到達し、Huic ergo parce Deusは、明らかにこの調性において新しいテーマとなるべきである。 ‘ Lacrymosa'が'Requiem aeternam'を再現するという考えは、この楽章('Requiem aeternam')の第27−9小節が再利用されることが強く示唆される。ヘ長調へ移調され、より低いパートで単純化されたリズムではあるが。 ゆえに、移調されたそのテーマは、やがて現れるアーメンフーガの主題の最初の半分に非常によく似ている。すなわち、多かれ少なかれ、すでに第4−5小節のソプラノによって引用されたレクイエムのテーマの反転である。 さらに、第11小節特徴的な減四度の下降跳躍は、'Requiem aeternam'の第27小節からのコピーであり、第6小節のテノールにもさかのぼる。その‘ Lacrymosa'における関連性は別として、メインのレクイエムのテーマの反転としての後の楽章におけるプレインソング‘ Te decet hymnus'の再利用は、レクイエムに対するモーツァルトの主なモデルのひとつにさかのぼることができるという考えであり、それはM.Haydnが、彼のハ短調のレクエムのBenedictusで、'Requiem aeternam'で使ったテーマを再利用したようなものである。(Ex8.6参照)。 p172 次の行、‘Pie ]esu Domine' はどのように設定されるべきだろうか?’Domine'が半終止の必要があることは、明らかである。'Requiem aeternam'の第14小節のように。そして、それ以降の‘ dona eis requiem’の行は、フルの二短調のカデンツで終止しなければならない。第8小節の半終止の緊張を解決するために、この点では、聴取者に半終止を思い起こさせるために。’Domine'上の半終止は、二短調であるべきである。‘Pie ]esu Domine'の行は二短調であるべきで、実際、最後のカデンツの解決感情は、その調性の以前の使用によって、弱められることだろう。 問題の解決は、ト短調への転調に際して、第13小節を使うことに現れる。第3,4,9小節を想起させるようなオーケストラのそして、次第に、第14−15小節において、ト短調から二反長へと移る。第16小節の’Domine'への準備において。 ‘Pie ]esu ’という言葉は、、繰り返され、そのために、フレーズの長さは、これまでの行のそれに最も近いものとなる。 第14−16小節の素材は、四度引き上げられて転調して、‘ Lacrymosa'の第5小節から来る。ゆえに、ソプラノパートは、第7−8小節におけるそれを呼び起こす。その間、バスはメインのレクイエムのテーマを逆行している。 第11小節‐第13小節の「Te decet hymnus」の最初の半分を引用し、Requiem aeternam'の第30-2小節のような、後の半分の使用はしないような一貫性のないことには反対もあるかもしれない。しかし、M.Haydnのハ短調のレクエムには、その優れた先例がある。なぜなら、彼の'Requiem aeternam'とBenedictusで、M.Haydnは、Tonus Peregrinusの前半のみを使用し、それから別の素材を続けているからである(私Maunderは、それに倣ったのである)。 いずれにせよ、プレインソングの後半は、‘ Lacrymosa'のこの点には適合させることはできない。なぜなら、それは半終止ではなく、完全終止のためであり、あるいは、設定すべき歌詞がさらに2行続いているためである。 第17−20小節は、第8小節の半終止の解決となり、第7−8小節をバランスする意図がある。以後、カデンツのフォルテマークへ向かうクレッシェンドとなる('Requiem aeternam' の第8小節が示すように、 ’requiem’の言葉は、必ずしもpianoを意味するわけではない)。 第18-20小節は、'Dies irae'の第38-40小節から採用され、その間、第17小節では、ソプラノは、第16小節から始まり、第18-20小節で逆行した形で繰り返されるレクイエムのテーマのstatementを完成する(したがって、第17小節は、第16小節の移調である)。 同時に、テノールは逆行したstatementを完成させ、アルトをはんてんさせる。 第15-17小節のソプラノ部分とハーモニーは、「‘Tuba mirum' 」の第27-32小節を連想させる。 2対形式の楽章は、第20小節の最初の拍で完了するが、短いコーダを追加して 'アーメン'フーガに導き、強いリズムの後の弛緩を生み出す必要がある。「Requiem aeternam」の第46-8小節は、明らかに、このような目的のために引っ張り出され、それは、「Amen」の開始のための適切な位置に仕上げるために、(第9小節のような予備の小節後に)適合され得る。 第9-24小節でのオーケストレーションについては、言及する必要はあまりない。単に第1-8小節のスタイルで続いていく。第10小節(第2バセット・ホルンとヴィオラ)の二重の繋留とその解決のためには、そして第16小節第1拍のビオラでは準備されていない四度のためには、 'Requiem aeternam'の第18小節の先例がある。 Kyrieの第51-2小節のように、、第2バセット・ホルンは、第18-20小節のテノールパートに切り替わるので、使用可能なトランペット音を二重にしないように、第20小節の第1拍のバセットホルンの間では、四度ではなくオクターブで終わるようになる。より精巧なティンパニのリズム(第8小節も参照)を持つ持続するトランペットの組み合わせについては、K 621の 'Che del ciel、che degli Dei'あるいはK620のActIの最後の合唱を参照のこと。 モーツァルトの16小節の「アーメン」フーガのスケッチが、Sequenc eの最後のセクションを形成することを目的としていたことは間違いない。主題はレクイエムの主要なテーマから厳密に逆転したものであり、いずれにしても、これは、単語「アーメン」が出現するレクイエムのテキスト中の唯一の場所である。おそらく、このフーガの完成は、「Lacrymosa」の完成ほどの緊急性はない。「Lacrymosa」は、もっとも節約的な演奏においてさえ、省略されることはできないだろう。なぜなら、‘Confutatis'の第40小節の第1拍で、あいまいに、しかもしかも間違った調性で(訳注;‘Confutatis'はヘ長調で事実上終止している)、セクエンツィアは終わろうとするからである。そのために、ジュスマイヤーの間に合わせ的なアーメン終止が変わりに使われたのである。 しかし、モーツァルトが、 ‘ Lacrymosa'や、'Requiem aeternam'とKyrieの配置のバランスの再現については、より精巧な扱いを意図していたことは、まったく明白である。そのために、単なるアーメン終止は、作品全体におけるモーツァルトの注意深いプロポーションを偽っているのである。 いずれにせよ、'Amen'をとりのぞくことは、モーツァルトの設定による16の疑いなき真正物をオミットすることになるであろう。 モーツァルトの人生の最後の1年間の、彼のフーガ書法のモデルはむしろ稀であるが、Kyrieや、K608 のファンタジアは、学ぶべきことがたくさんある(特にKyrieのフーガにおいては、反転やストレットなど)。 Biberのレクイエムの「Lacrymosa」はまた、(モーツァルト理解の)手助けになる。なぜなら、同じ主題と対主題のストレットの様々な組み合わせを含んでいるので。むろん、モーツァルトの初期の教会音楽には多くのボーカル・フーガがある。。そして、K 426の二手のためのC minorのフーガは、ほぼ対位法についてのの百科事典である。しかし、モーツァルトのフーガへの態度は、1780-90年の間にかなり変化したようである。初期の例はかなり長く、むしろゆるやかに構成されている傾向がある。モーツァルトは、全体の構造にはあまり関心を持っていないという印象を受ける。複雑さと天才性が増して驚異的な対位法の技を披露するよりも。 しかし1791年までには、そのテクニカルな熟達は完璧になり、モーツァルトは、ソナタ形式とフーガを融合させることに成功した、短くて緊密に編成されたフーガを書いていた。例えば、Kyrieフーガは、第15小節から始まる、明確に認識できる「展開部」を持っている。そこでは、二短調以外のさまざまな調性となっているそして、”再現部”は、バスがもともとの二短調で入ってくる第39小節からである。K608 の最初のフーガは同様なソナタ様形式になっている。規模は小さいが。 'Amen'の最初の仕事は、明らかに、その提示を終了することである。モーツァルトのスケッチは、最初の10小節で終わり、次の5小節では、欠けているすべては、ソプラノの2番目の対主題の終わりである。しかし、最初の対主題の連続する性質は、同様のパターンが次にも続くことを強く示している。そのために、第11-12小節のソプラノ(ミララソ♯ソ♯になる)についてはほとんど疑いがない。さらに、第12‐13小節のアルトは、第7‐13小節のテノールによって与えられた音型への縮約した回答を示し、第2-5小節におけるような最初の(ソプラノの)対主題は、それ自身、同じ回答の装飾された形式となっている。 したがってモーツァルトは、明らかに、縮約の多くの利用を意図し、それゆえ、単一テーマのフーガにおいて、反転や逆行のような、その他の標準的なテーマの操作もまた、意図している。 こうした精神では、ソプラノにとっては、第12小節のラソ♯となることは適当である。それは、第13小節において、ラシドと続いている。そのために、主題の最初の半分の縮約であり反転である形となる(こうした反転は当然、もともとのレクイエムテーマと同じこととなる)。 第13小節と第14‐15小節のソプラノは、アルトを模倣し続けており(第7小節のソプラノも比較せよ)、ビーバーの「ラクリモサ」の第8小節に合わせ(例8.20を参照)、それから、3小節分の休符のために、第19小節の応答との再度の入りの前に、ドロップアウトする。こうした休符は、ほとんどフックスによる義務とみなすことができ、たとえば、Kyrieの第5−7小節と比較できる。 モーツァルトのスケッチは第15小節で終わっているが、アルトのさらなる1小節を除き、第16−18小節を満たすことは、困難ではない。第18小節において、テノールは、第12小節よりは第6小節(のソプラノ)に従う。バスは、主題を持つが、応答はない。 Kyrieとの完全に規則的な提示との類似によって、第19小節での応答とともに、ソプラノのエントリーを遅らせる理由はない。ゆえにソプラノは、バスでもまた示されるが、第25小節の第1拍にまで続くことができる。そこが提示の最後である。 しかし、テノールは、期待される第2の対主題を持つことができない。なぜなら、第21、23小節の第3拍の四度の結果が、その跳躍によって正しくアプローチされていなかったからである。第2の対主題の繋留と解決は保たれている。テノールに主題の最初の半分の逆行性的反転を与えることによっているが(すなわち、メインのレクイエムのテーマの逆行版)。そして、第2対主題の上昇する四度は、代わりに、アルトに与えられる。第22小節においては、バスのファ♯が必須の音符ではないことがはっきりする。 提示部はこれで完成しており、フーガの残りの形が次に設定されなければならない。それは、中途でのエントリーが、トニックやドミナント以外の調性となっており、”再現部”は、バスにおけるオリジナルな主題とともにスタートするKyrieやK608のような”ソナタ形式”のフーガにおける規則であろう。 Kyrieの”展開部”が、6回の主題のエントリーと対主題の4声のストレットを持っているのに対して、中間のセクションにとって、ここでのより良いモデルは、K608の”展開部”である。なぜなら、それは簡潔であり、主題がからみついているからである(そして、反転した主題を含む再現部へとリードする)。 K608の中間セクションをコピーすると、その調性スキームを含め、以下のようなプランになる。 1 中間のエントリーはト短調→ヘ短調で、 2 バスにおける”偽エントリー”が、変ロ短調→ハ短調となり、二短調での完全なバスのエントリーを導き、再現部が始まる。 (K608においてこれに相当するエントリーのいくつかは、長調であるが、’Amen’の主題の半音のステップは、明らかに変更されることはできない) さらに考慮すると、2声の完全な中間エントリーは、2小節分のズレでもって、次のエントリーが入ってくるべきである。なぜなら、主題が提示部においてすでに2回出現すると、2つの対主題を持つ主題からなる3パートのパッセージは、余計になるからである。しかし、こうした3パートのパッセージに第4のパートを加えると、2小節ズレて出現する主題は、適合するであろう唯一のものとなることが、速やかに明らかになる。 さらにこれらの2回のストレットのうちの1回の構成は、満足に機能するであろう。なぜなら、バスが再現部を導くことになるので、それは、第2のストレットよりも最初のストレットにおいて、始まるからである。実際、それは、さもなければ、それぞれの対主題の付加が、誤った6/4和音を産生するので、第1のストレットを導くに違いない。 最初のストレットにおいて、続く声部は、ソプラノかテノールである。(アルトではない。それは、ト短調の主題が、低い音域や極端に高い音域では合わないからである)。しかし、それがテノールであったならば、第2のストレットは、ソプラノとアルトで受け継がれたことだろう。。そしてそれから、それらのどちらであっても、2回目の声部は、ほとんど望ましくないユニゾンで入ってくることになるだろう。 最初のストレットでの2番目の声部は、ソプラノである。そして、次のストレットはアルトとテノールで受け継がれねばならない。アルトは結果として、アルトとテノールの間を十度とし、パートの間での非常におかしな音間隔ができてしまう。 まとめ パート1 中間セクションについて、以下の様に配列されねばならない。 1(a)ストレット ト短調、2小節ズレて、バスにソプラノが続く。 1(b)ストレット ヘ短調、2小節ズレて、アルトにテノールが続く。 パート1には、提示部の終わりと最初のストレットの間のギャップのブリッジをすること、そして、両方のストレットにおけるその他の2パートを満たすことが依然として残っている。KyrieとK608の両者は、提示部の後、非常に短く、連続した、episodeを示す。フックスに従えば、第28−9小節のバスのエントリーは、突然のカデンツとして、和声化される(K337のBenedictusの第28−9小節と比較せよ)。そしてこれは、ソプラノにおいて主題の逆行かつ反転にてアプローチされ、テノールでは、反転でアプローチされる。アルトはバスを模倣する。 最初のストレットの間、2つの対主題は、完全に適合する(短調への転調とともに)。そしてアルトの最初の対主題とテノールの2回目の対主題を持つ構成は、その他のあたりよりもよい空間を産生し、提示において失われた2回目の対主題のためにテノールを補う。 varietyにとってしかし、第2のストレットは、最初の対主題のストレットに伴われ、そして、第2のepisodeの必要性は、第1へまっすぐな第2ストレットの参入によって避けられる。続いてソプラノは、第35小節において、期待されるラ音ではなく、ラ♭音を持つ。しかし、こうした主題の半音的変化は、モーツァルトのKyrieでの対位法での取り扱いと同種であり、すでに、第5小節でヒントを与えられたように、そこではソプラノは、シ♭音を持っている。 テノールとバスは第34−7小節で、それぞれ主題の縮約(ストレットにおいて同じ音高で現れようとする)、第2の対主題から由来したモティーフで、結合部をカバーしている。ゆえに、第36−8小節において、バスは主題の最初半分の反転を持っている。ソプラノはアルトとクロスする。Kyrieの第32−3小節のように。 中間部門のパート2にとって、主題の最初の3つの音符をベースとした連続するepisodeを伴って、K608のモデルが密接にフォローされている。テノールはふたつの対主題から由来し、ソプラノは、再現部への準備において、主題の完全な反転への対主題の最後の部分を拡大する。その間、アルトは、主題の2つの半音階的に変化させられたstatementとともに、テノールを模倣している。 再現部は、それまでのepisodeの続きのように始まるが、今回、バスにおける主題はかんぜんで、第53小節の増六度が連続パターンからの変化の印となっている。再現部のプランは、”Amen”テーマが主たるレクイエムテーマの反転であるという事実とともに、(同様にバスの反転したテーマで再現部が始まる)K608同様、再度示されている。交替した提示部における主題と応答の代わりに、主題は今や、反転し、メインのレクイエムのテーマからの主題からの逸脱を最後に明白にしている。 このスキームは特に、”ソナタ形式”フーガに適当である。なぜなら、再現部におけるエントリは、提示部でのようにドミナントとトニックを交代しているが、(通常のソナタ形式におけるような)ドミナントの調性への転調は不要であり、再現部全体がトニックにとどまることができるからである。 フックスによって推薦されているように、こうした4つのエントリーは、提示部においてなされているよりもより接近した空間でなされている。バスは多かれ少なかれ、テノール‐アルト‐ソプラノの順の固定を導く。 Kyrieの第82小節からの対主題のように)、そして、第60−1小節において、バスは、再度、縮約された主題を使う。バスにおける反転した主題のエントリーが、第64小節において、始まる。その間アルトは、最初の対主題を反転させ、テノールは、対主題の後の部分を基礎としている。 バスのエントリーは、2小節によって、半音階的に拡大している。 'Dies irae' トランペットとティンパニは 'Requiem aeternam' ‘ Lacrymosa' セクション' Dマイナー以外の様々なキーを範囲とするバー15から始まり、バー39の元のキーyのベースエントリーから始まる「再決定」を有する.K 608のフレーズは、 類似 ソナタのような形をしていますが、小規模です。 ‘Confutatis'; for |