対斜(false relation,cross relation)について
トップページへ
マタイ受難曲のページへ
音楽エッセイのページへ
対斜というのは同じ小節内にある別々の声部が同じ音程でナチュラルな音と臨時記号がついた音が同居している場合をさす。同一声部においてこういう状態の場合は対斜とはいわない。それは半音階進行の一部とみなされるからである。
さて、一般的な和声学ではこれはあまりやらない方がよいとされている。理由は簡単、要するに聞いていてなんとなく気持ち悪いからである。和声学上の禁則とはすべてこういった類で、理屈も何もとにかく聞いていて不快感をもよおす音の進行などはやめよう、というきわめてシンプルな理由によっているのである。
しかしこの対斜というのはたとえば完全五度や八度の平行の禁止のようにきちんと守られていることは少ない。これも理由は簡単で要するに完全五度の平行は本当に聞いていて気持ち悪いが、対斜の場合はそうでもないからである。対斜の譜例はいくらでも見つけることができるし、意図的に使われていることもある。特にバロック後期以降、完全に機能和声が確立されると、ほとんど対斜という概念さえもがなくなっていったように思われる。機能和声にしたがって作曲すれば必然的に同一小節の異なったパートで対斜が現れるからである。
たとえばCdur→Adurという和声の進行が同一小節内にあるとすれば(こういう和声進行はバロック期以降は少しもめずらしくない)、多声部の楽曲ならばどこかのパート同士で対斜の関係にならざるをえないだろう。したがって機能和声確立以降は対斜の概念はむしろ邪魔になったのである。現代でも作曲をする人も完全五度の平行の禁則などはきちんと守るであろうが、対斜なんて別に考えずに作っているんではなかろうか。
しかしルネッサンス期あたりでは事情は異なる。この時期はまだ機能和声が確立しておらず、たとえばナチュラルな音とそれに臨時記号がついた音は同じ音のvariationと思われていた。(D.Wulstan著「Tudor Music p166参照) 現在の和声学を知っている私たちからすれば、たとえば、FとFisを同じ音とは考えない。ところがルネッサンス時代までは臨時記号はまさに臨時記号であり、導音をつくったり、三全音を回避するためにやむを得ずつけたものであり、臨時記号がついた音はあくまでそのナチュラルな音の付属物であったのである。
(この時代にはまだまだ教会旋法の優位性が残っており、全音階が最良であり、臨時記号というものは必要時以外はつけない方がよい、という考えが根強く残っていたのである。しかし導音の魅力に作曲家が魅せられ、導音を作る為にどんどん臨時記号が頻発するにおよび、ついに全音階である教会旋法は長短音階にその王座の座を明渡さざるを得なくなったのである。このあたりは前掲書p118参照))
したがってルネッサンス期における対斜は機能和声に則って作られたものではないために、前後が不自然に聞こえてしまうのである。こうしたことが対斜が禁則に近くなった理由なのであろう。ためしに以下の曲を聴いてみよう。これはイギリスのチューダー朝の代表的作曲家のひとりのJ.shepardのミサ曲の一つであるが、下譜のように導音を作るためのAsのナチュラル化が何箇所かで計られている。そのためにそれぞれののパートが対斜関係になっている。この対斜は機能和声に基づいて作られたものではなく、導音を作るために偶然できたものであるため、当然前後の音のつながりはよくない。しかし、この時代は主に各パートの横の流れをスムースにすることに作曲の主眼がおかれ、縦の機能和声は副次的であったためにこういうことは特に気にしなかったようである。

ここをクリック!
さて、この対斜関係の音符同士がもっとくっつくとどうなるだろうか。上譜では対斜関係の音は拍子が離れていたのでぶつかることはなかった。しかし、この2音がもっと近づいてくるとついには重なるようになり、臨時記号がついた音とつかない音が短2度(ないしは短7度)でぶつかるようになる。(下譜参照) これはルネッサンス期のイギリス音楽でよくみられた現象で「English cadence」と呼ばれている。(前掲書p165参照) よくイギリスのチューダー朝音楽を聴いてるとところどころでものすごい不協和音で響くところがあるが、これがまさに「English cadence」である。有名な「コベントリーキャロル」がいい例である。
The Coventry Carol - Trad.

ここをクリック!
こうした不協和音(English
cadence)が英国のみで出現した理由についてはhttp://www.rmsr.ch/publications/arlettaz/musica_ficta/index.htmlによれば英国では16世紀半ばの宗教的混乱((メアリー一世の反動政策、処刑など)により、過去の写本が失われ、改訂された写本では臨時記号がめちゃくちゃにつけられてしまったせいであるという。その混乱は1530年から1575年まで続き、その間の資料は少ない。
English Cadenceの最初の印刷例は1575年の写本で見出されるが、それ以降English Cadenceが英国音楽の特徴ともなるのである。(大陸でも1575年以前の資料ではEnglish Cadenceのようなものが若干は見出されるが、それ以降はそもそもこれの原因となる二重化された導音(マショーの時代の”二重導音”とはまったく異なる概念。念のため)そのものが作曲技法上、避けられるようになった)
During the whole period, England clearly represents a special case. The most
important polyphonic manuscripts of the early sixteenth century (Eton
Choirbook, Lambeth Choirbook, Caius Choirbook) still seem to be unaware of
explicit attraction accidentals. Later on, the English manuscript tradition
becomes very confused, in part because of the religious conflicts, which
resulted in the loss of much mid-century material. The remaining sources
(Forest-Heyther partbooks, Henrican partbooks, British Library MS Roy. Add.
74-77, Gyffard partbooks) underwent numerous emendations by later hands,
including many additional accidentals. The dating of such alterations turns out
to be a very difficult task, often even an impossible one. Important printed
sources do not appear earlier than 1575 (Tallis and Byrd, Cantiones quae ab
argumento sacrae vocantur, London), at which date the situation begins to
improve again. In this publication of 1575, attraction accidentals are to be
found rather frequently, sometimes in combination with simultaneous false
relations (imperfect octaves) which soon became a distinctive feature of
English music.
The period between 1530 and 1575 therefore remains a very obscure one as concerns the use of attraction accidentals in English music. (http://www.rmsr.ch/publications/arlettaz/musica_ficta/index.html参照)
その頃、英国の事情は明らかに特殊であった。16世紀初頭の英国の最も重要な写本であるイートンクワイヤーブックやランベスクワイヤーブック、などでは近接した臨時記号の記譜に関しては無頓着であった。
その後、英国の写本は非常に混乱を極める。それは宗教的闘争によって多くの16世紀中ごろの写本が失われてしまったからである。Forest-Heyther partbookやHenrican partbookといった戦火を逃れた写本は後に多くの改変がなされた。そうした改変の中で多くの臨時記号の付加も行われた。
そうした改変がいつ頃行われたのかを明らかにすることは非常に困難な問題であり、しばしばそれは不可能である。印刷された重要な資料は1575年以前には明らかにされていない。(Tallis and Byrd, Cantiones quae ab argumento sacrae vocantur, London)そしてこの1575年はまた情勢が再び回復し始めた頃でもある。
1575年に出版されたこの資料では、近接した臨時記号はむしろ増加している。後に英国音楽の特徴にもなる同時的対斜(訳注;English Cadenceのこと)もまたしばしば認められる。※
※なお、H.K. Andrewsは、同時的対斜と'English cadence,'を区別している。'English cadence,'は、彼の議論では、カデンツへのアプローチにおける非同時対斜の用語となっている。しかし、彼の多くの例で十分に明らかにされているように、両者は、形式や機能の本質的な側面で異なることはなく、単に、2つの声部のオーバーラップがあるかどうかの違いだけで、密接に関連している
(Andrews, H. K. The Technique of Byrd's Vocal Polyphony. London: Oxford Univ. Press,1966, 99-110)。(Peter Urquhart CROSS-RELATIONS BY FRANCO-FLEMISH COMPOSERS AFTER JOSQUIN
p16参照)
1530〜70年はそれゆえ、英国音楽においては近接した臨時記号の使用に関しては非常にあいまいな状態であったといえよう。
なお、H.K. Andrews は、最も早期の 'English cadence' の例はジョスカンにあり、他の例は「フランドル楽派の次世代の作曲家においてたまに見かける程度」としている。彼はさらに、Gombert
や Clemensの作品におけるそうしたカデンツ形式は、「決してまれではない。」としている。29 (Andrews, H. K. The Technique of Byrd's Vocal Polyphony. London: Oxford Univ. Press,1966, p106)。
さらに、対斜に関しては、その位置が重要となる。つまり、カデンツ形成に関係するか否か、である。カデンツ形成時の対斜は、通常、inflectionする声部のmi-inflection(たとえばソーファ♯-ソ)とその他の同一音(ファ)とぶつかることにより生じるが、カデンツ形成時でない場合、もっとさまざまな理由で対斜が生じる。
ちなみに英国は16〜7世紀にこうした宗教的混乱を二回経験しており(二回目はかの宗教革命。なお、英国は15世紀後半にも宗教戦争とは異なるが”ばら戦争”を経験しており、この時期にもやはり前代までの音楽的遺産が多く紛失している)そのたびに前世代までの音楽的遺産はほぼ完全に息の根を止められてしまっている。こうした文化的断裂は新しい音楽文化を生み出すのには好都合だった面も多少はあるかもしれないが、やはりマイナス面の方がはるかに大きかったであろう。英国音楽史が大陸にくらべて今ひとつなのもこういったところにその遠因があるのかもしれない。(もっともドイツもまたかの30年戦争でシュッツからバッハにわたる100年を浪費したともいえるが)
ここでEnglish Cadenceの一例を見て聴いてみたい。かのTallisの有名なO Nata luxである。この曲のサウンドを聴くと、ところどころEnglish cadenceが出てくるのがおわかりであろう。
Thomas Tallis - O Nata Lux
ではバッハにおいてはどうだろうか。彼はマタイにおいて要所要所でこの対斜を使用し、その独特の効果を出している。バッハの場合、機能和声が確立した時期の作曲家であるので、対斜を用いる場合、前後の和声の要請に基づいているものであり、そこにはルネサンス時代にはない計算が働いているのは当然である。ここでは例として第7番の合唱と第38番のコラールを上げたい。
まず第7番では第6小節でアルトがAの音を続けた後、テノールがいきなりAsの2分音符で高く「Armen(貧しき者)」と叫ぶ。ここがまさに対斜。和音進行から言えばこの第6小節はFdurから根音のない属七なのか減七なのかわからない和音に移っており、この部分は何がしかの不自然さを聴くものに響かせるのである。このわざとやった対斜により、弟子たちの「貧しきものに・・」というえせ人権派を皮肉っているといえるのである。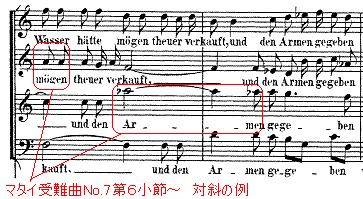
次に第38番のコラールであるが、これはなんと対斜のオンパレードである。(下譜の※印をつけたところが対斜)そしてこの対斜を主に「偽り」だの、「欺き」だのといったトゲのある言葉に対して使用していることがわかる。こうした対斜という手法を他の手法と混ぜることにより、この曲を明るいながらもなんとなくトゲのある曲となさしめているのである。
ここをクリック!
マタイ受難曲のページへ
音楽エッセイのページへ