前ページへ
第34〜35番のページへ進む
第二合唱の役割
シオンの娘たちがイエスの捕縛を嘆く二重唱を歌っている間に、第二合唱は断続的に三回、割り込むような形で闖入してくる。バセットヒェンで通奏低音がない不安定な状態がこの第二合唱の短い入りにより突然中断され、聴く者は突然の大合唱にびっくりさせられる。
(私事ですが)私が最初に「マタイ」を聴いたのは立教大学聖歌隊が演奏するのを生で聴いた時であるが、とにかく歌詞の意味はわからなくとも、この第二合唱が突然入ってくるところは強烈な印象を受けた覚えがある。そのくらいインパクトのある構成となっている。この入りにより、バセットヒェンで低音に飢えていた聴衆は驚愕とともに低音を堪能するのである。あたかも砂漠で飲む水のように。
ちなみにこの曲のようにデジタル的にとつぜんフォルテになったり、ピアノになったりするのはバロック音楽の特徴である。(詳細はバロック音楽はデジタルであるのページを参照のこと) この第二合唱の三回の入りはそれぞれHmoll、Emoll,Gdurであり、特に三回目の入りはバセットヒェンの部分の唯一の長調部分であり、非常に新鮮な気分を与える。 歌詞の方は「放せ、やめろ、縛るな」と、二重唱を応援するような内容である。
つまりこの第二合唱はテキストとしては二重唱の応援であり、音楽的にはバセットヒェンの低音を補完し、聴衆を驚かす意味合いもあるのだろう。ハイドンが例の「びっくり交響曲」を書いて居眠りする貴族たちを驚かせたようなことをバッハもまたそれより前にやっていたのである。この点は冒頭合唱では第一、第二合唱がおだやかな対話形式となっているのとはかなり様相が異なっているといえよう。
掛留音の効果
第62小節でいよいよ二重唱も終わりにさしかかかり、ソプラノとアルトは下譜のような非常に効果的な掛留音を形成する。(アルトのCis音が3拍目まで残り、ソプラノのD音と衝突する)それまでソプラノとアルトは3回のフーガでの入りを構成し、不協和音もあまりなく、比較的穏健にハモってきたといえるが、ここにいたり、ついに掛留音により短2度で衝突する。

あたかも二人でこれまでイエスの捕縛の嘆きを歌ってきてついに力尽き、二人の歌はこんがらがってしまった、という印象を受ける。このあと再び二人はきれいな3度のハーモニーを形成し、最後は二人なかよくH音で終止して次の合唱が入ってくる。
Sind blitze,Sind Donner パート1 通奏低音の役割
第65小節よりテキストは一変する。それまでのシオンの娘たちのイエスの捕縛の嘆きから一転してユダへのうらみつらみとなる。「人殺しのユダ(別にユダが手をかけてイエスを殺したわけではないのだが、ユダの密告がなければイエスが十字架にかけられるきっかけもなかったわけだからこのように言ってるんだろう)なんか地獄に落っことしちゃえ!」というかなり過激な内容である。
このテキストの内容の変化を受けて曲はvivaceとなり、拍子も4/4から3/8へと変化する。これまで聴衆が低音に飢えていたのを待ってました、とばかりにバスから勢いよく始まり、あたかも業の火が燃え移るがごとく、順次上のパートが入ってくる。ここでは第一、二合唱総出での入りであり、シオンの娘たちも一緒に参加しているのである。シオンの娘たちにすればやっと第二合唱の応援が本格的になったから、ひとつ私達も一緒になってにっくきユダを地獄に落としちゃいましょうよ、ってな感じかな。いつの世も女性は恐ろしい!?
第65小節以降の着目点はまずなんといっても通奏低音である。この通奏低音、なんと第68小節からずーっとほとんど16分音符のオンパレードなのである。こんな曲、バッハ以前にあったろうか。バッハの曲でもこんな曲はあるだろうか。さらに興味深いのは合唱やオーケストラがベネチア学派のごとく、途中きれいに分かれるのに対し、通奏低音だけはまったく分離せず、第一、二オーケストラともに同じ音でぶっとばすのである。あたかもユダを地獄へ送るドライブの役割をしているのである。今もしユダがこの曲を聴いたらバッハ先生もさぞかし自分を恨んでいるんだなあ、と嘆息するだろうね。
Sind blitze,Sind Donner パート2 楽器の入りについて
この曲の65小節以降は最初入ってくる楽器は通奏低音のみである。第81小節にいたってはじめて木管、他の弦楽器が入ってくる。そしてここから合唱は二部に分かれるのである。つまりこうした楽器が入ってくることによりここからシオンの娘達と信じる人たちが別々な歌を歌い始めますよ、ということがわかるようになっているのである。まあ、この楽器の入りはシオンの娘達と信じる人たちの分離信号みたいな役割を果たしているのだろう。
実際この部分は耳で聞いていてもこの入りはおもしろいが、視覚的にも、休んでいたオーケストラがにわかに準備を始めてここから入ってくるのをみるのは結構感動するものである。ベートーベンの第九の第四楽章で合唱が始めて入ってくるときの視覚的感動と同じようなものだ。
Sind blitze,Sind Donner パート3 第104小節の休止について
周知のごとく、ここの第104小節の休止は「verschwunden(消えた)」を表現している。音符を消すことで稲妻と雷が消えたという歌詞を表現しているわけだ。とにかくこの曲の勇ましい各パートが急に終止を迎えてしまうわけだから、この一小節の効果は絶大なものがある。当然、それまでのガチャガチャした音の余韻が残っているわけである。実際にホールの音としても残っているだろうし、何よりも聴くものの耳にはそれまでの残響がたっぷり残っているはずである。そしてこの残響が消えるか消えないかというところで次の部分が入ってくるところがまた憎いよね。
この休止の直前の調性はDdurであるが、その次の部分はFisdurで入ってくる。この転調もまた効果的である。聴衆はまさかこんな調性で入ってくるとは思いもよらないからである。バッハの時代としては珍しい転調であり、やはりバッハがヴィヴァルディなどからしっかりと転調の概念を学んでいたことがわかる。
Sind blitze,Sind Donner パート4 最後の転調
曲の最後の部分の転調がまた効果的である。第133小節でEmollで終止したあと、なんとFdurで入ってくるのである。これもまたバッハの時代としては異例の転調といえよう。そして結局はピカルディ終止によりEdurで終止するのである。この曲の最後の部分は結局大規模なナポリの六であるといえよう。(下譜参照)
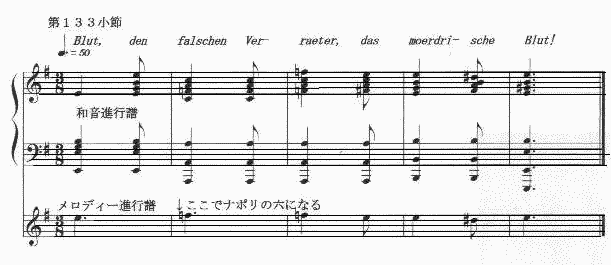
ここをクリック!
J.S.バッハ マタイ受難曲へ戻る
前ページへ
第34〜35番のページへ進む
合唱
Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?
稲妻と雷は雲間に消えたのか?
Eroffne den feurigen Abgrund, o Holle,
業火の淵を開け、おお地獄よ、
Zertrummre, verderbe, verschlinge, zerschelle砕け、滅ぼせ、呑み尽せ、踏みしだけ!
Mit plotzlicher Wut
突発する怒りで
Den falschen Verrater, das mordrische Blut!
不実な密告者、人殺しの血を。

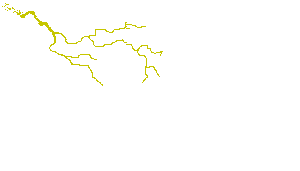
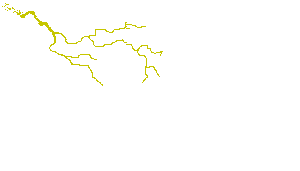

6世紀写本 ユダの改悛

グリューネバルト
辱められるキリスト