![]() パッヘルベルのカノン;バロック音楽入門
パッヘルベルのカノン;バロック音楽入門![]()
マイエッセイのページへ
音楽エッセイのページへ
パッヘルベルのカノンを初めて聴いたのは高校二年の夏だった。その一年近く前からなぜか突然クラシック音楽に目覚めて、図書館にあったレコードを片っ端から借り出して聴いていた時期だった。パッヘルベルという作曲家の名前もこのときはじめて覚えた。演奏はパイヤール室内管弦楽団、他にバッハの「音楽の捧げもの」、グルックの「精霊の踊り」とかがあった。
このパッヘルベルのカノンを初めて聴いたとき、それまで歌謡曲ばかり聴いてきた私は、世の中にこんなに美しい音楽があるもんだ、と思ったものだ。今から思えばパイヤールによってかなり厚化粧された演奏だったので特にそう思ったのであろうが。とにかく弦楽器の音色の美しさ、対位法(この頃この言葉を知ったばかりだった)というのはこんなにも美しい音楽を作り出すことができるものか、と本当に感激した。将来はぜひ作曲家になりたいものだ、と思ったものである。
パッヘルベルについて
パッヘルベルは1653年に生まれているから、かの大バッハよりは一世代前の人ということになる。(大バッハは1685年生まれ) 今でこそ彼の残した作品で有名なのはこのカノンだけであるが、もともとはオルガニストで、オルガンのための作品がたくさんある。バッハもパッヘルベルの作品を一生懸命勉強したようだ。
後に出現した大バッハがあまりにも偉大であるために、バッハ以前のオルガン曲はなんとなくかすんでみえてしまうが、パッヘルベルはオルガンにおけるコラールの扱い方について、パッヘルベル様式とでもいうべき独自の世界を作っている。
カノンについて
さて、カノンというのは同じメロディーを少しづつずらして歌っていくものである。小学校の時に習った♪あーきのゆーうーひーにーの「もみじ」や♪かえるのうたがーきこえてくるよーなんかがいわゆるカノンである。和音の構成が規則的になるように作られた曲(意図的であれ、偶然であれ)はカノンにすることができる。たとえば♪おーほしさーまーひーかーりーの歌なんかはカノンにして歌うことができる。きらきらお星の歌のカノンさらにこの曲は五度カノンといって調性をずらしたカノンにすることもできる。きらきらお星の五度カノン
パッヘルベルのカノンはその名の如く、全曲最初から最後までカノンである。弦楽器の三パートが2小節づつずれて全く同じメロディーを弾いている。しかしカエルのうたのように単純ではないから、耳で聴いただけではカノンであることを聴き取ることはまず不可能である。なんとなく同じメロディーが三回繰り返されているかなぁーくらいしかわからない。この曲は同じパターンが28回繰り返されるからある種の変奏曲といえなくもない。それにしてもあんな単純な和声からよくぞまあ、あれだけのメロディーパターンを作り出したもの、と感心する。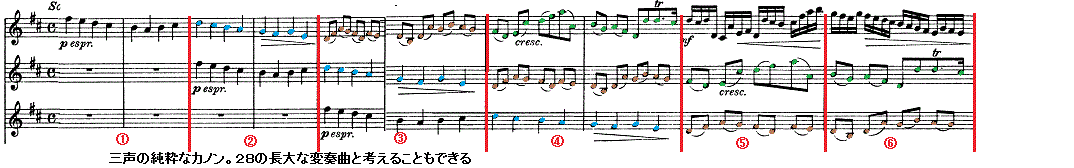
通奏低音について
このパッヘルベルのカノンの低音部(通奏低音という)はレ→ラ→シ→ファ♯→ソ→レ→ソ→ラを28回繰り返す。チェロバス奏者は演奏していて、飽きたり回数をまちがえたりしないもんか、と思ってしまうが、こうした低音部の繰り返しのパターンは、ルネッサンス時代の器楽曲などにおいてはよくみられ、グラウンドという名前がついている。低音が同じパターンを繰り返し、その間、他のパートがアドリブを含めていろいろなメロディーを演奏していくのである。「パッヘルベルのカノン」はこのルネッサンス期の音楽様式を踏襲しているのだ。
ところで、クラシック音楽というとアドリブのない、楽譜通りに弾かなければいけない融通のきかない音楽と思われがちであるが、実はバロック時代の頃までは演奏者のアドリブがかなりあった。楽譜には通奏低音と和音を示す数字が書いてあるだけで、あとはほとんど演奏者のアドリブ、という曲も多かった。(ちなみにこうした音楽のアドリブ的要素を排除しようとしたのが他ならぬかの大バッハである。彼はアドリブの達人であったにもかかわらず、自らの音楽では従来奏者のアドリブに任せていた部分も丹念に音符で埋め、アドリブの要素を排除していった。また古典派時代から始まったソロ楽器のコンチェルトなども当初はカデンツァの部分は奏者のアドリブにまかせられていることが多かったが、ベートーベンあたりからカデンツァもまた作曲家が予め書いておくことが多くなった。) グラウンドもまた、おそらくはかなりアドリブ的要素が多かったであろう。
パッヘルベルのカノンとジャズ
アドリブといえばジャズ。ジャズにおいても、このルネッサンスからバロックにかけてのグラウンドに相当する曲種がある。低音が同じパターンを繰り返し、その上を他の楽器がアドリブで次々といろいろなメロディーを出していくものである。そのやり方はバロック期のグラウンドと良く似ている。つまりバロック音楽とジャズは結構共通点が多いのである。
バロック時代にはきっと現代のジャズのような感覚で、聴衆はおしゃべりをしたり、一緒に歌ったりしながら演奏を聴いていたのであろう。だから、少なくともバロック音楽をメニューとする音楽会では、しかめっつらをして咳払いもはばかれる、という現代のクラシックの音楽会の雰囲気はいけないように思う。
さて、パッヘルベルのカノンは結構いろいろな編曲がなされている。グラウンドバスによるカノンであるから、ジャズっぽい編曲は十分に可能である。あるいはそんなCDも出ているのかもしれない。
パッヘルベルのカノンが有名になった理由
この曲が数あるパッヘルベルの曲のうちで突出して有名なのはおそらくパイヤールの演奏によるものが大きいのではないかと思っている。彼はこの曲をロマン派風に、およそバロックとは縁遠い演奏をしている。ヤマ場ではクレッシェンドし(バロック期にクレッシェンドの概念はなかった)、途中にチェンバロを入れ(チェンバロはバロックの楽器だが、この使い方はまるでポールモーリアのチェンバロの使い方のようである。そもそもバロック期にあんな分散和音なんていう概念はなかったんだから)さらにヴィオラにも分散和音を入れ、最後は弦の一部をオクターブ上げて終わらせている。
したがって彼の演奏ははっきりいって素顔がわからないくらい厚化粧をした女性のようなものなのであるが、しかしこれがなかなかいいのである。(バロックは古楽器で演奏しなければならないと思っている人にとっては聴くに耐えないだろうが) パイヤールの演奏を聴き慣れた耳で、あらためてバロックの原型に忠実なあっさりとしたこの曲の演奏を聴くと何となく物足りなく思ってしまうから不思議である。女性でももともと美人なのにお化粧をするとまた新たな美しさを醸し出す人がいる(石川さゆりみたいな人![]() )が、このパッヘルベルの曲なんかもそんな女性のようなもんなんだろう。
)が、このパッヘルベルの曲なんかもそんな女性のようなもんなんだろう。
パイヤールのあの厚化粧の演奏がなければこの曲もこんなには有名にならなかったかもしれない。実際によくBGMや有線放送なんかで流れるこの曲の演奏はパイヤールのものが一番多いような気がする。
バロック音楽入門としてのパッヘルベルのカノン
パッヘルベルのカノン(とりわけパイヤール指揮のもの)はバロック音楽入門として最適である。本当に美しくていい曲だとクラシック音楽を27年聴いてきた今でも思うし、演奏するにしてもそれほど困難な曲ではないだろう。こんなわかりやすい曲からバロック音楽の森に分け入り、バッハのマタイ受難曲のような傑作にたどりつく人が少しでも増えてくれたらと思う。
ページトップへ