| <声楽が表われるまでの経過句・総論> 第187小節からは次に声楽が表われるまでの経過句となる。ここのオーケストレーションはまさにベートーベンの面目躍如といった形で、各楽器がそれぞれの役割をはたし、全体としてすさまじいばかりの音響となる。より大規模なオーケストレーションを知っている今日のわれわれ眼からすれば驚くべきことではないかもしれないが、当時の会衆はこんなオーケストラを聴いてどう思ったであろうか。 とにかくここのところのオーケストレーションはオーケストラの持つ可能性を大きく飛躍させたと言ってよいだろう。オーケストラってこんな表現までできるんだ、と当時の会衆は驚いたに違いない。 ベートーベンが開拓したオーケストラの可能性への挑戦は後世の作曲家に引き継がれ、ワーグナーでほぼ頂点を極めたといってよいのではないだろうか。 なおこの経過句は後にもたびたび使用されることになるが、むろん初出のこの部分が一番複雑なオーケストレーションとなっている。そしてこの経過句が出てくるたびにオーケストレーションやリズムは異なるように設計されており、ベートーベンが同じ主題を何度も再使用しながらも決して聴衆を飽きさせることがないようにさまざまな工夫をこらしていることがのちのちの解剖でわかってくるであろう。 <各論> ここのオーケストラにおいては主役は木管楽器である。すなわち最初こそ木管、金管、弦三者ともに旋律ならびにその和声を奏でているのであるが、まず弦楽器(1stヴァイオリン)が第189小節で脱落し、金管とティンパニーが第193〜4小節で脱落し、といった具合に旋律を奏する楽器が減っていき、中途からはついに木管楽器のみとなってしまうのである。(原曲通りに演奏すると特に金管楽器が脱落してからは急にオーケストラがスカスカになってしまうので、このあたりは演奏によっては金管を少し補う場合もあるらしいが私はこのスカスカになるあたりがまた好きなのでここは原曲通りに演奏するのがよいと思う) それではこのあたりの楽器の間引き状況をMIDIで確かめてみましょう。伴奏を担当する弦楽器を全部はずしてより間引き状況がはっきりするようにしてみます。 ♪第187小節〜木管、金管楽器のみ 弦楽器を取り去ってしまうとこの部分がいかに急激に管楽器が間引きされていくかがよくおわかりであろう。ベートーベンがなぜこのような間引きのオーケストレーションを行ったのかはよくわからないが、しかし途中から金管楽器が抜けることによって伴奏を担当している弦の細かい音が引き立つようになり、金管に隠れていた木管楽器のメロディラインもはっきりする(特に一番目立つトランペットは直接メロディラインは吹いていない)というメリットはあるのでこういった効果をねらってのことだったのかもしれない。 次に先ほど取り去ったこの部分の弦楽器部分だけを取り出してみる。前述のようにここでは弦はあくまでも引き立て役であり、ことに2ndヴァイオリンとヴィオラはひたすら16分音符の細かい音をきざみ続ける。これら両パートがいかに地道に伴奏を行っているかを聴いていただきたい。 ♪第187小節〜弦楽器パートのみ さて、この複雑なオーケストラは第201小節において単純な二つの主題に収束する。すなわち下譜のように木管群がユニゾンで奏するテーマA群と金管ならびに弦がユニゾンで奏するテーマB群の二主題である。 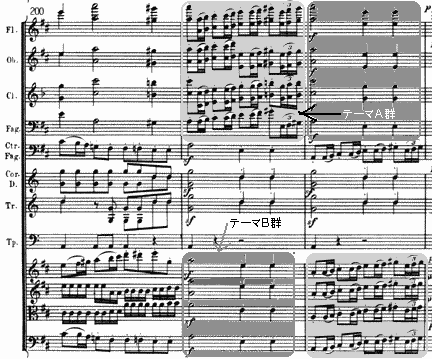 テーマA群とB群は楽器を代えて入れ替わる このように複雑に展開した曲がその頂点においてきわめてシンプルな形式や和音を取ることはベートーベンの特徴といってもよいもので(ベートーベンの影響力その2のページ参照のこと)ベートーベンのさまざまな曲に類似の構造を見出すことができる。 ところでこの二つの主題は上譜のように、木管群と弦楽器群とが入れ替わって二回出現するが、テーマBが音の大きい金管楽器によって繰り返されており、それが目立ってしまうので、正直いってこの楽器交代による効果はベートーベンのねらい通りには出ていない。第九作曲当時すでに彼の耳はほとんど聴こえない状態であり、頭の中に響く音だけで作曲していたための限界といえるかもしれない。 続いて第203小節からのところ。それまでフォルテが続いていたのが一転してピアノに転じ、旋律はフルートからオーボエへと受け継がれ、次のフォルテへの中休みとなる部分である。 ここの部分の特徴は何といっても転調の見事さであろう。ことにエンハーモニック(異名同音)の技術を用いた以下の部分は感動的である。  ♪このあたりの和音をピアノで聞いてみる ♪このあたりの和音をピアノで聞いてみるエンハーモニックを使用して和音はHdur第二転回形→Fisdur→Esmoll第一転回形と転調する。 その後は半ば強引に再度Adurの和音へと転調していき、また再度冒頭の不協和音が出現し、ソリストを迎えることになる。最後にこのページに相当する部分の「第九」を聴いてみましょう。 ♪第187〜207小節 |