| <第一主題の登場> 第92小節より有名な”第九のメロディ”が本格的に登場する。単純で歌いやすく、なおかつ無限の変奏の可能性を秘めているすばらしい旋律といえよう。(下譜参照)  この旋律はソリストが入ってくるまでに計4回繰り返される。最初はチェロバスで、次にヴィオラとチェロで、その次に1stヴァイオリンで、最後はフルオーケストラで、という具合に執拗に同じ旋律が繰り返されるが、新たにこの旋律が出現するたびに曲の雰囲気が変わるように設計されているので聴いていて飽きが来ることはまったくない。 ここではこの一回一回について解剖していきたい。 まずはチェロバスから。そもそもチェロバスが単独でかくの如く旋律を奏でるなどということ自体がまったく新しい発想であった。ベートーベンはチェロバスによるレシタティーボを延々と書いてきて、おそらくここでそれならばアリアもチェロバスに歌わせてしまおう、と考えたのである。つまりバロック期から発達してきたレシタティーボ→アリアという声楽曲に普遍的なパターンをこの「第九」という交響曲においても実践したのである。これまでは脇役に甘んじていたチェロバスをその主役に置いて。 このチェロバスによるファーソララソファミという有名な旋律の提示は実はアリアだったのだ!! フルオーケストラによるカデンツのあと、この旋律は聴こえるか聴こえないかといった音量から入ってくる。そして徐々にクレッシェンドしてきて頂点に達し、さらに波が引くように再度ピアニッシモで終る、というパターンである。ベートーベンの影響力その2のページでも書いたけれども、これほどにダイナミックレンジの広い旋律はおそらくこの”第九のメロディ”が最初ではなかろうかと思う。 この部分の演奏解釈はすでに固まっているようで、どんな演奏を聴いてもほぼ同じようなパターンを取る。確かにこの旋律の演奏はこれより他はやりようがないだろうね。 次にヴィオラとチェロで二回目のこの旋律が現れる。音域もオクターブ上となり、チェロにとっては高い音域なのでチェロのこの音域独特の味が出るようになっている。 この部分の対旋律はコントラバスとファゴットである。コントラバスはチェロがヴィオラと一緒に旋律を歌う方に逃げてしまっているので一人バス音域を担う。こうしたパターンはベートーベンでは珍しくはないのだが、通常はチェロ+コントラバスでオクターブで演奏されるバス音域がコントラバスだけになると乾いた無機的な独特な音になる。これはこれでベートーベンがあえて意図した効果といえる。 ここでこのコントラバスの対旋律を聴いてみよう。この対旋律は主旋律の強弱に合わせ、主旋律がフォルテになると高音域に行き、ピアノになると低音域をさまようようになっている。高音域では弦の緊張が高まるコントラバスの性質をうまく利用した音の強弱と音高との見事なバランス感覚を見て取れる。 ♪第116小節以降〜コントラバスによる対旋律 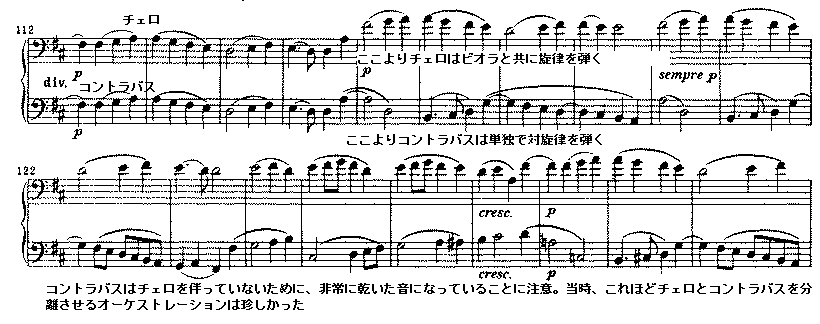 ファゴットは以下のような対旋律を吹く。 ♪第116小節以降〜ファゴットによる対旋律 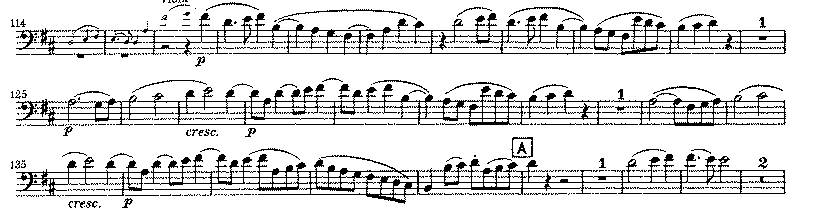 結局チェロバス+ヴィオラの旋律にコントラバスとファゴットの対旋律がからまった見事な三重奏となっているのである。 ♪第91小節〜140小節 その次は1stヴァイオリンによりこの第一主題が現れる。ヴァイオリンが加わることにより和声はより重厚なものとなってゆく。 ここでは対旋律は一挙に4種類に増える。第91〜140小節でコントラバスで奏でられた対旋律はそっくりそのまま2オクターブ持ち上げられて先ほど主旋律を歌ったチェロとヴィオラが担当するようになる。(一部オクターブ下がる部分もある)コントラバスは今度はより単純な対旋律を奏でるようになる。2ndヴァイオリンは主旋律にまとわりつくような対旋律を奏で、ファゴットは主旋律のそれぞれのフレーズの後半をオクターブ下でなぞるだけの単純な音型となる。ここでそれぞれの対旋律を個別に聴いてみよう。普段は全体の雰囲気を盛り上げる脇役に徹しているこれら対旋律たちがいかに魅力的なパートを演奏しているかがおわかりいただけると思う。 ♪第139小節〜2ndヴァイオリンによる対旋律 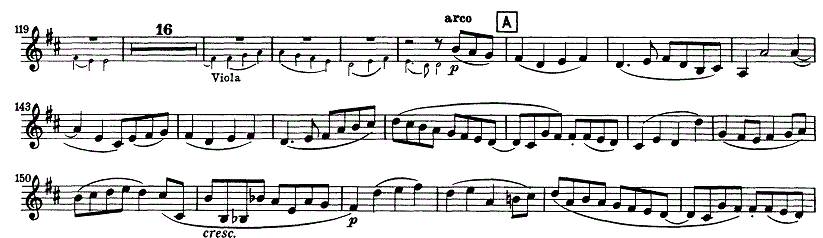 ♪第140小節〜コントラバスによる対旋律 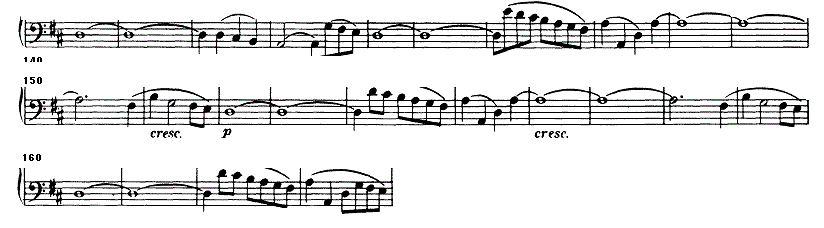 ♪第140小節〜ファゴットによる対旋律 ♪第140小節〜チェロ+ヴィオラによる対旋律 それではここでこの部分の全体を聴いてみましょう。 ♪第139〜163小節全体 すばらしい弦のハーモニーですね。特にフルオーケストラへと向かうこの部分の最後のあたりのクレッシェンドがたまらん。 クレッシェンド、デクレッシェンドという概念はバロック期の音楽にはなく(バッハの音楽にさえない!)古典派以降に生まれた新しい音楽概念であるが、ベートーベンの「第九」はこの新しい音楽概念を主題そのものやあるいは曲全体の雰囲気の盛り上げなどに実に効果的に使用していることがわかる。 なお、ワーグナーはやはりベートーベンの「第九」のこの部分に感動したと見えて、「タンホイザーの大行進曲」でベートーベン同様、クレッシェンドを効果的に用いている。 最後はいよいよフルオーケストラによるこの主題による大合奏。弦のハーモニーがクレッシェンドし、頂点に達したところでこのフルオーケストラとなる。 ここのオーケストラは複雑に見えるが、よくよくスコアを見ると構造的にはきわめて単純であることがわかる。すなわち管楽器が総出で和声を含む主題を吹いているのに対して、弦楽器は重弦を用いてリズムをきざんでいるという二通りのパターンしかないのである。 こうしたオーケストレーションにおける各楽器の集約化は後にチャイコフスキーが得意とした手法で(チャイコフスキーの甘美な旋律についてのページ参照)、ベートーベンのこの部分はその萌芽と言えなくもない。ベートーベンの近代オーケストレーションの発達への寄与度はむろんきわめて高いものがあるが、後の時代に発展させられるべきさまざまな工夫をし、オーケストラの未来への可能性を示した(つまりオーケストレーションというものを決して完成はさせなかった。ここがモーツァルトとの大きな違いで、モーツァルトの場合は彼独自の閉じた世界を築き上げたが、ベートーベンの場合は後の時代へと開放された世界を作ったのである)という点こそが彼の最大のオーケストラへの貢献であろうと思う。 それではここでまず旋律とその和声の部分を聴いてみよう。かの有名な旋律は木管、金管総出でにぎやかに演奏される。和声としてはやはり”ホルン五度”が目立つ。これはこの旋律ならば必然的なものである。 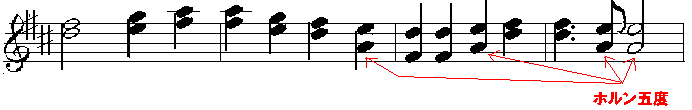 ♪第164小節〜旋律とその和声のみ 弦の伴奏はティンパニーとともに ♪第164小節〜弦の伴奏部分 重弦のほんの少し遅れるタイムラグが何とも心地よい。これまで3回ポリフォニックで出現してきたこの”第九のメロディ”は、4回目に至って古典派的純ホモフォニックな形で出現するのである。 ♪第164小節〜フルオーケストラ |