| Cohrs版解説 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | R.Maunder Mozart's Requiem5へ戻る |
| R.Maunder Mozart's Requiem7へ進む |
| バッハのフーガの技法、モーツァルトのハ短調ミサ、シューベルトの未完成交響楽、ブルックナーの第九、マーラーの第10交響曲、ベルクのLulu,ブゾーニのファウスト、などの音楽的なトルソは、終わりのない魅力を醸し出している。いくつかのフラグメントは伝記的理由で遺された。たとえば、さくしゃが新たなプロジェクトに向かったとか、あるいは、作曲の途中で死んだとか。その他は単純に、他のものは、当初から、さらなる精緻化や作曲上の研究を意図していなかった。しかしその他は、 完成されたが私たちには不完全な形でしか残されなかった 作品のなごりを示している。 こうしたフラグメントの版を演奏することが適当であるかどうかは、ケースバイケースで、慎重に考慮されるべきである。現存する資料と同様のものすべてを心に思って。多くのドグマティストは、カテゴリー的に、作品の完成を非難する。それらがオリジナルなソースを決して研究していない時には。こうした論争は、音楽の生きいきとした経験にはふさわしくない。しかし、批評家が、それがシューベルトの未完成交響楽、ブルックナーの第九、マーラーの第10交響曲演奏版を作るための冒涜であるかどうかという論争を続ける間は、こうしたアレンジは、コンサートホールで見出され、音のレコーディングの役にたつ。 確かに、こうした指揮者間、リスナー間の論争において、モーツァルトのレクイエムは、いくつかの奇妙な理由のために、常に例外扱いをされていた。一貫して、こうしたフラグメントは、我々に”作品”を構成するものとしての片手間の完成であるが、特殊なステイタスを与える。音楽が気や美学は、ダブルスタンダードの罪を持っていた。現代の作家がLepold Nowvakに、なぜ一方で、その他の作品の完成を拒否するのか、同時に、モーツァルトのレクイエムを作るための付加において、黙従するのか、と問うたら、彼はこう答えるだろう。「モーツァルトは違うんだよ。レクイエムは200年の歴史を経ている。さらに、ジュスマイヤーは、モーツァルト自身の意図を知っていて、その原則を基礎とすることに反対することは、許されないんだよ」と。 モーツァルトの時代、さらなる問題がある。すでに知られているようにレクイエムはWalseggからの依頼によるものであった。彼は、それを彼の妻アンナのための葬式で使うつもりであった。彼女は、その直前に亡くなっていた。そしてそれをモーツァルトの名は伏せて、彼の代理人の名を使っていた。彼は、前払いで25デュカを支払っていた。さらに25デュカの上乗せを予定していた。不幸なことに、モーツァルトは、作品が完成する前に死んだ。どうすべきか? モーツァルトの未亡人コンスタンツェは、前払いを払い戻すことは困難だった。そして、緊急に第2の掛け金を必要とした。50デュカは、225ギルダーに相当し、作曲者の3かげつぶんの稼ぎであった。 モーツァルトは、1791年12月5日に死んだ。そして、その5日後の12月10日に、フラグメント作品が演奏された。彼自身のメモリアルサービスとしてセクションは、INTROITとKYRIEであった。オーケストレーションの仕上げは、モーツァルトのもっとも古い弟子であったFranz Jacob Freystadtlerと彼の若い友人で、コピーストで作曲家であったジュスマイヤーが担当した。Critical Reportによれば、写本は、2人の書記がいた証拠があり、書記の同定は、知られていなかった。そして、Micael Lorenzは完全に、Freystadtlerによるレクイエムのスコアの可能性を否定した。12月21日、アイブラーは、自筆譜を受け取った。1792年のレントの頃までにそれを完成させることを条件に。もはや、2か月しか時間は残されていなかった。ほどなく、彼はあきらめた。理由は不明である。 p286 ジュスマイヤーは最後の仕上げをした。我々が知っているように、モーツァルトは彼を、そもそも作曲家として扱っていなかった。コンスタンツェは、彼を単に、モーツァルトの筆跡をマネすることができるということで選んだに過ぎなかった。非常なプレッシャーのもとで、ジュスマイヤーは1792年2月の終わりにスコア完成させた。(作品のコピー全体が、1792年3月4日に、ウィーンのプロシャ大使に渡されたという記録がある)。そして、カバーにはモーツァルトの署名が偽造されてさえいた。伯爵は、モーツァルトによる作品を命じていた。そしてそれが、彼が得ようとしていたものであった。ゆえに、ジュスマイヤーは、タイトルページに、”di me w.A.Mozart m[anu] p[ropria]1792という日時としたのである。モーツァルトが1791年に亡くなったことは知られていた事実であったにも関わらず。喜んだ受領者は、すぐに、スコアの彼自身のコピーを作り、著者として彼自身の名前を刻んだ。これは、今日にまで続いている”con game"の最初を位置付けている。我々は、通常、”モーツァルトのレクイエム”として作品に言及しているが、より正確には”レクイエムフラグメント”であり、さらに言えば、作品を完成させた音楽家や校訂者のことは、まったく言及されていない。 Known and unknown Models for Mozart's Requiem Wolffは,モーツァルトはレクイエムを書くにあたり、教会音楽の新しい革新的な様式であり、明らかに、歴史的な死者のためのミサ曲や手に入るさまざまな曲を参考とした、と指摘している。それらは彼自身の時代の最高の音楽と同程度の葬儀音楽を作りながら、ジャンルの熟考のレビューをしている。 Wolffによると、INTROITUSは「大部分が、1737年に書かれたヘンデルの「キャロライン王妃のための葬送アンセム」HWV 264の葬儀の賛歌の最初の合唱に主に基づいている」。 HandelのDettingen Te Deumの最終コーラスは、KYRIEのモデルとなった。 Hartmut Krones, Leopold Nowak、その他によって確立されたように、モーツァルトのレクイエムはさらに、Gassmann、Gossec、Michael Haydnの死者のためのミサ曲からの引用がある。また、大バッハのロ短調ミサ、クリスマスオラトリオ、マニフィカト、C.P.E. BachのAuferstehung und Himmelfahrt Jesu、そしてGeorg Reutter the youngerのMissa S. Caroliも引用している。 しかし、モーツァルトの最も重要なモデルの1つは未知のままであり、今日まで言及されていない。 それは、ペルゴレージの1734年作のヘ短調のStabat Mater である。この作品は、当時非常な成功を収め、さまざまな版で出版され、多くの図書館に写譜され、世界的な音楽コレクションとなった。さらに、これによるさまざまなパロディが存在する。たとえば、Giovanni Paisiello, Johann Sebastian Bach (Psalm 51 “Tilge, Hochster, meine Sunden”), Johann Adam Hiller (1776), Joseph Eybler (c. 1800) and Alexej Fyodorovich L'vov (c. 1830)などである。校訂チームによる好奇心をそそる編曲も現存している。 Salieriによる4声部作品、Susmayrによって追加された木管楽器の部分、von Seyfried(1831)によるトロンボーン、全体がOtto Nicolai(1843)によって改訂され、編集されている。古いペルゴレージ・コンプリート・エディション(フィレンツェ、1942年)は、Dies iraeとしての匿名による編曲を出版している。それは、ボローニャで発見された合唱のための編曲からのもので、2本のcorni da cacciaを持ち、ハ長調のラルゴが導入曲となっている PergolesiのStabat Materは、レクイエムのモデルや先例として、さらに興味深いものである。 モーツァルトは、1742年の初めに初めて登場したオリジナル版を知っていた可能性があり、遅くともHiller(1776)の編曲からそれをよく知っていたであろう。 Stabat Materの始まりは、レクイエムの冒頭を聴衆に思い出させる(また、長調に変形されて、Recordareの始まりにおいても)。しかし、特に顕著なのは、古いペルゴレージの版からの、Dies irae編曲の最終章における同一性である。そこではLacrymosa と Amenが、モーツァルトのSEQUENTIAに対応している。Lacrymosaの最初の動機がまったく同様であり、特に、ペルゴレージによるAmenのフガートの始まりは、Plathによって発見されたレクイエムのAmenスケッチとほぼ同一である。モーツァルトはこれを3/4拍子に変更しているが。 ジュスマイヤーの補筆 ジュスマイヤーの補筆による版は、Nowakのよって、1965年にNMAにて出版された。それはしばしば、Wolffによる批判の対象となっている。 「彼の労作の結果は、驚くべき良き楽想と不十分な達成との特殊な混合である。。言うまでもなく、かなりの半可通と誤解の言及は、リスナーに彼のやり方を知らしめる意図がある。彼の付加は確かに、均一なスコアを産生しない。・・・彼は、時間も関心もなかった。対位法に挑戦するためのテクニカルな資格もなかった。・・・ジュスマイヤーは、疑いなく、多芸で有能なアシスタント、そして経験ある作曲家ではあったが、彼は決して、真の巨匠ではなく、事実、コンスタンツェは彼をモーツァルトの弟子のひとりとしてしか見ていなかった。これこそが、なぜ彼女がすぐにジュスマイヤーに自筆譜を渡さなかった理由である。」 一方、Wolffは、こうも言う。 「この非常に貴重な歴史的文書は、唯一の現存かつアクセス可能なジュスマイヤーの付加であるだけでなく、その他に、モーツァルトのオリジナルであった再発見された音楽的楽想の可能性を差し出す唯一のソースである。」 p290 Sanctus,Benedictus,Osanna,Agnus Deiはジュスマイヤーによって書かれたが、今日では失われたスケッチをおそらくは使用していた。そしておそらく、KYRIEにおけるモーツァルトの指示の使用も。そこで、作品は少なくとも、真実の結論を明らかにする。以下のTableは、ジュスマイヤーの作品の外観を表している。 INTROITUS、KYRIE Requiem 声楽と通奏低音はモーツァルトによる。器楽化はモーツァルトが始めているが、おそらくはすべてではない。 Kyrie 器楽化は、知らざれざる2人による。最終版はジュスマイヤーによる。(以下略) Wolffの提案するように、Susmayr補筆でモーツァルトの痕跡を見つける可能性がある場所を知りたい人は、モーツァルトが作曲構造の出発点として使用したバスラインとボーカルパートから始めるのが一番良いであろう。ここでのモーツァルトの嗜好における最も強い論議は、全体の統一を築くための、初期のパートからのモチーフの使用である。そのテクニックは、Susmayrの残した作品から明らかなように、彼がマスターできずに終わったものである。 例えば、Agnus Dei の最初の合唱バスパート上に確立された作品の分析をする学者は、レクイエムのテーマを引用する。それは、モーツァルトによって発展させられた、作品の多くの場所で出現する対位法の形式である。サンクトゥスではさらにつながりがある。初めのソプラノの部分は、Dies iraeの最初の長調としての変奏以外の何ものでもない。 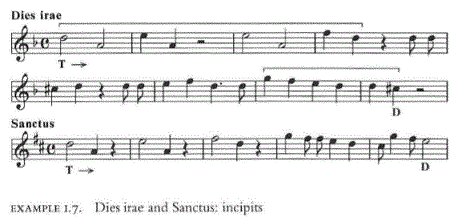 Osanna のフーガの主題は、Quam olimフーガの主題の変奏である。Benedictusの冒頭は、モーツァルトが彼の弟子のBarbara Ployerへの練習帳にメモしたテーマと同一である。 このテーマの最後の句は、未完のハ短調の荘厳ミサ曲K427のIncarnatusを思い起こさせる。確かに、Susmayrはこれを知らなかった。さらに、最終的には、作曲家がOsannaのフーガに戻ってブリッジを形成しようとしたかもしれない厳粛な形が現れる。それは、 INTROITUSの "et lux perpetua"という言葉に類似した形で先に現われた形である。こうした、耳で区別し得るなヒントとは別に、予定された接続の例として取り上げることができるさらに小さな詳細がある。例えば、Agnus Deiと同様、Benedictusの始まりにある連続的な16分音符の形は、Lux aeternaや最終フーガに付随する細かい音形と結びつく。このような要素は、レクイエムの全体のボーカル・セッティング内容が、モーツァルト自身によって予め作曲されていたという印象を支持している。そうであれば、Susmayrが持っていたこうしたことに対応するようなスケッチは、アクセス不可能または完全に失われたとみなされなければならない。 Earlier Editions and their Intentions Susmayrの声部補筆、彼の活気のない器楽作法と彼が作曲したセクションのインスピレーションの欠如は、しばしば批判を巻き起こした。しかし、今日入手可能な新しい版は―そして机の引き出しの中にあっていくつかの出版されなかった作品―作品の問題へのアプローチへの異なった戦略を提示する。Franz Beyer(1971)とH. C. Robbins Landon(1990)の新しい版では、Susmayrの補筆の意図を保っている。Richard Maunder (1988)、Duncan Druce(1993)、Robert Levin(1994)の新しい版は、Susmayrの補筆に関して、より批判的である。DruceはSusmayrのテキストの修正、編集だけでなく、Lacrymosa未完成部分の続きを、彼自身で新しいアレンジをしている。Hans-Josef Irmen (1978) は、Amen、SANCTUS、Agnus Deiをパロディーで置き換えた。SANCTUSのために、「エジプト王タモス」K. 345を、 AmenとしてVesperae Solennes(K. 339)のLaudate pueriを、Agnus DeiはB flatのMissa Brevis(K. 275)を当てた。 Robbins Landonの最後の版は「混合版」とみなすことができる。 それには、Lacrymosaまで、Eyblerのすべての補筆が含まれている。 EyblerはLacrymosaまでの補筆のほとんどを既に完成させていた。大事なところの前で筆を折った。彼の高い能力の例として、ここではDies iraeのトランペットとティンパニが挙げられる。Eyblerは金管楽器の補助とともに合唱の残りを完成し、合唱の肌理はより透明に聞こえるようでありティンパニのエントリはより劇的である。一方、Susmayrは金管楽器の持続的な音で合唱を支えようと考え、そうすることで声楽部分をカバーした。 Wolffが示しているように、Susmayrは時にはEyblerのアイデアのいくつかを使って、時にはそれを悪化させて修正することもあったが、彼はそれらを完全に無視して、自身の手馴れたオーケストレーションに置き換えた。しかし、Lacrymosaに続いて、Robbins Landonは、純粋なSusmayrのテキストを単純に再現したので、彼の版は内部の二分法によって傷つけられている。これに加えて、Robbins Landonは、しばしば批判されたSusmayr補筆の要素を温存した。SanctusとOsannaのはともにD majorであり、BenedictusはB flat majorである。 Quam olim fugueのモデルに従えば、D majorでのOsanna の繰り返しが期待されただろう。しかし、SusmayrはB flat majorとしてそれを繰り返している。 Robbins Landonはこの状況を残した。結局のところ、その訂正は、おそらく、モーツァルトの前述の変化した動機を利用して、ベネディクトゥスの終わりからオサナに新たに作曲されることとなった。 Richard Maunderは、サンクトゥスとベネディクトゥスの両方を真実ではないとみなし、完全にそれをなくすことを提案した。しかし、彼は自身のスコアへの補足として、これらのセクションのSusmayrの補筆を追加し、レクイエムを未完成として、あるいは指揮者に、これを演奏するかどうかをまかせることとした。一方、Maunderが作品のために行った新しいオーケストレーションは、SusmayrのSanctus、Benedictus、Osannaとはまったく一致していない。 Duncan Druceはもっと根本的な解決策を見出した。彼はモーツァルトのテーマであったと認められているものについて、ソロカルテットとともに全く新しいベネディクトゥスを作曲し、OsannaのDmajorへの移行を作曲することができたた。残念ながら、テーマとは別であり、結果は完全にモーツァルト自身の作品のヒントを捨てしまっている。 Wolffが提案しているように、シュトマイヤーへの最も痛烈な批判は、モーツァルトのスケッチをうまく利用できないと思われたことである。その例として挙げられるのが、Susmayrがやや不器用なやり方で書いたSanctusである(興味深いことに、彼は数年後に自身のニ長調のMissa Solemnis SmWV 106のSanctusのために再びこの楽章の冒頭を使用した)。モーツァルトとSusmayrの間の断裂は、バスパートにおけるCと(その他の声部の)C♯の醜い関係によって印される。BeyerとDruceはこれをカバーように試みたが、トランペットにおけるはっきりとしたファンファーレとともに、むしろ失敗に終わった。 Robbins Landonはこの影響を軽減しようとした。レヴィンだけが彼のリアリズムの中で、Wolffの洞察に従った。これは純粋に和声的な問題であり、元のスケッチへのSusmayrによる誤解の可能性があり、バスパートのC音が、アルトのA音で置き換えられている。 また、Osannaのフーガは、Susmayrが扱いきれなかった元のスケッチを基礎にしている。4つのパートすべてにおけるテーマの提示の後、彼は短い、むしろ不器用な終わりを追加しただけである。 BeyerとRobbins Landonに対抗して、DruceとLevinは両方とも、このスケッチを完全なフーガに盛り込むために十分な企画をした。だがそうすることに、Druceはあまり成功しなかった。なぜなら、彼の版は、同じようなモーツァルト自身のフーガよりも長く(例えばKyrieフーガ)、レクイエムの調和と様式の限界を超えているためである。Levinのフーガはわずか58小節しかなく、短くてシンプルである。しかし、ここでは厳密なフーガが期待されるが、Levinはテーマからは独立した楽器のエントリーを導入している。また、このセクションにクラリネットを導入するという彼の決定は、むしろ奇妙である。彼は、モーツァルト自身が、F管のバセット・ホーンをニ長調の楽章に使えなかったために、もはや使用されないG管を愛用していたと主張している。他方、SusmayrはF管のバセットホーンを、♯が3つつくSanctusで使用していた。 Lacrymosaを締結するAmen fugueは、D minor(Kyrie fugue / Amen fugue / Cum sanctis fugue)のレクイエムとその対称軸の構造を明確にする上で欠かせないものとみなされなければならない。しかし、Susmayrは、2小節のアーメン終止を好み、精緻化して使用すべきAmen fugueを省いた。彼は、モーツァルトの意図を何も知らなかったわけではなく、むしろ、モーツァルトが非常に頻繁に彼にワークアウトについて語っていたので、厳密なポリフォニー書法への要求に応えられなかったのである。そして、モーツァルトが意図していた反転、縮小、回文といったフーガのプランも作れなかった。モーツァルトのスケッチからも分かるように、アーメン・フーガの主題は、レクイエムの最初の動詞の主なテーマを正確に逆転させたものである(Wolff)。一方、Susmayrの弁護をすると、Eyblerは、彼がコンスタンツェからもらっていたスケッチをすべて返さなかった可能性がある。 (おそらく、Amenのスケッチは、アイブラーの所有にとどまっていたのだろうか?)しかし、スケッチの配置は、レクイエムのテーマを逆さにして使用したことによって、懐疑的である。 p293 にもかかわらず、BeyerとLandonは、アーメンフーガをつかっていない。かれらは、1960年に発見されたこのスケッチの存在を知っていたにもかかわらず。1991年の新しい版で、Landonは、Amenスケッチが、より早期の作品である「ミュンヘンのキリエK341 」に帰属すると言い出した。Alan Tysonが、透かしを比較して、1987年に、Amenスケッチは、モーツァルトが1791年の9月の終わりに使い始めたのと同じtypeIIの紙に記されていた、と説明した事実があるにもかかわらず(Landonはこの事実を知らなかった可能性もある?)。 Maunderは、おそらく一番、最初に、このフーガに傾注した。彼の版は、その長さと簡潔さに説得力がある。たとえ、それが転調を含んでいても。Levinが、18世紀のこの種のフーガが同じ調性で書かれているとし、それゆえ、Lacrymosaだけでなく、セクエンツィア全体に対する安定した結論を見ていたように。さらに加えて、最後が単に6小節というのは、あまりにも短すぎる。 Druceのフーガは、大胆なブレイクや興味深いシンコペーションを含んでいる。様式的にそれは、ブラームスのドイツレクイエムのように響き、そして、127小節という長さは、あまりに長く、作品のプロポーションを壊してしまう。 Levinは、中間の道を取った。彼のフーガは、88小節であり、Maunderのより若干長く、より深い対位法となっており、より長い終止セクションを含んでいる。しかし、Lacrmosaに引き続き、それは、あまりに豊かで名人芸的に見える。さらに、それは伴奏の器楽に、独立したエントリーを含んでいる。厳密にヴォーカルフーガであるレクイエムフラグメントにおける、モーツァルトのフーガに対抗するものとして。そこでは、、器楽はヴォーカルパートによってのみサポートされているが、わずかな例外(トランペット、ティンパニ、バス)とともに、それらはフガートのパッセージにおいて、オブリガートの役割において稀に現れる。 モーツァルトのKacyrimosaの第8小節後の絶筆の後、DruceとMaunderは、フーガまでの彼ら自身の経過句を書いている。一方、Levinは、ジュスマイヤーの版を保持し、単に該当する詳細において、最後のみ変更を加えている。Druceは、アイブラーのスケッチを使って、2つのさらなる小節を加えている。しかし、彼の器楽化は、そのかんそうや経過の長さがやはり、作品の様式的なパラメーターを超えるようになってしまう。すべてで、彼のLarymosaは36小節となる。Maunderは、彼自身の作曲をさらに続けているが、24小節であり、ジュスマイヤーより6小節分短く、様式的にもより説得的である。 Hans Josef Irmenは、モーツァルトでモーツァルトを完成させるという魅力的なアイデアを持っていたが、このパロディー技法のために選んだモデルは、1773年と1780年の作品から選んだもので、結果はたとえば、Alois Schmitt による1901年完成の、ハ短調大ミサ曲のパスティッチョのように、確信的なものではない。Irmenの最初のもっとも興味深いアイディアは、おそらくは、セクエンツィアの最終フーガとしてK339のLaudate pueriが選ばれたことである。なぜならそれは、レクイエムにおけるKyrieフーガのテーマだけでなく、ペルゴレージのstabat Materの最終合唱もまた担っているからである。しかし、このフーガのインストルメンテーション(Agnus Deiと同様、Mass、K. 275より選ばれた)では、独立したヴィオラの部分はなく、Irmenはバセット・ホーンやバスーンも使用しなかった。結局、彼のスコアは、モーツァルト自身のインストルメンテーションの限界を超えている。なぜなら、彼のSANCTUSのパロディのために、Irmenはオリジナルなインストルメンテーションを採用して、レクイエムにはどこにもない2管のフルートと2管のホルンを追加したからである。彼は、ハ短調ミサ曲は、Incarnatusにおいて、やはりフルートを加えたが、モーツァルトの時代にフルートとオーボエは同じ奏者によって演奏されていた事実をを見逃していた。ハ短調ミサ曲において、Incarnatusは1パートのオーボエだけであったが、フルートパートは確かに、その他のオーボエ奏者によって演奏された。 。 Irmenは、バセットホルンやファゴットを持つレクイエムをステレオタイプの灰色の響きとしてそのくらい色を非難したが、ザルツブルグ教会でのモーツァルトの作曲が、しばしば木管楽器を完全に使い、彼のオーケストラ作曲のほとんどが弦楽器、バスパート、2管のオーボエ、2管のホルンのみしか使わないと考えれば、我々はこれを同様にステレオタイプとみなす事になろう。また、SusmayrもEyblerも、レクイエムの独特なシンプルさを否定するようなさらなる木管楽器を追加していない、ということを見逃してはならない。一方、インストルメンテーションは、私たちに伝えられているように、まだ多くのニュアンスを許している。基本的に、バセットホーンは単にそれ以外の典型的なオーボエを置き換える。ここでの唯一の問題は、最初のバセットホーンがソプラノとコラボレーションされている場合、ソプラノがバセットホーンの範囲の上限を超えたときに変化を必要とする、バセットホーンの限られた音域である。 p294 自費出版で登場したIrmenのスコアは、最終的に未完成とみなされなければならない。彼の一生の間にいくつかの公演があったにもかかわらず、多くの間違い、パフォーマンスの欠如兆候、数字付き低音はまったくなかった。そして、Irmenは、変更されていないSusmayrの補筆の欠点の多くを残した。この肯定はもはや利用できない。校訂者の 'Prisca Verlag'は、彼の突然の死の時にすでに清算されていた(2007年)。Irmenの未亡人が2009年に現在の作家に説明したように、彼の版のそれ以上の案は計画されていない。 手にし得るレクイエムのすべての補筆を見てみると、それぞれに対して根本的な苦情の数を増やすことができるという失望した結論に至るに過ぎない。 本当の悪魔は、 モーツァルト自身がスコアの大半をオーケストレーション化せずにしておいたために、(未完成部分への)作曲の付加のみならず、インストルメンテーションにもある。 だから、Susmayrに疑問を抱くだけでなく、その他のすべての校訂も取り上げている。 BeyerとRobbins Landonは、Susmayrの和声学的間違いのいくつかを修正したが、より多くの問題を先送りした。MaunderとDruceは後のオペラ(「魔笛」、「皇帝ティトスの慈悲」)をその器楽化のモデルとして参考としたが、教会音楽の”悲愴的様式”についての全体的に異なった要求をほとんど認識していなかった。Alan Tysonの研究を無視し、レクイエムは、モーツァルトがオペラの仕事を終えて、すなわち、プラハから帰国した後(1791年9月中旬)に始まったと結論づけている。 Druceの想像力豊かな補筆は、作品の様式的領域をはるかに超えている。彼が作曲した句は、歴史的な作曲技法についてや、レクイエムが作られた当時のstile anticoについての知識がほとんどない。そしてモーツァルトのスケッチ自体が示しているように、Amenフーガにおいて主要な役割を演じたであろう。Levinも同様のケースであり、モーツァルトの初期のザルツブルクスタイルを参照することでさらに悪いミスを犯し、インストルメンテーションに関しても、レクイエムが、ウィーンのモデルを明示的にたどったという事実は無視する。レヴィンは、様式的に完全に異なる、1783年の未完成のハ短調ミサをモデルとして(Sanctus; Amen fugue)使った。このようなモデルは、レクイエムに単純に移行していくことはできない。なぜなら、モーツァルトは、作品に固有のまったく新しいスタイルを開発していたからである。Irmenはモーツァルト自身の楽器を上回ってさえいた。彼の補筆、モーツァルトの作品をパロディとして使ったIrmenの方法(Laudate pueriのみは様式的に適当だとは思うが)は、モーツァルトが設定した作曲上の限界に関して、様式的に矛盾しているように見える。 Concerns of the New Edition 上記を考慮して、レクイエムを演奏する準備をしている人は誰でも、ジレンマの角に陥る。校訂のどれを使用するかを決めることができなくても、それらの要素を集めることはできる。実際、教会の音楽家の全世代は、そのようにすることによって、レクイエムの独自の「バージョン」を作成している。しかし、これには根本的な決定が非常に多くなり、既存の校訂版では解決されていないために、問題のいくつかは残る。このため、現在の著作者は、自分の版に着手しようとする。これは、次の前提の下で行われた。 1)Susmayr'の補筆は、モーツァルト自身の時代にあり、モーツァルト自身のスケッチに少なくとも部分的に基づいていることを前提とすることができる。それらは、レクイエムの後半の声楽部分やバスラインに関するすべての新しい版のためには不可欠な考慮事項である。しかしそれらは精査されなければならず、必要に応じて他の素材と交換、変更されなければならない。モーツァルトがスケッチを残していたにもかかわらず、Amen, Sanctus, Benedictus, Osanna、 Agnus Dei は、完全に新しい版を必要とした。必然的に、他の校訂との類似点は、SusmayrまたはEyblerのテキストが使用されている場所に現われ、そこでは修正が明白であるかまたは代替の可能性は非常に低かった。 2)EyblerはSusmayrよりもはるかに優れた経験豊かな作曲家だったので、SEQUENTIAでの彼の追加はSusmayrのものよりも好まれていた。Wolffが正しく指摘したように、必要な修正あるいは減少さえもが、様式的に疑わしい「より精緻に、独立したオーケストラの伴奏に対する傾向」を与えられた。 p295 インストルメンテーションは、作品の特性を尊重しなければならない。したがって、モーツァルトの現存時のインストルメンテーションが示すように、トロンボーンの独立した句は、慎重に考慮された例外を除いて、大規模には避けられ、わずかである。 tuttiの句では、木管楽器は合唱をサポートし、ファゴットは時にはバスラインを吹き、オーケストラ的響きに加えて、より大きなリズム的な輪郭に貢献する。上部の弦楽器の作曲的肌理は、バスパートとボーカルパートに対峙する。 3.)モーツァルトの自筆譜自体はほとんどそのような指示を提供していないので、この新版は、アーティキュレーション、テンポ設定、モーツァルトの通常の指示に沿った大胆かつ数字付きバス、写本中に見られる粗い指示を補充しなければならない。 このニュー・エディション(= NE)の主な目的は、Eyblerの校訂とより密接に対応するスタイルで作品を完成させることである。(木管楽器のより自由な書法、時に分割されるバイオリン、ヴィオラの自立性を含む)。Susmayrの技術的な欠点の大部分を取り除く努力は、たとえSusmayrの補筆を現在の校訂者のものと置き換えても、様式的に一貫性のあるものにすることを意図している。 このため、モーツァルトの初期の作品をパロディーの基礎とすることができたかどうかを調べることができるかどうかの問題を検討した(Amen, Sanctus, Benedictus, Osanna, Agnus Dei)。しかし、ハ短調ミサのCREDOとAGNUS DEIの完成に反して、現在の校訂者はこれがほとんど意味をなさないとの結論に達した。まず、レクイエムの様式は、モーツァルト自身の手によることが明らかであるように、肌理においてユニークであり、その単純さゆえに、納得のいくような作品を見つけて、そのスタイルと信頼できる適合を形成することが極端に困難であった。 Irmenが「エジプト王タモス」K. 345からの抜粋をSANCTUSとして使用するようにしたことは、レクイエムの様式的限界を完全に超えており、このジレンマを目の当たりにしている。 (Irmenの編曲は、「ミュンヘンのキリエ」K341を使った未完のハ短調ミサ曲の完成には向いていたことだろう)。一般に、確かなモデルはほとんど見つかっていない。 SANCTUSには適切なもの作品はなかった。校訂者は、しばらくの間、Irmenの指導に従い、レクイエムに適合するようにインストルメンテーションが拡大された Laudate pueriを基礎としたAmenフーガを供給するような試みを受けた。しかし、この作品は長すぎたようで、さらに悪いことに、拍子が間違っていた。スケッチが明らかにしているように、モーツァルトは明らかに、2/2拍子( Laudate pueriの拍子)ではなく、3/4拍子のフーガを意図していたのだ。 (彼はさらに、Pergolesiのオリジナルの拍子を変更した。Laudate pueri は、Amenスケッチの拍子を思い出させる。) Christoph Wolffは、作品の構造決定のためのこの決定の重要性を強調した。「正式な理由から、フーガとともにSEQUENTIAを終わらせることは、必然であった。作品の5つのすべてのセクションは、フーガを含み、シンメトリカルな流れで、(そのフーガ)は偶数―奇数―偶数―奇数―偶数という拍子で動く。Osannaのフーガは、(Susmayrの精緻化の欠点とは別に見られる)は、意図的にオリジナルな解決策の連続体に完全に適合し、Quam olim Abrahae fugueの主題の基本要素をさらに発展させる明確な輪郭を持つテーマに基づいて、全体の構造安定性の要求を満たす。一方、Osannaのフーガは、三拍子でのシンコペーションの始まりによるのではなく、その内部構造の強い対照性のために、その新規さと個性を強調する。それは、シンコペートされた始まりと最後には規則的な8分音符で終わるその非対称構造(3 + 3小節)である。しかし、より一般的には、モーツァルトのフーガの扱いでは、すなわち、作曲概念として、2つの主たる関心が明らかになっている。モーツァルトは伝統を守っているが、それを質的に新しいものに変えることでそのようにしている。ここでは、「古い音楽の聖なる尊厳と新しいものの豊かな飾り」を結びつける絆を語ったNissenが思い出される。したがって、レクイエム全体がこのような形式の枠組みに組み込まれていることは偶然ではない。Introitusと Kyrieの音楽は、出発点を示す。それは、反復、変化するテキスト、到達点でもある。 p296 これらすべての理由から、作品の構造上の配置を妨げずにパロディー以上のAmenフーガの新しい「補筆」をすることはできないように思えた。同様の理由から、いくつかの良い議論があるにもかかわらず、Cum sanctisのパロディのために選択されたモデルはなかった。 SusmayrのKYRIEのパロディーの不十分なテキストの配置、特に、テキスト"quia pius est"に適していない作品の終わり部分、またはレクイエムとして必然の悲しむ人に対する慰めのなさ、といった議論である。後者の問題は、ニ長調での終止において1小節長くし、より慰め的な半格終止によって解決された。実際には、Cum sanctisのパロディために利用可能な非常に良いモデルがあった。それはモテットMisericordias Domini K.222(1775)である。この作品はニ短調であり、後にレクイエムのテーマとして知られたテーマを含み、キリエのフーガを予言したセクションを持っている。(このモテットとレクイエムを同じプログラムとして演奏することは興味深いことだろう)。 Editorial Method and Layout NEは、「批判的な版」ではなく、実際のアレンジとしてはっきりと意図されている。 それゆえ、小さなタイプの点線のスラーまたは四角いブラケットを使って他の追加を区別する必要はないであろう。 結局のところ、モーツァルトの自筆譜はファクシミリで入手できる。誰でも興味のあることがあればどこでもそれを調べることができる。 同様の理由から、この版には包括的な解説のみが含まれており、原典の細部ごとの「批判的な報告」はない。 実際の音楽家は、このようなレポートを研究したり、詳細な言語学的問題を調査することはめったにない。 さらに、現在でさえ、学者は写本に見いだされる様々な手のつき具合の程度について同意しない。 ロビンズ・ランドンは、モーツァルト自身が書いたことのない「M」のセクションを収録している。 p297 Concerning the Trombones この自筆譜は、モーツァルトが独立したトロンボーンの使用に非常に注意を払っていることを示している。彼はもともと、アルト以下の声楽部分の補強として当てていた。12段の用紙を超えないほどに、楽器の種類が少なかったために、これは実用的な解決策であった。(ハ短調ミサ曲の場合では、2段スコアが必要であった)。モーツァルト自身の手では、トロンボーンの独立した糸口は、2つしか存在していない。レクイエムでの最初の出現は、作品の性質に促され、Tuba mirumの最初に、テノールトロンボーンソロとしてである。 一方、Susmayrはトロンボーンのために独立した書法をする誘惑に駆られた。彼は、トロンボーンパートを、可能な限り2つの譜表に分けて別々に表記した。しかし、Susmayrに基づいた他の校訂での過剰な独立したトロンボーン書法は―特にベネディクトゥスでは特徴的な―作品の様式とは異なっているように見える。オリジナルな写本は、「突然現われ出た自筆譜」であり、モーツァルト自身によるトロンボーンの指示はほとんどなく、Susmayrによって付け加えられた箇所は特に矛盾はない、という事実を見逃してはならない。したがって、トロンボーンをできるだけ計画的に扱い、正当な理由がある場合に限り、トロンボーンを独立して使用することが最善の方法であった。トロンボーンはまた、ボーカル・ソロやソフト・パッセージにも休止する必要がある。これらはNEの中で「senza Trb」と表示されている。 Nowakはレクイエムでのトロンボーンの書法と演奏を包括的に検討した。 (NMA、Vol。I / 1/2/2、pp。XVIIIff; Vol.I / 1/2/1、pp。XIIIffも参照) 特に、彼は次のように指摘した。「ボーカルパートの細かい音符は、トロンボーンパートにおいてはより長い音で表現されていた。しかし、これは音楽制作の慣習と演奏する地域によって異なる。」 Susmayrはこのような単純化を示すことはまれである。 (Nowak、p。XIX) しかし、NEではリズムを単純化していないので、演奏者の裁量に任せている。これはモーツァルトの時代の演奏に対応している。現在のトロンボーンのパート(トロンボーン奏者は単にボーカル・パートを演奏したわけではなかった)から見ると、すばやいパッセージにおいてトロンボーンは大体において、主旋律のみを演奏するだろうと指摘した Irmenに同意するであろうが。「今日の楽器演奏家の喜ばしい演奏は、モーツァルト自身が、レクイエム演奏で今日聞くことができるような芸術性を明示的に要求していない、という事実を見落とさないようにすべきである。」 一方、モーツァルトの時代コロラトゥーラのパッセージは、腕の良いトロンボーン奏者のためのチャレンジとみなされているかもしれない。そして彼は確かに反対しなかっただろう。もし彼らが書かれているようなすべての音符を演奏できるのであれば・・・ レクイエムのユニークさを強調するために、NEでは写本のように、テノールとアルトに相当する音部記号で持って、トロンボーンをヴォーカルパートとcolla parteであるように記譜する。 これらを読むことは、指揮者にとっては難しいとは限らない。 しかし、現代のトレブル音部記号は、ソプラノのためのもので、無論、ヴォーカルスコアは現代音部記号で書かれている。 |