■令和3年11月29日 やはりズレている毎日新聞
先日も、酒気帯び診察をした産婦人科医の報道を真っ先にしていた。(産科院長が飲酒し出産手術 乳児は一時生命危機 厚労省「あり得ない」) この"事件”は、その後いくつかの報道機関が追随はしたようだが、大きな社会問題にはならなかった。それは、記事の対象、その取り上げ方がいかにも大衆受けするような形であり、あまりに医学には無知・無謀な非常識なやり方だったからである。 毎日新聞は、これまでこのような形でたびたび、医療機関を叩いてきた。なぜかそれは毎日新聞に特異的な現象なのだ。 その特徴は、基本的には医療機関性悪説であり、医療において不幸な事象(”事故”ではない)が起きると、何でも患者側の味方ぶって、医者が悪い、患者が犠牲者だ、と言い張ること。不可抗力事象が、毎日新聞の手にかかると、過失・重過失事故になってしまう。 この記事にしても、以下のような毎日新聞独特の見解が語られている。 SARS-Cov-2ワクチンによる死者が1325人もいる→国はその99%が因果関係不明と結論づけている→だがそうした状況はおかしい。遺族が納得しないのは当然だ→だから、国はもっと積極的に因果関係を追及する義務がある→国はそれをしないで問題を放置している だが、こうした推論は非常に有害である。 まず第一に、1325人という数字。これはあくまでもファイザー社やモデルナ社に報告があった数字だけであり、両社が積極的に蒐集した数字ではない。おそらくは同じような状況で報告されていない例は多数ある。それは特に医療機関の義務でもなく、接種後日数なども厳密に決まっているものでもないから。 つまり、この数字自体、あまり意味がない。 次に、ワクチン接種後死亡の評価方法について。厳密に評価するためには、亡くなった人がワクチンを受けた場合と受けなかった場合との比較が必要である。受けていなくて生存していれば因果関係ありと評価できるが、当然それは不可能。 病理解剖などをすれば、確かに死因がはっきりするケースはあるだろう。しかし、それとワクチンとの因果関係はわからない。無論、ワクチン接種と何らかの病気あるいは症状との明確な関連性が明らかであれば、それは可能となるかもしれないが、今のところは、難しい。 たとえば、ワクチン接種後に少数ながら心筋炎が起こり得ることはほぼ明らかになっており、実際それで死亡した人はいるが、心筋炎になったことにワクチンが関係していたのかどうかの証明はできない。あくまでも"推定”しかできないのだ。 結局、遺族にしても毎日新聞にしても、不可能な追求をしようとしているのだ。毎日は遺族の味方を自称しているから、こうなる。 遺族からすれば、確かに、国に因果関係を証明してもらいたいとは思うだろう。30歳の若い息子さんを亡くした67歳の父親が、それを強く求めるのは当然のことだ。誰でもわが身に置き換えれば、そう思うだろう。 だがそれは、解決が不可能な要求なのだ。国とていじわるでγ回答をしているわけではない。それ以上調べようがないからこそ、わからない、としか回答せざるを得ないのだ。 医療には実は、こうした事象が無数ある。原因不詳の死亡。無論、病理解剖はするし、可能な限りの検索はする。それでも原因はわからない。 しかし遺族からすれば、それでは納得しない。「死んだからには何らかの原因があるはずだ、何らかの過失があるはずだ」と考える。毎日新聞は、そんな遺族に”寄り添う”。医療機関性悪説でもって。 本当はわかっているはずだ。医療機関は何かを隠している。よし裁判でそれを追求しよう、となる。 だが、多くの場合、医療裁判は医療者側の勝利で終わる。むろん、原告側に過失の立証責任があるためもあるが、実は裁判に俎上される事象の多くが、過失・重過失よりも不可抗力で起こった場合が多いからというのがその主たる理由である。損害賠償ははっきりとした病院側の過失・重過失がなければ認められないし、刑事裁判となればましてや、さらに強い重過失が求められる。そのような事象は実は、数少ない。 医療裁判の多くは、医療者側の説明不足で起こる。というか、遺族側が説明不足と感じた時に起こる。仮に、医療者側に過失があったとしても、経過をきちんとわかりやすく説明し、しかるべき謝罪をすれば、それなりの補償は必要となるかもしれないが、裁判まで行くことはまずない。 SARS-Cov-2ワクチンによる死亡は、仮にそれがあったとしても、医療者側の過失はほぼ考えにくい。あるとすれば、アナフィラキシーショックに対する処置に過失があった場合くらいだろう。そうした事例ならばあるいは、因果関係が証明できるかもしれないが、そうした報告は聞かない。 アナフィラキシーショック以外の死亡では、過失はほぼあり得ないのだから、法的責任追及は無意味であり、あくまでも医学的原因追求がメインとなり、しかしながらそれはまた、医学的にほぼ不可能なのである。 要するに、毎日新聞の追求は、あまりに患者に寄り添うつもりにおける無理筋と言える。だから他のメディアは毎日ほどにしつこくはない。 なお、NHKも以前の同じような視点でこの問題を取り上げていたことを、指摘しておく。 | |
■令和3年11月30日 恐ろしい、共産党の歴史観
これは、サヨクにやよく膾炙している、いわゆる"自虐史観”とも異なっている史観である。自虐史観の場合、戦前の日本のやったことはすべて悪であり、民は善であり、軍部を含む権力は悪である、という見方であるが、少なくとも戦前の日本の政党政治は否定していない。 つまり、戦前の日本にも憲法があり、政党が存在し、短期間(1924~32年)ではあれ二大政党制も存在し、首相は天皇からの大命降下であったとはいえ、国を動かす中心であった。天皇が政治に口をはさむことは、国家非常時(二・二六事件、張作霖爆破事件後)だけだった。張作霖爆死事件での天皇の発言は田中義一内閣崩壊を招き、昭和天皇はしたがって、その介入を悔いていたと言う。 いっかなサヨクによる自虐史観でも、以上の事実だけは、認めている。 要するに天皇は、明治創生期を除けば、国を統治していたなどといったことなどまったくなかった。否、明治創生期においても、天皇が主体と成って政治をおこなっていた事実はなく、むしろ薩長政権がその権威付けなどのために、天皇を政治利用していたに過ぎなかった。明治六年の政変などその好例で、大久保・岩倉は、国家のために、西郷や土佐派の追い出しのために、天皇を政治利用した。 天皇が国を統治していたなど、平安時代にまで遡らねばならないだろう。つまり共産党は、戦前の日本を平安時代の日本と同置している!のだ。 こんな歴史観ひとつとっても、いかに共産党が、特殊な政治組織であるかが理解できよう。立民の枝野前代表は、当然こうした共産党綱領は読んで共闘をしたのだろうが、であれば彼が「冷たい共闘」にとどめたのも当然だろうし、それでもこうした組織と共闘をしたところに、大いなる疑問を感じるのである。 | |
| ■令和3年11月30日-2 イエと自由恋愛
朝ドラ『カムカムエヴリバディ』では、紋切り型ではあるが、個人の恋愛とイエとの矛盾が描き出されている。家格が合わない若者同士の恋愛を成就させるのはやはり非常に困難を伴うものであり、究極の家格違いの恋愛をものの見事に成就させたどこかの国のお嬢様を思わず連想してしまった。
人には自由恋愛をしたいという根源的欲求がある。特定の人を好きになるというのは、ごく自然な人間の感情なのだろう。 こうした感情の昇華したものが結婚であると思いたいが、結婚という制度自体は、こうした感情とは裏腹に作られてきた。すなわち、権力の維持・継承という、ありていに言えば結婚とは”政略結婚”であり、”政略結婚”こそが、結婚制度の目的だった。 こうした結婚制度と恋愛制度のとの間の齟齬は、すでに16世紀のシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」でも取り上げられたように、古くから存在していた。いつの時代でも、高い家格に生まれた若者の自由恋愛には、どうしたも避けられない枷が嵌められてしまうものなのだろう。 私も若い頃には、こうした若者に同情もしたが、60歳を過ぎて、年頃の娘・息子を持つ年齢ともなると、「厳しい競争の時代、家を維持するためにはそれなりの家格の娘と結婚しなければならない。自由恋愛の結婚をするのなら、家を出ろ、その代わり経済的保障は何もない、恋愛を優先するなら生きてはいけないぞ」という、雉真稔の父親の一言には、父親の立場としては、確かにうなずかざるを得なかった。やはり、親の言うことを聞かずして、後に苦労をした人も何人かは見てきたし。 親の反対を押し切って自由恋愛を貫いても、必ずしも幸せになれるとは限らない。否、逆にそうした例では不幸になることの方が多いように思う。 確かに、あまりにも理不尽とも言える反対理由を唱える親もいる。たとえば「相手が長男でないとダメ」とか「他県の男はダメ」とか「片親ではダメ」とか「同居でないとダメ」とか「高卒の男ではダメ」とか{×1はダメ」とか・・・ こうした非常識な理由で反対する親も確かにいるにはいるが、私の経験上は、そうした親はやはり少数派だと思う。子の不幸を願う親はまず皆無なので、やはり親が反対する(少なくとも二の足を踏む)理由には、それなりに理由があることが多い。たとえば・・・ ×2以上の相手はダメ 奨学金以外の借金のある男はダメ 非正規雇用の男はダメ 客観的に見て明らかに家庭に問題がある 中卒の男 こうした理由での親からの反対・ないしは二の足を踏む状況は、ある程度はやむを得ないと思う。そして雉真稔のような高い家格に生まれた男はやはり、配偶者にはそれなりの家格が望まれるのも、やむを得ないだろう。 親の目はやはり確かなもので、↑のような理由で反対されて強引に結婚した人の多くはやはり、あまり幸せな結婚生活は送ってはいないように感じる。 無論、例外は多数あり。どうあっても不釣合いと思われる二人でも幸せな結婚生活を送ることもあるはある、眞子さんにはそのようになって欲しい・・・ | |
■令和3年11月30日-3 共産党切りはできないのだが・・・
もともとは国民民主の議員だから、当然、路線は変更せざるを得ないだろう。元来、立民はそうあるべきだったのだし・・・ しかし・・・ それがまた極めて困難である。それは、共産党を切らなければならないから。今の立民に共産党を切ることはできるのか? それは政治的にきわめて困難であると思う。 もともと立民の先祖の民主党は、もっとずっとリベラルな、むしろ保守的な政党だった。何せ2009年の政権交代前には、当時の小泉政権と同じような新自由主義が党の政策だったのだ。たとえば小泉政権前の民主党の政策は、「自己責任と自由意思を前提とした市場原理を貫徹することにより、経済構造改革を行う。これにより、3%程度の持続可能な経済成長をめざす」などとなっている。今で言えば、小泉構造改革とアベノミクスを合わせたような政策だ(両者はある意味、正反対だが)。 こうした民主党の新自由主義路線が小泉構造改革で奪われると、民主党は急激な路線転換、すなわち左旋回をおこなった。小沢一郎が代表となってからだ。 民主党の政策は、成長を無視し、分配オンリーという、サヨク的なものとなっていったが、小泉改革がかなり痛みを伴うものであったがゆえに、相対的な世論の支持を受け、2009年の政権交代へとつながっていった。 その政権はしかし、あえなく失敗し、その後はアベノミクスを掲げた自民党時代が続いたために、その後民進党→立民と名を変えたこの政党は、さらに左旋回をしていった。 すでに共産党との共闘選挙は国政のみでも2回目になり、都議選なども含めると、もはや立民と共産は不即不離の関係となり、まさに”立憲共産党"状態となっている。 こうした状況で、泉氏が代表になっても、立民から共産を引き剥がすのは無理だろう。つまりこの路線はもう動かせない。 泉氏としては、自らの思想・信条と立憲共産党とのはざまでさぞ苦労することだろう。またもや党が分裂し、新党が生まれる可能性は十分ある。泉氏はもともと国民民主なのだから、あるいは立民でも右の方の人は(野党共闘に反対だった人)は、国民民主に戻る、ないしは入るかもしれない。いよいよサヨクは、有権者のみならず、政党人からも見捨てられるだろう。 | |
■令和3年11月30日-4 曖昧模糊で戦わざるを得ない代表選
野党共闘派からは小川淳也が出馬するかと思ったが、結局はじいさんの方が出てきた。こちらがうっかり代表になっては困るためだろうか? 西村氏については当選回数は立派だが、辻元、レンホウに比べればはるかに知名度が低いし、目に見えないクォータ制を満たすためだけのあて馬出馬だろう。 自民党総裁選でも、野田聖子がそんな立場ではあったが、彼女の場合は知名度もあったし、これまでに何度も総裁選出馬を検討したこともあったので、それなりのインパクトがあった。 自民党の総裁選では、各候補の政策がはっきりし、かつ異なっていた。河野太郎は途中でかなり日和ったが、それでも最低保障年金や脱原発などの彼らしさは残してはいた。 自民党の強みは、内部で政策の決定的な違いがないことである。つまり、多様性はあるがバラバラではない、ということ。原発にしても、河野太郎でさえ、少なくとも既存の原発の再稼動までは認めている。 立民の場合、内部の路線対立は深刻である。共産党との共闘を続けるのか、共産党を切るのか、という路線対立は、埋めることは不可能である。 したがってもしも各候補者が生の主張をすれば、間違いなく党は分裂する。みんなそれを知っているから、あいまいなことしか言えない。だから代表選は面白くない。自民党総裁選のように、その主張で党員や議員が選ぶことができない。結局は、代表選と言いながら、これまでの各候補やその支援者の力関係で決まってしまう。 代表は泉氏がなるだろうが、前当ミニコラムで述べたように、共産党をきっちりと切ることができず、かといってガチでの共闘もできずといった、枝野路線よりもさらにあいまいなつかず離れずの状態で来年の参院選を戦わざるを得なくなるだろう。負けは必至。 | |
| ■令和3年11月30日-5 非常時にエッセンシャル度がわかる
朝ドラ「カムカムエブリバディ」は今、ちょうど大東亜戦争 に達している。日々、人々の暮らしはきびしくなり、また若者は次々と招集されている。戦前から始まる朝ドラは、どうしても必ず、あの時代にぶつかるので、そのたびに、胸が苦しくなる。 朝ドラを見ていて私が興味を持ったのは、召集を受ける順番である。 それはいろいろな基準はあるだろうが、戦争に行けば当然、ある確率で戦死者が出るわけで、はっきりいって、国家的見地から見て、死んでもらっては困る人間を温存し、死んでも差し支えない人間が優先的に戦地に送られることになる。つまり、若者限定ではあるにしても、人の命にはやはり軽重がある、という重い事実を思い知らされる。 人命は地球より重い、などと言われるが、あくまでもそんなことは平時の建て前であり、国家が非常時になると、そんなきれい事などはあっという間に引っ剥がされ、ホンネがむき出しになる。 朝ドラでは、主人公の安子の恋人である雉真稔のような、当時はエリートであった学生は、召集が免除されていた。つまり、将来国を率いる立場になるエリートは、国のために早々に死なれては困るので、温存されていたわけである。だが戦況が悪化するにつれ、学生もまた招集されるようになったが、理系学生はまだ招集が免除されていた。つまり文系学生よりも理系学生の方が、社会のエッセンシャル度が高かったのである。確かに、文学を知っている人間よりも、工学に通じている人間の方が、戦時ではことに必要とされたことだろう。 学歴以外でも、職業でもまた、戦争遂行や銃後の国家維持のための人間のエッセンシャル度が顕在化された。 より具体的には、あるサイトでは次のようにあった。 衛生兵を徴用したい・・・・・薬屋に勤めている 砲兵に徴用したい・・・・・・・乙種では砲弾が運べない バス運転手、機関士・・・・・国内の輸送が滞るのでほぼ徴兵しない 警官や役場に勤める者・・・原則徴兵は後回し 工場の熟練工・・・・・・・・・後回しにする 即刻徴兵される者・・・・・・赤・犯罪者など国体を乱す者 八木アンテナ勤務・・・・・・・内地の司令部など 猟師・・・・・・・・・・・・・・・・海軍 結核を煩っている・・・・・・・徴兵見合わせ Yahoo!知恵袋より 興味深いのは、犯罪者は即刻徴兵されたとのことで、おそらくたとえばどんな国家でも囚人は国のお荷物であり、平時は仕方なく(死刑囚以外は)生かせているが、戦時になれば、真っ先に一石二鳥とばかり、国家の厄介者の始末を兼ねて戦争の遂行のために使ったのだろう。共産主義者も、当時は非合法であったから犯罪者と同じ扱いであり、同様の処置を受けてもやむを得なかったと言える。病人は、戦地に連れて行っても役に立たないから、国家のエッセンシャル度は失礼ながら低いが、召集は当然のことながら、まぬかれていた。 また次男、三男等はやはり、将来家を継ぐべき長男よりも優先して召集されていたことだろう。彼らのエッセンシャル度は長男よりもはるかに低かったのである。長子単独相続が確立した江戸期以降、地方で食い詰めた農家の次男、三男等が江戸に流れてきて、結婚もろくにできないまま、寿命も短く死んでいったが、戦時には召集という形で、そのエッセンシャル度の違いが顕在化したのである。 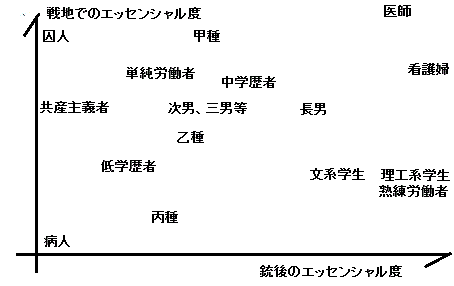 ●Covid-19禍が顕在化した現在の職業のエッセンシャル度 さて、戦時のように命を取られるような恐ろしいことはないとはいえ、昨年来のCovid-19禍の社会においてもまた、職業によるエッセンシャル度がはっきりと示されることとなった。 Covid-19が病気である以上、圧倒的エッセンシャル度が高いのは医療職であるのは当然であるが、その中でもかなり濃淡がある。 トップは圧倒的に看護師であり、医師はその次となる。重症患者の管理、中等症患者の重症化評価等において、看護師の持つスキルほど、社会から必要とされたものはなかった。看護師は、適切な医師からの指示のもとで、あるいはある程度は自己判断で柔軟に働くことができる。さらには患者数が急激に増えたために、大量の人手を要する。 逆に医師の場合、医療の統率者なので、実は数はそれほどは要らないということがバレてしまった。これまで医師不足がいろいろと言われてきたが、実はそれはうそであり、医療界は実は、少数の優秀な統率者と多数の均質な働き手がいる世界が理想なのである。たとえば医者は3人いても1人優秀であればそれで十分で、あとの2人はどーでもよいが、看護師は10人居れば全員が均質なスキルを持っている必要がある。(なお、戦場では外科治療に多くの医師が取られるので、上図のように、戦地でのエッセンシャル度は看護師よりも高い)。 その他にもいろいろな医療職があるが、Covid-19禍でのエッセンシャル度がある程度落ちることは否めない。ただ、Covid-19の治療を含めて一定の医療水準を保つためには、各専門職が欠かせないことは、言うまでもない。 その他の職業はいちいち書かないが、三密忌避の結果も相俟って、芸術や飲食、観光といった職業がエッセンシャル度が低いことは明らかとなった。確かに音楽会に行かなくても生きてはいけるし、宴会がなくても、外食をしなくても家で飲み食いしていればいい。結婚式だって、しなければしないでもかまわない。もともとは親のためにやっていたようなものだし。 このように、社会が非常時になると、それまで隠されていたさまざまなエッセンシャル度の相違が顕在化するのである。 ●それでも命は平等であり、職業に貴賎はない このように、人の命や職業にはやはりエッセンシャル度の違いがあることは、認めざるを得ない事実ではあるが、それでも私はやはり、人の命は平等であり、職業は、少なくともそれで食べている人がいる限りはすべて必要なものだ、と思う。 先ほど囚人はもっとも社会のエッセンシャル度が低いと書いたが、彼らとて、少なくとも彼らの親兄弟だけからすれば、決してそうとは言えないだろう。エッセンッシャる度の低さはあくまでも、国家的見地からのものである。 職業にしても、少しでも政府が行動緩和を許容すれば、すぐにわーわー騒ぐ人たちも出てくる。良き芸術はやはり、人が人らしく生きていくためには必須のアイテムである。 だからできれば、こうしたエッセンシャル度などがわからないような、平和な時代が続くことを祈りたい。むろん、戦争と違って、病気のパンでミックは人智ではコントロールはしがたいが。 | |
■令和3年11月30日-6 メルケルはやはりしたたかで、ドイツはやはりバカだった
教条主義者ならこれを、メルケルの変質、と非難するだろう。脱石炭をしたのになぜそれを輸出するのか、と。そう、どこかの国のバカサヨクのように。(たとえば、朝日新聞は、令和2年7月12日社説(令和2年7月16日当ミニコラム)で、石炭輸出をやめろ、と主張している)。緑の党にこれを言わせない政治力はさすがだと思う。 メルケルは、緑の党などとは異なり、すべてを理解して脱原発、脱石炭を進めてきたのだろう。もともと脱原発にしても、1000万kW以上の火力発電設備の増強を訴えたし。 そもそも褐炭が豊富で、2011年当時は石炭・褐炭が発電量の4割を占めていたドイツでの脱石炭宣言自体が、無謀だった。 メルケルは、強力なジェットエンジンで強い自己主張を推し進めるというよりは、グライダーのように風を読んで政治を進めるタイプだから、緑の党や環境団体に圧されつつのやむを得ない選択だったのではあろうが、石炭発電量も2011年以降は急激に減少し、現在では23%にまで低下させている。将来派生するであろう問題はさておいても、脱原発も脱石炭も、それ自体は達成はできそうである。目標の達成可能性を探るバランスにすぐれているのだろう。 ●将来的には問題続出? ドイツのような無理筋なエネルギー政策がとにもかくにもここまできたのはやはり、メルケルの政治力の賜物だろう。しかし、将来的には必ず禍根を残すと思う。 もともと火力発電増強を唱えながら脱石炭を言った以上、火力発電燃料としては、天然ガスに頼らざるを得ない。その天然ガスはしかし、ロシア頼みであり、ノルドストリーム2に頼らざるを得なかった。それはまた、ドイツのエネルギーの生殺与奪の権を、にっくきプーチンロシアに握られることを意味する。 メルケルはこれを、「今は過渡期だから。将来はVREの”V”が取れるから大丈夫」で押し切った。だから記事でも、"過渡期”、”橋渡し”といった文言が並んでいる。(原語では何と言うのかしらん?)。 したがって、メルケルの過渡期論が間違いであることがおそらくは近い将来に証明された時、ドイツはパニックに陥ると思われる。つまり、これまでのFITの負担が国民に重くのしかかっている(ドイツの家庭電気料金はダントツで世界一高い)割には、VREはいつまでも経済的に自立せず、寒波が来たり、昨今のように欧州全体の風力発電量が長期にわたって減るなどといった事態が常態化すれば、実は世界のエネルギー政策は、VREの脱”V”化という青い鳥を追い求めていただけだったということが、世界中で認識されるのではないか? その時生き残るのはやはり、化石燃料を残していた国(あるいは原発大国)である。アラブ諸国は再生エネを推進しつつ、化石燃料は温存している。ノルウェーは自国の発電を限界費用ゼロの水力発電に依存しつつ、化石燃料を輸出して外貨を稼いでいる。 ドイツの場合は、悪いことに、隣に原発大国のフランスがあるために、これを巧妙に利用すれば、政策の失敗を糊塗することができるので始末に悪い。失敗していても成功だ、と言い張ることも可能なのである。 わが日本は、それができない。ごまかせない。欧州からの圧力に押されて仮に、立民が公約するように石炭発電を捨てたら、原発を捨てたら、乱高下する天然ガスにのみに頼らなければならない。いくらVREを増やしても、”V”が抜けない以上、相応の火発設備を、それも稼働率が低いものを多く作らなければならない。電気料金はうなぎのぼりになり、日本はにっちもさっちも行かなくなる。”V”を取ってくれる青い鳥はいないのだから。 |