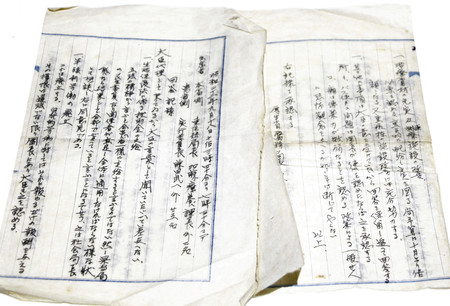日本人の身長が縮んでいる!
調査によると、男女ともに1978~1979年生まれ以降、日本人の平均身長が低くなっている。100年前から約15cmも伸びてきた日本人の身長だが、国立成育医療研究センターの資料によると、日本人の平均身長は1978~1979年の男性171.5㎝、女性158.5㎝をピークに、以降20年間低下し続けているという。栄養状態が悪くなったわけではないのに、これはいったいどういうことだろう。
日本人は身長を高くする遺伝子が自然淘汰されている!?
2019年9月、英国のオンライン科学雑誌『Nature Communications』に理化学研究所等の研究チームによる、ある研究結果が掲載された。それは、身長が高くなるのは遺伝的変異のひとつで、日本人は身長が高くなると何らかの不利な影響があり欧米人より身長が低いらしい、というものだ。その「不利な影響」とは? 東京大学大学院でゲノム解析分野の教授を務めている鎌谷洋一郎氏に聞いた。
「日本人約19万人の遺伝子を調べたところ、とても弱い効果ではありますが身長を高くする遺伝的変異が自然淘汰されている可能性があることがわかりました。これは欧州系集団で検証された結果とは真逆です」(鎌谷洋一郎氏 以下同)
我々は、さまざまな遺伝情報を持って生まれてくる。その長さは30億塩基対で、99.5%以上の部分では人の間では互いに同じだが、残り0.5%は異なる。その0.5%のうち、身長に関わる場所は573箇所(最終的には数千になる可能性も)。その中には身長を高くする遺伝子があるが、日本人はこの遺伝子が自然淘汰されている。つまり、身長が低いほうが生存に有利だと考えられるという。
「身長や体重などのように、遺伝的要因と環境的要因によって個人の違いが生じる特徴は“多因子形質”と呼びます。身長は多因子形質の中でも、遺伝的な影響が強く、8割は遺伝因子の影響だと報告されています。残りの2割が栄養状態や健康状態などの環境要素。日本人がもつ遺伝子プール(遺伝子情報の多様性)が戦後に大きく変化したとは考えづらいので、身長が100年前から15㎝伸びたのは、後者の環境要素によるものでしょう」