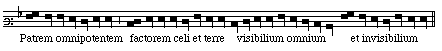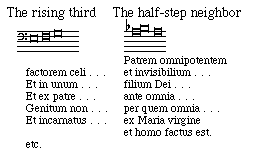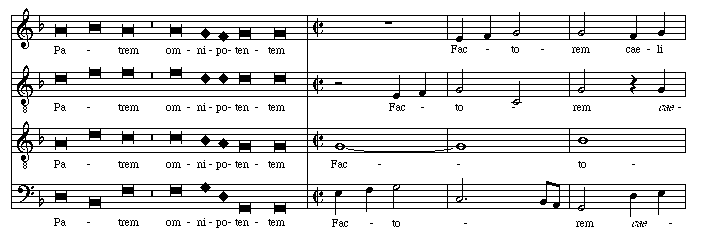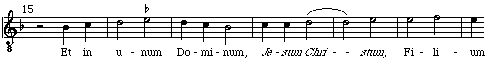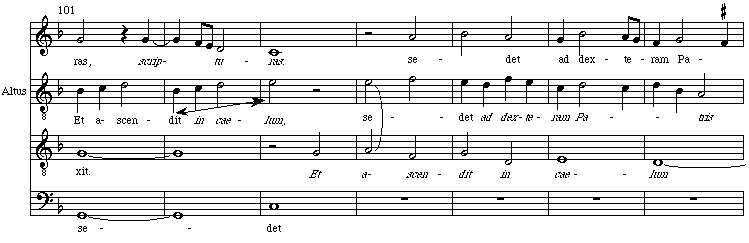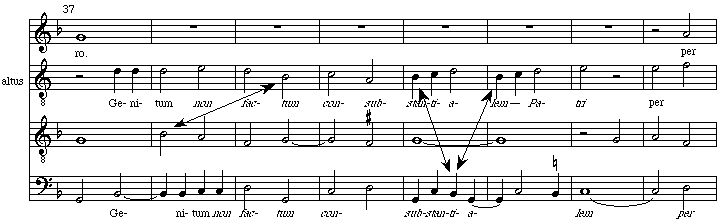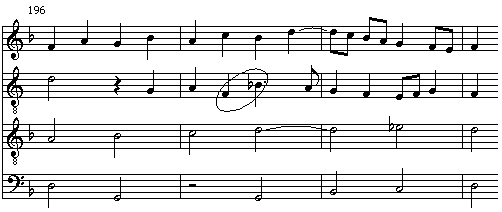|
丂
丂偙偺儁乕僕偼Comments on
Josquin's Patrem De tous biens plaine偺東栿偱偡丅僕儑僗僇儞偺Patrem De
tous biens plaine傪椺偵偲傝丄偦偺拞偱偟偽偟偽巊梡偝傟偰偄傞摿掕偺儌僠乕僼偑Musica
Ficta偵傛偭偰偳偺傛偆偵曄宍偝偣傜傟偰偄傞偐丄墘憈偵偍偄偰偦傟偼偳偆夝庍偡傟偽傛偄偐丄側偳偑榑偠傜傟偰偍傝丄戝曄偵嫽枴怺偄榑暥偱偡丅拞悽偐傜儖僱僒儞僗偵偐偗偰偺妝晥偵偼杮椺偱庢傝忋偘傜傟偰偄傞傛偆偵丄僷乕僩偵傛偭偰椪帪婰崋偑偁偭偨傝側偐偭偨傝丄偁傞偄偼偦偺悢偑堎側偭偰偄偨傝丄偲嬤戙榓惡妛偱偼峫偊傜傟側偄傛偆側傕偺偑偁傝傑偡丅暯嬒棪傗僴挿挷偩偺僿挿挷偩偺偲偄偭偨挷惈偺妋棫偟偰偄側偐偭偨摉帪丄椪帪婰崋偺埖偄偑埫拞柾嶕偺忬懺偩偭偨偙偲偑傛偔傢偐傝傑偡丅
|
丂
俥倝倗侽丂僌儗僑儕僆惞壧Credo嘥偺嵟弶偺晹暘乮Cf. Liber Usualis p俇係乯
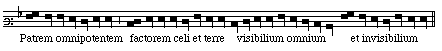
丂僕儑僗僇儞偺儈僒嬋偱偼丄偦偺拞偺俠倰倕倓倧偱偼僌儗僑儕僆惞壧Credo嘥乮栿拲丟Liber Usualis 倫俇係乯偐傜偺堷梡偑懡偄丅僕儑僗僇儞偼偙偺Credo嘥偺拞偵偟偽偟偽弌尰偡傞擇偮偺摿挜揑側儌僠乕僼乮堦偮偼mi-fa-sol偺忋徃壒宆丄傕偆堦偮偼mi-fa-mi偲偄偆敿壒僗僥僢僾壒宆丅偨偩偟壓晥俥倝倗侾偱偼儔乕僔侒-儔乯傪堄幆揑偵巊梡偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅偙偆偟偨儌僠乕僼傪巊梡偟偰偄側偄晹暘偼偁傑傝側偔丄惞壧偐傜偺堷梡偑彮側偔側傞晹暘偵偦傟偼廤拞偟偰偄傞丅
俥倝倗侾
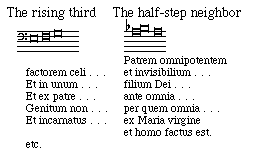
丂偙偺僾儗僀儞僠儍儞僩傪慡嬋偵傢偨偭偰巊梡偟偰偄傞嶌昳偺堦偮偵僕儑僗僇儞偺 Patrem De tous biens
plaine偑偁傞丅偙偺嶌昳偼儁僩儖僢僠乮栿拲丟悽奅偱堦斣嵟弶偵妝晥報嶞傪巒傔偨恖乯偺報嶞晥Fragmenta Missarum (RISM
1505[1]偵廂傔傜傟偰偍傝丄傑偨Capplla Sistina41幨杮乮CS41)偵傕偁傞丅傑偨Albert
Smijers偵傛偭偰1956擭偵曇嶽偝傟偨嶌昳廤偵傕偙偺扨撈偺Credo偑娷傑傟偰偄傞丅
丂偙偺嶌昳偱偼Credo嘥傪奺僷乕僩偑掕慁棩偲偟偰棙梡偟偰偄傞偑丄捠忢偺応崌偼傗偼傝僥僲乕儖偵偍偗傞巊梡偑堦斒揑偱偁傞丅De
tous biens
plaine偼僊僛働儉偺僔儍儞僜儞偐傜偺僷儘僨傿偱偁傞偑丄偙偺僕儑僗僇儞偺嬋偵偍偄偰Credo俬偺掕慁棩偼superius偲altus乮忋擇惡晹乯偵擣傔傜傟傞丅
丂儁僩儖僢僠偺報嶞晥偵偍偄偰偼丄偙偺嶌昳偼Credo俬偺嵟弶偺晹暘乮乯偑superius偵尰傟丄偦傟偼崟怓偱婰晥偝傟偨僽儘僢僋僐乕僪偺僴乕儌僯乕傪敽側偭偰偄傞丅偙傟偼CS41偺幨杮偵偼尒摉偨傜偢丄摿庩側傕偺偱偁傞丅乮壓晥俥倝倗俀乯
俥倝倗俀
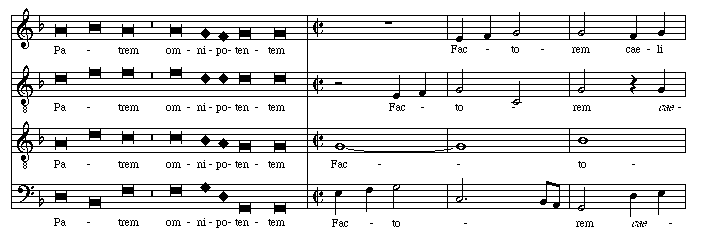
丂億儕僼僅僯乕偼幚嵺偵偼Factorem
caeli偐傜巒傑傞丅superius偑戞侾俆彫愡傑偱掕慁棩傪壧偄丄偦偺偁偲偼altus偑偙傟傪係搙壓偵堏挷偟偰堷偒宲偄偱偄偔丅
丂偙偺堏挷偺夁掱偵偍偄偰丄Credo俬偺mi-fa-so偲忋徃偡傞儌僠乕僼偼Smijer偺斉偵偍偄偰偼俛僫僠儏儔儖亅俠亅俢偱偼側偔丄俛侒亅俠亅俢偲忋徃偟偰偄傞丅偙傟偼儌僠乕僼偺廳梫側曄峏偱偁傞丅乮壓晥俥倝倗俁嶲徠乯
丂偝傜偵丄altus偺慁棩慄偑俛侒偐傜巒傑偭偰係搙忋傑偱忋徃偡傞偲偒偼丄堦斣忋偺俤偼俤僫僠儏儔儖偱偼側偔丄俤侒偱壧傢傟傞偺偑晛捠偱偁偭偨丅偙傟偼偙偺慁棩偺棳傟偱惗偢傞嶰慡壒傪旔偗傞偨傔偺張抲偱偁偭偨丅偦偺偨傔偵Smijers偼偙偆偟偨俤偺晹暘偵偼棑奜偵侒婰崋傪偮偗偰偄傞丅乮栿拲丟偡側傢偪musica
ficta偱偁傞乯
俥倝倗俁
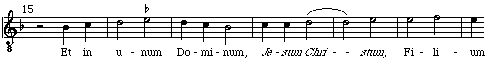
Werken, Fragmenta Missarum p.
98).
丂偟偐偟側偑傜丄偙偆偟偨俤偺張抲偼mi-fa-mi偺儌僠乕僼偑偦偽偵偁傞帪偵偼E僫僠儏儔儖偲偟偰張棟偝傟傞偺偑晛捠偱偁偭偨丅偝傜偵傑偨Smijers偼偙偺mi-fa-mi偺儌僠乕僼偺榓惡揑峔憿傪廳帇偟丄榓惡偺曄壔偺棳傟偺拞偱偙偺儌僠乕僼偑偨偲偊偽mi侒-fa-mi侒偺傛偆偵慡壒曄壔偡傞傛偆偵側傜偞傞傪摼側偔側偭偨偲偟偰傕暿偵偲偑傔傞偙偲傕側偐偭偨丅偙偆偟偨応崌丄bass傗tenor偺俙壒偑偦偺僇僊傪埇偭偰偄偨丅乮栿拲丟壓晥戞侾侽俀乣俁彫愡偵偍偄偰altus偼嶰慡壒傪宍惉偟偰偄傞丅戞104彫愡偱偼tenor偑俙偲側偭偰偍傝丄偙傟偲姰慡屲搙傪宍惉偡傞偨傔偵altus偼俙僫僠儏儔儖偲側傝丄寢壥揑偵屻偺壒偲偲傕偵mi-fa-mi偺僥乕儅傪宍惉偡傞乯
俥倝倗係
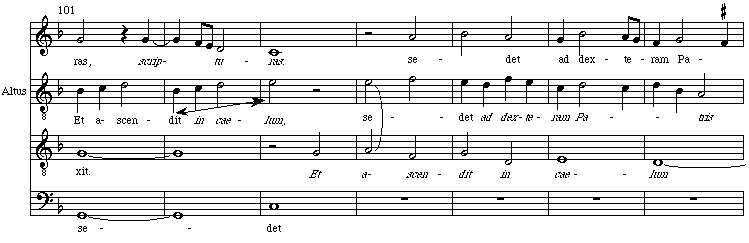
丂俢丏俵倳値倰倧倵偵傛偭偰侾俋俈俇擭偵峴傢傟偨儗僐乕僨傿儞僌偱偼偦偺椪帪婰崋偺桳柍偺慖戰偼傎傏慡柺揑偵Smijers偺偦傟偵廬偭偰偄偨丅偦傟偼斵偺椪帪婰崋偑棟偵偐側偆傕偺偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅Smijers偼偦偺慖戰偺婎弨傪戞侾侽係彫愡乮俥倝倗係嶲徠乯偍偗傞傛偆偵姰慡屲搙傪堐帩偱偒傞傛偆側宍偵偍偄偨丅偙傟偵傛傝Altus偵偁傜傢傟傞俤亅俥偺敿壒恑峴偺僷僞乕儞傕堐帩偝傟傞偺偱偁偭偨丅偟偐偟偦偺寢壥丄乮戞侾侽俀乣俁彫愡偺Altus偺傛偆偵乯嶰慡壒偺恑峴偑惗傑傟偰偟傑偆丅偮傑傝偙偆偟偨忬懺偺傑傑偱偼傕偲傕偲偺mi-fa-sol偺忋徃儌僠乕僼偺堐帩偺栤戣揰傪夝寛偱偒偢丄壗傜偐偺僽儗乕僋僗儖乕偑昁梫偲側偭偰偔傞丅
丂偦偺僽儗乕僋僗儖乕偼埲壓偺傛偆側傕偺偱偁傞丅傕偲傕偲偺俛僫僠儏儔儖亅俠亅俢偲偄偆忋徃儌僠乕僼偺尨揰偵婣傞偙偲偵傛傝丄嶰慡壒傪夞旔偡傞曽朄偱偁傞丅幚偼偙偺傛偆偵偟偰傕懳埵朄偦偺傕偺偵塭嬁偼側偄偟丄傑偨曇廤幰偵傛偭偰俤壒傊晅壛偝傟偨侒婰崋傕戝暆偵尭傜偡偙偲偑偱偒傞丅偝傜偵嶰慡壒側偟偱傕偲傕偲偺儌僠乕僼偺宍懺傪傕堐帩偱偒傞偺偱偁傞丅偱偼嬶懱揑偵偼偳偆偡傞偐丅
丂幚偼儁僩儖僢僠偵傛傞侾俆侽俆擭偺斉偱偼altus僷乕僩偺晥昞忋偺僼儔僢僩婰崋偑寚擛偟偰偄傞丅乮壓晥俥倝倗俆嶲徠乯丂Smijers偼偙偺寚擛傪柍帇偟丄偙傟偼扨側傞晥柺嶌惉忋偺儈僗偱偁傞偲偟偨偑丄偟偐偟偦偆扨弮偵偼峫偊傜傟側偄丅側偤側傜儁僩儖僢僠偵傛傞晥柺偱偼偡傋偰偺altus僷乕僩偵偍偄偰偙偺侒婰崋偑寚擛偟偰偄傞偟丄傑偨懠偺僷乕僩偵偍偄偰偼偙偆偟偨寚擛偑傑偭偨偔擣傔傜傟側偄偐傜偱偁傞丅
丂偝傜偵傑偨儁僩儖僢僠偺斉偵偼堦売強偩偗柧敀偵altus偺俛壒偵侒婰崋偑彂偐傟偰偄傞晹暘偑偁傞丅乮壓晥俥倝倗俇偺戞侾俋俈彫愡偺晹暘乯丂偙傟偼柧傜偐偵偙偺altus偵偍偄偰偼丄俛壒偑傕偲傕偲偺婰崋偲偟偰偼僫僠儏儔儖偱撉晥偝傟偰偄偨偲偄偆偙偲傪帵偟偰偄傞丅乮偪側傒偵Smijers偺斉偱偼偙偺晹暘偺侒偵偮偄偰偼壗傕尵媦偟偰偄側偄乯
丂慜弎偺傛偆偵丄altus僷乕僩偺晥昞忋偺侒婰崋偺寚擛偼偙偺嶌昳偡傋偰偵傢偨偭偰擣傔傜傟傞丅掕慁棩偐傜堷梡偝傟偨altus僷乕僩偱俛僫僠儏儔儖傪偲傞晹暘偵偍偄偰偼丄摨帪偵壧偆懠僷乕僩偺晹暘偱偼傎偲傫偳偺応崌俛壒偼俛侒偲側偭偰偄傞丅乮壓晥俥倝倗俆嶲徠乯偙傟偵傛傝丄嶌昳慡懱偑侒偲僫僠儏儔儖偺偣傔偓崌偄偵傛傞僺儕恏偺嵤傝偑偆傑傟傞丅偦偺傑偝偵僴僀儔僀僩偑壓晥偺晹暘偱偁傞丅乮栿拲丟偙偆偟偨偣傔偓崌偄偼摿偵拞悽偺嬋偱偼偟偽偟偽尒傜傟傞丄偦傟傎偳捒偟偄偙偲偱偼側偄乯
俥倝倗俆
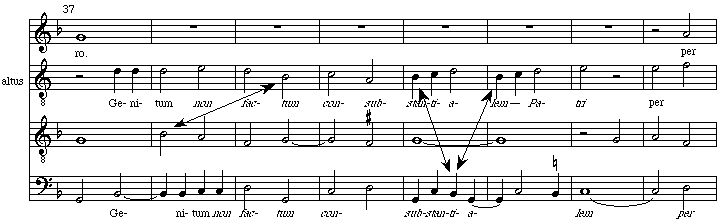
丂丂丂栿拲丟altus偺晥昞偵侒偑偮偄偰偄側偄偙偲偵拲栚丅偦偺偨傔偵altus偲tenor偵偍偄偰俛僫僠儏儔儖偲俛僼儔僢僩偑偣傔偓偁偭偰偄傞丅
丂altus偑掕慁棩堷梡晹暘傪廔椆偟傛偆偲偡傞偲偙傠偵偔傞偲乮偦傟偼偨偄偰偄堦偮偺僼儗乕僘偑廔椆偡傞偲偙傠偱偁傞乯俛壒偼昁偢俛侒偲側傞偙偲偵拲栚偟偨偄丅偦偟偰偦傟偵傛傝偦偺晹暘偼戝掞偼廮傜偐偄僿僋僒僐乕僪乮栿拲丟偙傟偵娭偟偰偼懳幬偵偍偗傞栤戣揰偺儁乕僕偺嵟壓抂偺昞傪嶲徠偺偙偲乯傪宍惉偡傞傛偆偵側傞偺偱偁傞丅
丂壓晥俥倝倗俇偺戞侾俋俈彫愡偵偍偗傞柧敀側俛侒偺晹暘偑偼偙偆偟偨僷僢僙乕僕偺堦偮偱偁傞丅幚嵺丄傕偟傕偙偙偵侒婰崋偑偮偄偰偄側偐偭偨偲偟偰傕丄媈偄側偔偙偺晹暘偺俛壒偼乭fa乭乮栿拲丟僜儖儈僛乕僔儑儞偱偼俛侒乯偲偟偰姰慡巐搙偺挼桇偲偟偰乮栿拲丟偙傟偼傑偝偵廮傜偐偄僿僋僒僐乕僪偺棳傟偱偁傞乯壧傢傟偨偙偲偱偁傠偆丅
俥倝倗俇
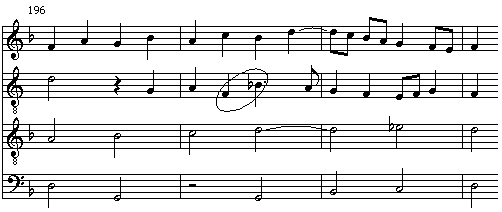
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仾偱altus偲tenor偑俤僫僠儏儔儖偲E侒偱傇偮偐傞
丂偄偔偮偐偺彮悢偺僷僢僙乕僕偵偍偄偰偼偟偐偟挷惈婰崋偺憡堘偵傛傞栤戣傕婲偙偭偰偄傞丅偨偲偊偽fa偲mi乮栿拲丟僜儖儈僛乕僔儑儞偱偼梫偡傞偵敿壒僗僥僢僾傪帵偡乯偺嬼慠偺廳側傝偵傛傞僋儔僢僔儏偺傛偆偵丅偟偐偟側偑傜丄偙偆偟偨僋儔僢僔儏偺戝晹暘偼抁偄傕偺偱偁傝丄栤戣偵偼側傜側偄丅偨偲偊偽忋晥俥倝倗俇偺戞侾俋俉彫愡偵偍偗傞tenor偺俤侒偲altus偺俤僫僠儏儔儖偲偺娫偺僋儔僢僔儏側偳偼曇廤忋偺寚娮偲偟偰傛傝偼懳埵朄偵偍偗傞僺儕恏僗僞僀儖偺堦庬偲偟偰擣傔傜傟傞傋偒偱偁傠偆丅
丂乮晥偱偼帵偝傟偰偄側偄偑乯戞俈俇彫愡偵偍偗傞戝婯柾側僋儔僢僔儏偼傗傗夝庍偑傓偢偐偟偄丅偙偙偱偼altus偼掕慁棩傛傝堷梡偝傟偨晹暘偲側偭偰偄傞偑丄偙偺僋儔僢僔儏傪掶惓偡傞偙偲偼altus傗bass偺慁棩慄偺帺慠側棳傟傊偺戝偒側挧愴偲側偭偰偟傑偆偩傠偆丅偙偙偼偙偺嶌昳偵偍偗傞桞堦偺戝婯柾側僋儔僢僔儏偱偁傞丅
丂偙偺嶌昳偵偍偗傞挷惈婰崋偺晅偒曽偺媈栤偵懳偟偰偡傋偰摎偊傞偙偲偼崲擄偱偁傞偑丄偟偐偟altus偵偍偄偰侒婰崋偑晥昞偵偮偄偰偄側偄偙偲偵傛傝丄怴偨側僴乕儌僯乕姶妎傗慁棩偺棳傟偺儘僕僢僋偑惗傑傟傞偙偲偼妋偐偱偁傞丅
丂俠倰倕倓倧嘥偺僾儗僀儞僜儞僌偺棙梡偵偍偄偰偼偦傟偑掕慁棩偦偺傑傑偺棙梡偱偁傠偆偲偙偺嶌昳偺傛偆側偁偪偙偪偐傜偺敳偒彂偒偵傛傞堷梡偱偁傠偆偲丄偲偵偐偔偦傟偧傟偑帺恎偺慁朄揑悽奅傪昞尰偟偰偄傞偺偱偁傞丅俛僫僠儏儔儖偲俛侒偲傪嫟惗偝偣偨偙偺嶌昳偼丄堎側傞慁朄偵偍偗傞慁棩傪尒帠偵寢崌偝偣偨僕儑僗僇儞偺擻椡傪崅偔昡壙偟偨僌儔儗傾僰僗偵傛偭偰壓婰偺傛偆偵徿巀偝傟偰偄傞丅
偙偺嶌嬋壠乮僕儑僗僇儞乯偵偲偭偰偼丄堎側偭偨慁朄偺慁棩傪寢崌偝偣偰嬋傪嶌偭偰偄偔偙偲偼傑偭偨偔梕堈側偺偱偁傞丅偦偟偰斵偼偦傟傪偄偲傕偨傗偡偔桪夒偵偍偙側偭偰偟傑偆丅斵偼偦偺慁朄偑壗偱偁傠偆偲丄僯働傾怣宱偵偍偄偰僄僆儕傾慁朄傪娷傑側偄儈僒嬋傪嶌傞偙偲偼傎偲傫偳側偔丄丄傑偨偦偺懠偺傗傝曽偱偁偭偰傕昁偢傗惉岟傪廂傔傞偱偁傠偆丅(Dodecachordon,
ed. and trans. by Clement Miller, MSD 6 (Rome 1965), p. 266):
偙偙偱忋婰偺嬋偺戞侾俆乣俆侽彫愡偺晥傪尒偰傒傑偟傚偆丄偦偟偰擇庬椶偺墘憈偱壒偺堘偄傪妋偐傔偰偔偩偝偄丅http://www.unh.edu/music/alamire/jDTB-playExample.htm
乮栿拲丟忋婰偱堷梡偝傟偨俢丏儅儞儘乕偺墘憈偲僇儁儔丒傾儖儈乕儗偺墘憈偲偑幚墘偱挳偗傑偡丅摨偠晥柺偱傕椪帪婰崋偺偮偗曽偺夝庍偺堘偄偱偙傫側偵傕暤埻婥偑曄傢傞傕偺偐偲嬃偐偝傟傑偡乯
|