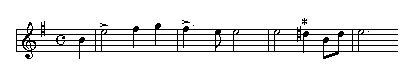
<全体的結語>
音楽エッセイの頁へ戻る
声楽曲における特有な半音変化について
導音の二重化について
今回の研究において用いられた一連の異なったアプローチは結局は一つのポイントに結論付けることができる。すなわち13世紀後半にその起源を持つ近接した導音の原則は14,5世紀に次第に整備されていったが、16世紀後半にはさまざまな試みがなされ、結局その頃(16世紀後半)になると音楽家たちは旋法理論に格別の関心を持ち始めた、ということである。
近接した導音の原則の一時の傾向はGaffuriusや後のDanckerts,Coclico、あるいは多くのドイツ理論家たちの沈黙、器楽タブラチュア、とりわけオケゲムにはじまるフランドル楽派の作品の二重導音といった理論的研究の中に本質的に見て取れる。
臨時記号を記譜する習慣の復活の動きは作曲家であるカルペントラ、ヴィラールト、フェスタ、あるいは理論家であるVanneo,Dentice,Del Lago、そしてリュート奏者のFrancesco da Milanoらにより、1530年代のイタリアで起こった。そしてその30年ほど後にそれはフランス、フランドル地方にも広がったのである。
こうした革命的なできごとがスムーズに予測どおりに行われたか、といえばそれはそうではない。古いものや由緒正しきものがそうであるように、近接した導音の原則もまた必ずしも西洋音楽全般を支配していたわけではない。ルネッサンス後の200年は近代和声的音楽が支配的であったと言えようが、しかしベルリオーズやボロディン、ドヴォルザークといった19世紀の作曲家たちは彼らのインスピレーションの一部を旋法的美学から受けていたのである。
それゆえ、もしもかのドヴォルザークの有名な旋律に下譜のような導音が加えられたらならば、それはこの旋律の破壊を意味するものとなろう。
ex.: A. Dvorak, 9th symphony ("From the New World"). IV. Allegro con fuoco
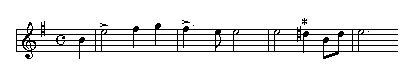
同じ頃、ワーグナー式の半音階主義は作曲家らを正反対の引っ張っていった。この流れは20世紀初頭の無調音楽の出現へと向かっていった。
しかしこの流れの過程はいまだに終着を見ていない、そして旋法的定式もまた今後の西洋音楽の作曲家たちらによりいつの日か再び用いられるようになるにちがいない。
<訳者補遺>
日本の歌謡曲においてもこのページで書かれているような旋法的旋律への関心が高まった時期があった。昭和50年代である。この時期の歌謡曲では旋法的な旋律をもったものがいくつか見られる。たとえば森田公一とトップギャランが歌ったヒット曲「青春時代」ではヒポドリア旋法が用いられている。(下譜参照)

↑原曲;旋法的旋律となっている

↑もしもこのように機能和声的にしたら興ざめである
ところで導音の有無があいまいなままに広まっている名曲もある。たとえば以下のように「荒城の月」「グリーンスリーブス」ではその楽譜に導音のあるものとないものとがある。
↑「荒城の月」最初の部分。
↑同じく「荒城の月」。導音が使用されている譜例。
↑「グリーンスリーブス」最初の部分。

↑同じく「グリーンスリーブス」。導音が使用されている譜例。