| K165 Exsultate,Jubilate |
| ようこそDr.町田のホームページへ モーツァルトの教会音楽のページへ |
| Exsultate, jubilate, o vos animae beatae, dulcia cantica canendo, cantui vestro respondendo, psallant aethera cum me. 歌いなさい、喜びなさい、 あなたがた祝福された魂よ、 甘い歌を歌いながら。 あなたの歌に応えて、 天も私と共に歌います。 |
| K165 Exsultate,Jubilate |
| ようこそDr.町田のホームページへ モーツァルトの教会音楽のページへ |
| Exsultate, jubilate, o vos animae beatae, dulcia cantica canendo, cantui vestro respondendo, psallant aethera cum me. 歌いなさい、喜びなさい、 あなたがた祝福された魂よ、 甘い歌を歌いながら。 あなたの歌に応えて、 天も私と共に歌います。 |
変則的なソナタ形式である。
オーケストラの前奏が、通常の協奏曲同様、提示部の第一主題と第二主題を定型的に、同じ調性(ヘ長調)で演奏する。その後、第21小節より第一主題がソプラノで歌われるが、第一主題には、第36小節から始まる、次のような、2番目のモチーフも伴っている。
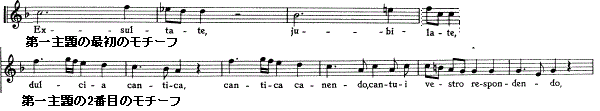
続いて第二主題は、オーボエ伴奏に乗って、属調であるハ長調で第49小節より、以下のように現れる。
![]()
第71小節より展開部となるが、あまり展開部っぽい感じではない。 通常、展開部では、テーマがある程度変奏されて入ってくるのが普通であるが、提示部第一主題の最初のテーマとまったく音型は同一である。
違いは、第71小節のシが?になっていることで、提示部では、ここは♭がついている。つまり両者ともに和音は第二転回形なのであるが、提示部ではバスとの関係が短7度となるのに対して、展開部では長7度となり、幾分、緊張感が高まる。しかし何分、一瞬のことなので、普通に聴いている限り、その違いの認識はまず困難であろう。ところが、次のo
vos animae(第77小節)になると、まったく提示部と同じになる。
![]()
そして再現部が、第85小節より始まる(声楽は第86小節から)が、通常のソナタ形式のように、いかにも”戻りました”という感じではない。ここでは、第一主題の最初のモチーフが省略され、下属調である変ロ長調にて、その2番目のモチーフから、唐突に始まる。こうした特殊なソナタ形式なので、一聴してでは、その形式の認識がしづらい。
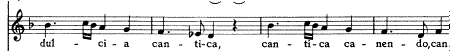
ではなぜ、モーツァルトはこうした再現部を作ったのか?再現部では、第97小節より第104小節まで続く、提示部にはなかった長〜いコロラチューラが出てくる。モーツァルトはおそらく、このコロラチューラを挿入するために、本能的に、第一主題の最初のモチーフをカットしたのではないだろうか?
ソナタ形式において、再現部の冒頭において、提示部の頭がカットされたり、属調や下属調で入ってくることは、時々見かける。たとえば、モーツァルトの弦楽四重奏曲K387の第4楽章では、再現部の冒頭は、提示部の冒頭のフーガ部分が省略されて入ってくる。調性も、下属調となっている。また、ブラームスの交響曲第4番第一楽章でも、提示部の冒頭がカットされて再現部が入ってくる。
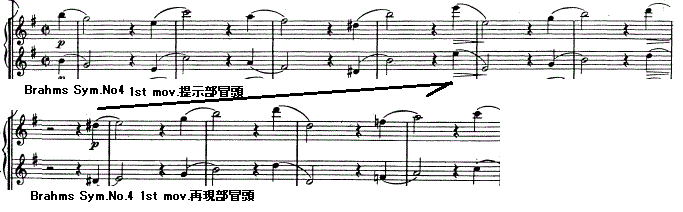
シューベルトの交響曲第5番の第一楽章や、有名な「鱒」では、再現部が下属調で入ってくる。こうした工夫は、いずれも合目的であるような気がする。主調ではなく、下属調での再現部は、私の知る限り、完全4度上で出現しており、展開部の緊張感がそのまま残存する。また、K387やブラームスの頭切りは、いずれも主題の冗長さを排する結果となっている。いずれもその冒頭カットは、きわめて効果的である。