| 俲侾俁俋倂a倝倱倕値倛倎倳倱倣倕倱倱倕乮屒帣堾儈僒乯 儌乕僣傽儖僩偺嫵夛壒妝偺儁乕僕傊丂丂丂丂丂丂丂僋儗僪埲崀偺儁乕僕傊丂丂 妝晥傊偺儕儞僋 奣梫 丂偙偺嬋偼側傫偲儌乕僣傽儖僩侾俀嵨偺帪偺嶌昳偱偁傞丅崱偺擔杮偺姶妎偱偄偗偽彫妛俇擭惗偺帪偵嶌嬋偟偨偙偲偵側傞丅 儌乕僣傽儖僩偼憗弉偺揤嵥偱桳柤偱偁傞偑丄彮擭偺崰偺嶌昳偼廆嫵壒妝偵尷傜偢儌乕僣傽儖僩偺嶌昳偲偟偰偼傗偼傝廗嶌偺堟傪弌側偄傕偺偑懡偄丅屻擭偺鉟梾惎偺擛偔偺柤嬋孮偵斾傋傟偽墘憈夛傗俠俢偺懳徾偲側傞傛偆側傕偺偱偼側偄丅 丂偟偐偟偙偺嬋偼堘偆偺偩丅柍榑儌乕僣傽儖僩偺杮摉偺屄惈偲偄偆傕偺偼屻擭偺傕偺傎偳偵偼擣傔側偄偑丄彮側偔偲傕偙偺帪戙傑偱偵恖椶偑摓払偟偨廆嫵壒妝偺儗儀儖偼姰帏偵儅僗僞乕偟丄嬋偺峔惉傗僆乕働僗僩儗乕僔儑儞側偳丄屆揟攈偺儈僒嬋偺偍庤杮偺傛偆側嬋偵巇忋偑偭偰偄傞丅 丂偙偺嬋偑惗傑傟偨侾俈俇俉擭偲偄偆擭偼傑偩傑偩僶儘僢僋婜偺壒妝彂朄偑巆偭偰偍傝丄屆揟攈壒妝偑帪戙偺嵟愭抂偩偭偨傢偗偱偁傞偑丄儌乕僣傽儖僩偼庛姤侾俀嵨偵偟偰帪戙偺嵟愭抂壒妝傪彂偄偨傢偗偱偁傞丅 丂偲偵偐偔儌乕僣傽儖僩偑偙偺嬋埲慜丄侾侽嵨偺帪偵彂偄偨壗嬋偐偺廆嫵壒妝偼摿偵寙弌偟偨傕偺偱偼側偄偺偱丄斵偼擔杮偱偄偊偽彫妛係擭惗偐傜俇擭惗偱偁傞娫偵挿懌側傞嶌嬋媄朄偺恑曕傪偲偘偨偙偲偵側傞丅 嶌嬋攚宨 丂偙偺嬋偑屒帣堾儈僒偲偄傢傟傞栿偼儌乕僣傽儖僩偑僂傿乕儞偺屒帣堾偺怴偟偄晅懏惞摪偱偺專摪幃偱墘憈偝傟傞儈僒嬋偺拲暥傪庴偗偰彂偄偨偐傜偱偁傞丅 丂偙偺專摪幃偺嵺偵偼俲侾侾俈偺乽Benedictus sit Deus乿傕摨帪偵墘憈偝傟偨偲偁傞偑乮僇儖儖丒僪僯挊丂憡椙寷徍栿乽儌乕僣傽儖僩偺廆嫵壒妝乿倫侾俉乣乯丂乽The complete丂Mozart乿倫俀俁偱偼暿偺嬋偱偁傞偲偝傟偰偄傞丅 丂傑偨僽儔僀僐僢僾幮偐傜弌偰偄傞僗僐傾偺夝愢偱偼傗偼傝俲侾侾俈傕摨帪偵墘憈偝傟偨偲偙偲偱偁傞丅偙傟埲忋偺帒椏傪帩偨側偄巹偵偼偳偪傜偑惓偟偄偐傢偐傜側偄偑丄偄偢傟偵偣傛偙偺俲侾俁俋偺儈僒嬋偑偙偺專摪幃偺偨傔偵嶌傜傟丄侾俈俇俉擭侾俀寧俉擔偺惞曣儅儕傾偺夰擠偺廽擔偺慜擔偵偦偙偱墘憈偝傟偨偙偲偼傑偪偑偄側偄丅側偍丄偙偺擔偑專摪幃偵慖偽傟偨偺偼偙偺晅懏惞摪偑惞曣儅儕傾偺惗抋偵曺偘傜傟偨偨傔偱偁傞丅 嬋偺奣梫 丂偙偺嬋偼僴挿挷偱偁傝丄僉儕僄偺嵟弶偲傾僯儏僗僨僀偱偼俁娗曇惉偺僩儘儞儃乕儞偑撈帺偺僷乕僩傪庴偗帩偭偰偄傞丅乮捠忢儌乕僣傽儖僩偺帪戙偺廆嫵壒妝偱偼僩儘儞儃乕儞偼傾儖僩埲壓偺崌彞傪側偧偭偰偄偔偩偗側偺偑晛捠偱偁傞丅偟偐偟偙偺嬋偵偍偗傞傛偆側僩儘儞儃乕儞偺埖偄曽偼摿偵儌乕僣傽儖僩偵屌桳偺傕偺偱偼側偄偲偄偆丅乯偙偲偵傾僯儏僗僨僀偺偦傟偼旕忢偵報徾揑偱偁傞丅 丂嬋偺婯柾偼偐側傝戝偒偔丄摉帪偺憫尩儈僒乮儈僒嬋偼戝嶨攃偵婯柾偺戝偒側乽憫尩儈僒missa solemnis乿偲婯柾偺彫偝偄乽彫儈僒missa brevis乿偵暘偗傜傟傞丅慜幰偼僥僉僗僩偺挿偄僌儘儕傾偲僋儗僪偑僇儞僞乕僞宍幃偵傛傝僥僉僗僩偑暘妱偝傟偰奺乆悢嬋偯偮偱峔惉偝傟傞偺偵懳偟丄屻幰偼僇儞僞乕僞宍幃傪偲傜偢偵娙寜偵彂偐傟偰偄傞乯偺彂幃偵懃偭偰嶌傜傟丄偟偨偑偭偰僌儘儕傾傗僋儗僪偼僇儞僞乕僞宍幃偱揱摑揑側暘妱偵懃偭偰嶌傜傟偰偄傞丅僴挿挷偱偁傞偨傔丄嬋慡懱偼柧傞偔壺傗偐側傕偺偱偁傞偑丄僉儕僄偺嵟弶偲傾僯儏僗僨僀偼僩儘儞儃乕儞偺撈帺偺嶲壛傕偁偭偰偐憫尩側傕偺偲側偭偰偄傞丅 丂榓惡妛揑偵偼偲偙傠偳偙傠偱婾廔巭偑岠壥揑偵巊傢傟偰偄傞偺偑摿挜偱偁傞丅僆乕働僗僩儔偵偼償傿僆儔偑擖偭偰偄傞丅偙傟偼僂傿乕儞偱墘憈偝傟偨偨傔偱偁傞丅(屻偺僓儖僣僽儖僋偱嶌傜傟偨儈僒嬋側偳偵偼償傿僆儔偑敳偗偰偄傞丅僓儖僣僽儖僋偺嫵夛偺僆乕働僗僩儔偵偼償傿僆儔偑側偐偭偨偨傔偱偁傞乯 嬋偺奺榑 侾僉儕僄 丂娚媫娚媫偺巐晹峔惉丅挷惈偼僴抁挷乚僴挿挷乚僿挿挷乚僴挿挷偲側偭偰偄傞丅娚偺晹暘偺壧帉偼kyrie eleison,媫偺晹暘偼kyrie ,christe椉曽偱偁傞丅媫偺晹暘偼摨偠嬋偺孞傝曉偟偱偁傞丅 嵟弶偵備偭偔傝偲偟偨摫擖晹偑偮偄偰偄傞丅償傿僆儔偲僩儘儞儃乕儞偺僆僽儕僈乕僩偑報徾偵巆傞丅崌彞偼儂儌僼僅僯僢僋側巐惡偦傠偭偨傕偺偱偁傝丄搑拞偱尭幍偺榓壒偑擇売強擖傞偨傔偵晄埨掕側嬁偒偲側傝丄偙傟偑僉儕僄僄儗僀僜儞乮庡傛偁傢傟傒偨傑偊乯偲偄偆捝楏側嫨傃偺尨摦椡偲側偭偰偄傞丅側偍丄偙偺摫擖晹偼僴抁挷偱偁傞偑丄偙偺挷惈偼摉帪偼憭幃偺挷惈偲偝傟偰偍傝丄儌乕僣傽儖僩偑側偤晛捠偺儈僒嬋偱偙偆偟偨挷惈傪巊梡偟偨偐偑屆偔偐傜榑憟偺揑偱偁偭偨傛偆偱偁傞丅偙偺摫擖晹偼僪儈僫儞僩偱廔巭偟丄師偺Allegro偑巒傑傞丅 丂偙偺Allegro偺晹暘偼僜僫僞宍幃偱彂偐傟偰偄傞丅摫擖晹偲偼懪偭偰曄傢偭偰僴挿挷偺柧傞偄嬋偱偁傞丅崌彞偑擖偭偰偔傞捈慜偺戞25彫愡偺 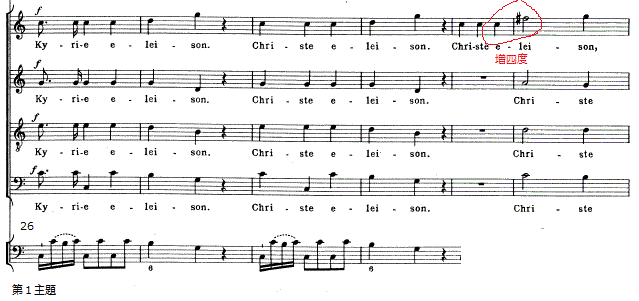 戞俁係彫愡傛傝僩挿挷偵揮挷偟偰戞擇庡戣偑僜儘僇儖僥僢僩偲偟偰弌偰偔傞丅  戞係係彫愡傛傝偄傢備傞揥奐晹偲側傞丅戞俇俁彫愡偱慜弎偺嵟屻偵傑偨慜弎偺壒宆偑僩挿挷偵揮挷偝傟偰嵞搙尰傟偰嵞尰晹偵擖傞丅偟偨偑偭偰嵞尰晹偼懏挷偱偁傞僩挿挷偱擖偭偰偔傞偑丄偙偆偟偨偙偲偼摿偵傔偢傜偟偄偙偲偱偼側偄丅 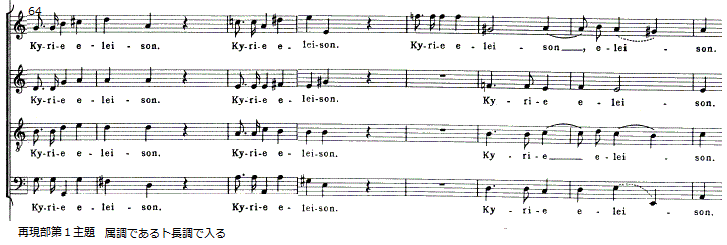 丂戞俈俀彫愡偐傜偼戞擇庡戣偑崱搙偼僀抁挷偱弌偰偔傞丅 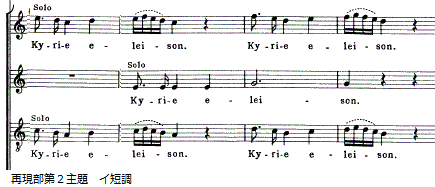 嵟屻偵傑偨儐僯僝儞偱 俀僌儘儕傾丂 丂僌儘儕傾偼偙偺帪戙偺儈僒嬋偱偼捠忢偼嵟弶偺乽Gloria in excelsis Deo乿偺偲偙傠偼愭彞幰偑壧偭偰崌彞偼乽et in terra pax乿偐傜擖傞傛偆偵嶌嬋偝傟傞偑丄偙偺俲侾俁俋偱偼嵟弶偐傜嶌嬋偝傟偰偄傞丅嬋偼摉帪偺揱摑偵偟偨偑偭偰埲壓偺傛偆偵彂偒暘偗傜傟偰偄傞僇儞僞乕僞宍幃偱偁傞丅乮幃暘慡懱偺儔僥儞岅偲朚栿偵娭偟偰偼儈僒嬋偺幃暥傪嶲徠偺偙偲乯 嘆Gloria in excelsis Deo乣丂丂丂崌彞丂僴挿挷 嘇Laudamu te乣丂丂丂丂丂丂丂僜僾儔僲僜儘亄傾儖僩僜儘丂僩挿挷 嘊Gratias,agimus tibi乣丂丂丂丂崌彞丂僴挿挷仺僀抁挷 嘋Domine Deus Rex coelestis乣丂僥僲乕儖亄僶僗僜儘丂僿挿挷 嘍Qui tolis peccata mundi乣丂丂崌彞丂僿抁挷 嘐Quoniam tu solus sanctus乣丂僜僾儔僲僜儘丂僿挿挷 嘑Cum sancto Spiritu乣丂丂丂丂崌彞偵傛傞僼乕僈丂僴挿挷 丂嘆偺晹暘偼儂儌僼僅僯僢僋側崌彞偱偁傞偑丄報徾揑側偺偼戞侾俉亅侾俋彫愡偺丄僆僋僞乕僽偺僩儔儞儁僢僩偲偲傕偵偁傞 僥傿儞僷僯偺 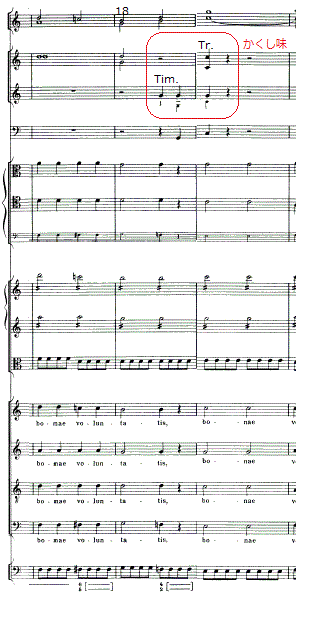 傑偝偵塀偟枴丅偙偙偺偲偙傠偼偁傑傝戝壒検偱偼側偄偺偱墘憈偺嵺偵偼偤傂栚棫偨側偄傛偆偵丄偐偮偼偭偒傝挳偙偊傞傛偆偵偙偺僥傿儞僷僯傪擖傟偰傕傜偄偨偄傕偺偩丅 丂師偺嘇偱偼尫偺敽憈偵傛傞僜僾儔僲偲傾儖僩偺旤偟偄擇廳彞丅挷惈偼尨挷偺僪儈僫儞僩偱偁傞僩挿挷偵曄壔偟偰偄傞丅戞55乗俇俀彫愡偺僜僾儔僲偲傾儖僩偺僐儘儔僠儏乕儔晽偺摦偒偺偲偙傠偼偦傟偧傟adramus,丄laudamus偲暿偺尵梩傪壧偭偰偄傞偺偵嵟屻偼摨偠-mus te偱偆傑偔塁傪摜傫偱廔傢偭偰偄傞偺偑偍傕偟傠偄丅巹偼偙偺晹暘偼俴丏儌乕僣傽儖僩偺桳柤側乽偍傕偪傖偺僔儞僼僅僯乕乿偺戞擇妝復偵側傫偲側偔暤埻婥偑帡偰偄傞偲巚偭偰偄傞偺偩偑偳偆偱偟傚偆偐丅 丂師偺嘊偺晹暘偼抁偄偑Adagio丂偲Vivace偺懳斾偑尒帠偱偁傞丅戞79彫愡偱偼俠倓倳倰仺俧倓倳倰仺俙倱倓倳倰偲偄偆堦晽曄傢偭偨婾廔巭偑梡偄傜傟偰偄傞丅偦偟偰側偤偐暯峴挷偱偁傞僀抁挷偱廔巭偡傞丅 丂嘋偺晹暘偼尨挷偺僒僽僪儈僫儞僩偱偁傞僿挿挷偺柧傞偄僥僲乕儖偲僶僗偺擇廳彞偱偁傞丅偙傟偲偄偭偨摿挜偼側偄偑儌乕僣傽儖僩傜偟偄柧傞偝傪帩偮丄偁傞堄枴偱儈僒嬋傜偟偐傜偸暤埻婥傪傕偭偰偄傞嬋偱偁傞丅 丂師偺嘍偺晹暘偱偼壧帉偺曄壔偵懳墳偟偰堦揮偟偰僿抁挷偺埫偄暤埻婥偵側傞丅崌彞偼堦娧偟偰儂儌僼僅僯僢僋偱偁傝丄敽憈傕儚儞僷僞乕儞偑懕偔偑丄榓惡偺曄壔偑帺嵼偱偁傝丄挳偄偰偄偰朞偒傞偙偲偼側偄丅柧傞偄僨儏僄僢僩偺偁偲側偺偱偙偲偝傜偵廳嬯偟偝傪姶偠傞偑丄偍偦傜偔偼儌乕僣傽儖僩偼偙偙偼彞偊傞傛偆側壧偄曽乮僀儞僩乕儞乯偺墑挿偺傛偆側姶偠偱彂偄偨偺偱偁傠偆丅偟偨偑偭偰偙偙偺晹暘偼偁傑傝姶忣夁懡偵側傝偡偓側偄傛偆側偁偭偝傝偲偟偨壧偄曽傪偟側偗傟偽偄偗側偄丅側偍丄偙偺嬋偱傕傗偼傝晄巚媍側婾廔巭偑尒傜傟傞丅 丂偙偺嬋偼僪儈僫儞僩偱偁傞僴挿挷偱廔巭偟丄師偺嘐偑僿挿挷偱擖偭偰偔傞丅嘐偼乽庡偺傒惞側傝丄庡偺傒墹側傝丒丒丒乿偲偄偭偨壧帉傪斀塮偟偰僜僾儔僲僜儘偱柧傞偔崅乆偲壧傢傟傞丅 丂嵟屻偺嘑偺晹暘偼姷椺偵偟偨偑偄僼乕僈偱偁傞丅偙偺庡戣偼憹巐搙傪娷傫偱偄傞揰偱曄傢偭偰偄傞丅乮壓晥嶲徠乯傾乕儊儞偺偲偙傠偼挿偄僆儖僈儞億僀儞僩偲側偭偰偄傞偑偙傟傕傛偔偁傞僷僞乕儞偱偁傞丅乮僿儞僨儖偺儊僒僀儎偺傾乕儊儞僐乕儔僗偺帪戙偐傜偁傞乯  丂偙偺僼乕僈偺摿挜偲偟偰偼丄慡懱偵傢偨偭偰丄傾儖僩僷乕僩傪丄僆僋僞乕僽忋偱侾倱倲償傽僀僆儕儞偲僆乕儃僄偑側偧偭偰偄傞偙偲偑嫇偘傜傟傞丅gloria偵偍偄偰偼丄僩儘儞儃乕儞偑侾僷乕僩偟偐巜掕偝傟偰偄側偄偺偱丄偍偦傜偔偼揱摑揑側僩儘儞儃乕儞偵傛傞傾儖僩僷乕僩偺曗嫮偑尒崬傔側偄偲傒偰丄偙偺傛偆側偙偲傪偟偨偺偐傕偟傟側偄偑丄傎傏摨帪婜偵彂偐傟偨丄偙偺嬋偲巓枀嬋偲偝傟傞K66偵傕摨偠傛偆側傾儖僩偺曗嫮偑尒傜傟傞丅偍偐偘偱偙偺慬抲偵傛傝丄偙偺僼乕僈偵偍偄偰偼丄傾儖僩僷乕僩偑旕忢偵栚棫偮丅 丂偦傟偵偟偰傕偙偺僼乕僈偺尒帠偝偲偄偭偨傜両12嵨偺儌乕僣傽儖僩偼姰慡偵僼乕僈偺嶌朄傪儅僗僞乕偟偰偍傝丄側偍偐偮僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偼姰帏偵嵟怴偺傕偺偲偟偰嶌傜傟偰偄傞丅乮僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偼僶儘僢僋婜偐傜屆揟婜偵偐偗偰戝偒偔曄壔偟偨丅儌乕僣傽儖僩偺彮擭帪戙偼傑偩偦偺怴偟偄僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偺傗傝曽偑妋棫偟偨偽偐傝偺帪婜偱偁偭偨丅偦偺帪婜偵偡偱偵偙傟偩偗偺嬋傪彂偄偰偄傞偺偼嬃堎偲偟偐偄偄傛偆偑側偄丅側偍儌乕僣傽儖僩偼屻偵怴偟偄僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偱僿儞僨儖偺儊僒僀傾傪曇嬋偟偰偄傞偺偼桳柤偱偁傞乯 丂偙偺嬋傕傑偨嘆傗嘊偺晹暘偲摨條丄婾廔巭偑梡偄傜傟乮戞315彫愡乯嵞搙僼乕僈偺庡戣偑採帵偝傟偰廔傢傞偲偄偆宍懺傪偲偭偰偄傞丅 儌乕僣傽儖僩偺嫵夛壒妝偺儁乕僕傊丂丂丂丂丂丂丂僋儗僪埲崀偺儁乕僕傊丂丂 |