K108 Regina Coeli (天の女王)
楽譜へのリンク
マリアのアンティフォンについて
モーツァルトはRegina Coeli(天の女王)という曲をK108、K127、K276の計3曲書いている。このRegina
Coeliというのはマリアのアンティフォンと呼ばれているものの一つでこのマリアのアンティフォンは以下の4種類ある。
①Alma Redemptoris Mater (救い主なる御母よ)
②Ave Regina caelorum(めでたし天の女王)
③Regina coeli(天の女王)
④Salve Regina(めでたし女王)
本来アンティフォンというのは交唱という訳語のごとく、二つのコーラスによって交互に詩篇を歌う歌い方を言うが、マリアのアンティフォンはなぜか交互に歌うというわけではないのにアンティフォンといわれている。この4種類のマリアのアンティフォンは聖務日課における終課の最後に歌われていたもので、季節によってこの4種類のマリアのアンティフォンが順番に歌われていたのである。マリアのアンティフォンは古くから4種類ともさまざまな音楽がつけられてきた。特にルネッサンス時代がいちばんさかんだったようである。モーツァルトはこれらの4種類のうちのRegina Coeliのみに三つの曲をつけたことになる。
Regina Coeliの歌詞
Regina coeli laetare Alleluja 天の女王、喜べ、ハレルヤ
Quia quem meruisti portare Alleluja あなたのお生みになった御子はハレルヤ
Resurrexit sicut dixit Alleluja お言葉どおり復活された。ハレルヤ
ora pro nobis Deum 我らのために祈りたまえ。
Alleluja ハレルヤ
K108の概要
この曲は自筆譜が残っており、「1771年5月、ザルツブルクにて」という自署まで残っている。しかしだからといってザルツブルク大聖堂で演奏されたものではないらしい。それはオーケストラにヴィオラが2パート入っているからである。(ザルツブルクのオーケストラにはヴィオラがなかった)
この曲は四楽章構成となっており、第一曲は合唱、第二、三曲はソプラノソロ、そして第四曲は合唱+ソプラノソロである。その雰囲気はバロック期のナポリ楽派の音楽がそのモデルとされている、と言われるほどに確かにナポリ楽派的である。第二曲のソプラノアリアや第四曲のコロラチューラ、第三曲のナポリの六の使用などがその根拠である。しかし第一曲と第四曲はしっかりと古典派の基本であるソナタ形式で構成されており、モーツァルトがイタリアの音楽をよく研究した上で、同時代の最新式の書法をもってこの曲を書き上げたことがわかるのである。
第一曲Regina coeli laetare Alleluja この第一曲はととのったソナタ形式で書かれている。定型的な、同一調による第一、第二主題による序奏のあとに合唱が入ってきて第一主題を歌う。第二主題は型どおりト長調で出てくる。そして短い展開部のあとに型どおりの再現部となる。
第二曲Quia quem meruisti portare Alleluja Resurrexit sicut dixit Alleluja
ソプラノアリア。調性はヘ長調。途中にいかにも歌うのがむずかしそうなコロラチューラが2か所入っている。こういったところは本当にイタリア的である。途中と最後のAllelujaは合唱が合いの手のように担当している。
第三曲ora pro nobis Deum
ソプラノアリア。 調性はイ短調。この第三曲の特徴は何といってもナポリの六の使用である。下譜はソプラノアリアの最初の部分であるが、このシ♭がナポリの六である。これを聴くとスカルラッティらナポリ楽派のカンタータなどを思い出しますね。
![]()
第四曲Alleluja 合唱+ソプラノアリア。やや変則的なソナタ形式である。展開部がほとんどないので、ソナタというより、ソナチネといった方がよいかもしれない。この第四曲の歌詞はAllelujaのみである。第一曲同様の長い序奏のあと合唱が第一主題を歌う。その後今度はソプラノソロが第二主題を歌う。やはりコロラチューラの、歌うのがむずかしい主題である。その後に合唱が続くがこれは第一曲の第二主題に似ている。
その後、ほとんど展開部らしい展開部はなく、今度は再現部が属調であるト長調で入ってくる。再現部が提示部と異なる調性で入る例はしばしば見られるものである。(当サイトで紹介した同じくモーツァルトのK381の第四楽章、シューベルトの第五交響曲、「鱒」などにその例が見られる)その後は第二主題がやはりソロ→合唱と原調で現れ、明るく曲を終える。
まとめ
カルル・ドニは「モーツァルトの宗教音楽」の中で、モーツァルト研究の泰斗アインシュタインがこの曲を「声楽部をもったイタリア風シンフォニアにすぎない」と言っていることに不満を持ち、この曲を「端倪すべからざる曲である」(相良憲昭訳 同書p62)と書いているが、確かにこの曲はよくできた名曲である。この曲が書かれた1771年といえばまだ大バッハが死んで21年、世上は古典派音楽の確立期であった。まだまだバロック期の音楽の雰囲気も残っていたにちがいない。このK108はそんな雰囲気の中で、イタリアバロックの音楽と当時最新式の古典派のソナタ形式をみごとに融合させた名曲といえるであろう。
K127 Regina Coeli
楽譜へのリンク
この曲は1772年に広範囲な音域を持つ歌手であったミカエル・ハイドン夫人のために作られた。彼女はかなり有能な歌手であったらしく、そのためにこの曲の独唱部はかなり技巧的にむずかしい。曲は当時の交響曲の形式をそのまま踏襲しており、ソプラノソロ+合唱つきの交響曲といった感じである。楽器はモーツァルトの三作のRegina Coeliの中ではこの曲のみ金管楽器やティンパニが使われておらず、第二、三楽章でフルートが使われているのが目立つ。
第一楽章はソナタ形式の合唱曲である。前奏で第一、第二主題が出され、協奏曲と同じ構成の、定型的なソナタである。
この曲の特徴は、オーケストラと合唱が独立していてそれぞれに自己主張をしていることである。たとえば第二主題では以下の如くである。ここで注目すべきは、主題は1stバイオリンで奏されるということ。通常合唱曲では、合唱が主でオーケストラが従であるから、合唱で主題が出るものだが、この曲はそうではないのである。(下譜;但し、その後の合唱は提示部と再現部で共通なので、ここからが第二主題と考えることも可能であるが、前奏においては下譜の主題が第二主題として出ている) すなわち、オーケストラが強い曲といえる。
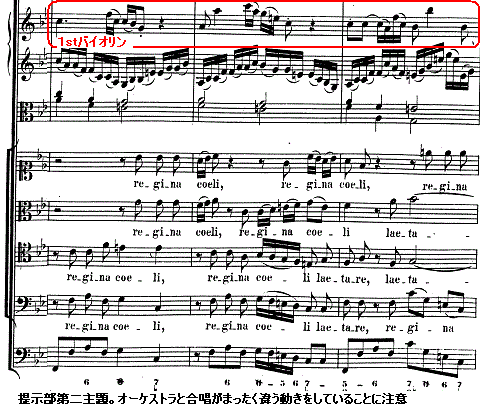
上譜(提示部第二主題部分)を、ここに対応する再現部の第二主題部分と比べてみよう。(下譜)
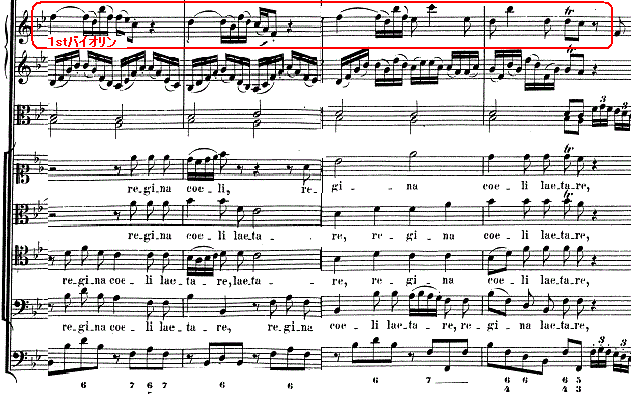
↑再現部第二主題
両者を比較すると、1stバイオリンがまさに主題を奏していることがよくわかる。両者はほぼまったく同じ音型だから。しかし、対応する部分の合唱パートを見ると、まったく違っていることがわかる。これにより、この曲においてはオーケストラが主で、合唱はあくまでもオーケストラに従属した存在であることがよくわかるのである。
さらに細かくみると、オーケストラは古典派的に、ホモフォニックかつ分散和音的に動くのに対して、合唱はポリフォニックに動いていることがわかる。モーツァルトは何と、この曲において、ソナタ形式を取りながら、前時代であるバロック的要素と、新時代の古典派(変な言い方だがこうしか表現のしようがない)の要素を極めて精巧に結合しているのである。
第二楽章と第三楽章はつながっている。(したがってひとつの曲とみなしてもよいのかもしれないが、最後の楽章がソナタ形式なのでこれを第四楽章とした)前者はソロと合唱で3/4拍子でヘ長調、後者はソプラノソロで4/4拍子で変ホ長調である。いずれもソロパートはかなり技巧的である。
第四楽章は歌詞は「Alleluja」のみで、前奏なしでいきなりソロで入ってくる。形式はやはりソナタ形式であるが、コンチェルト調の定型的な第一楽章と比較するとかなりモーツァルトがいろいろな工夫をしているのがわかる。
たとえばこの楽章では前述のようにソロがいきなり入ってきて第一主題を歌うが、一部はかなり技巧的である。第二主題は合唱で出てくるが、型どおりこの第二主題は第一主題の属調であるヘ長調である。ここで面白いのは、ソプラノとバスが声部交換を行っていることである。その昔中世やバロック期でよく使われていたこうした声部交換(Stimmtausch)がこんな場面ででてくるのもおもしろいものである。
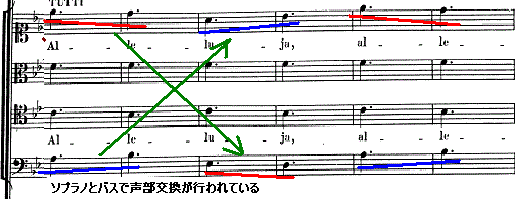
提示部はこのまま合唱がずっと続く。
展開部はソロが主導し、合唱が続くが、あまりパッとせずに、早々に再現部となる。だいたいにおいてソナタの原則通りであるが、最後の終結部にはソプラノソロのコロラチューラが入って、かなり長大である。
この第四曲は、イタリアカンタータの伝統を受け継いだソプラノソロのコロラチューラと当時最先端のソナタ形式が物の見事に結合した名曲であると言える。モーツァルトは、フーガとソナタを結びつけた曲は割と書いている(たとえば、K387第四楽章やジュピター交響曲第四楽章など)が、イタリアバロックとソナタ形式を結合させた曲はさほど多くないように思う。したがって、この第四曲は、そうした面において、稀有なる名曲といえるのではないか。
<まとめ>
この曲は、音楽的には、K276のRegina Coeliほどに強く印象に残るというほどのものではないが、技巧面で見た場合、極めて分析のしがいのある曲である。第一曲は合唱協奏曲とも言うべき定型的なフーガであるが、オーケストラは合唱の伴奏に甘んじることなく、大いに自己主張をしている。
また第四曲はイタリアバロックとソナタ形式が見事に結合しており、モーツァルトの高い技術を物語る。いずれにせよこの曲は、漠然と鑑賞するよりは、分析しながら聴くほうが面白い曲である。
![]() K276 Regina Coeli(天の女王)
K276 Regina Coeli(天の女王)
楽譜へのリンク
この曲は自筆譜が残っていないので、正確な作曲年が不明である。アインシュタインは作曲様式からこの曲の作曲年を1779年とし、それが広く受け入れられてきたが、あくまでも作曲様式からの推定のため、科学的根拠がない。作曲様式からの作曲年の推定がいかに不正確であるかは、古くはバッハ研究の泰斗シュピッタによる、作曲様式から推定したバッハのカンタータの作曲年代が、戦後のデュルらの実証的な研究でことごとくくつがえされたことでもわかる。したがってこの曲の作曲年代はわからない、としておいた方がよいのかもしれない。なお、この曲ではヴィオラが含まれていないので、ザルツブルク大聖堂で演奏されたであろうことはまちがいないと思われる。
この曲に関してはカルル・ドニは前掲書で「装飾趣味がいささか過剰で、表面的なお祭り気分のモテット」(相良憲昭訳p69)とさんざん酷評しているが、私はそうは思わない。確かにRegina Coeliのテキストに対する音楽としては華美な気がしないでもないが、一つの宗教作品として考えればこれはよくできた名曲であると思う。少なくとも私はモーツァルト作の3曲のRegina Coeliの中では一番好きである。
曲の概要
この曲は他の二曲のRegina Coeliと異なり、カンタータ形式を取らず、最初から最後までAllegroの一曲のみでできている。またソロも前二曲のようなコロラチューラはなく、ソロカルテットとしてかたまりを作り、合唱と一体となっている。(こうした作り方がアインシュタインをしてK321のヴェスペレと同時期の作曲年と考えさせしめたのであろう)
形式は、かなりわかりにくくはあるが、一応はソナタ形式であるとみてよい。メインのテーマは第5小節から始まる、以下の2つである。

Regina coeli laetare Alleluja (第一主題 最初〜第37小節)
Quia quem meruisti portare(第二主題 第38〜第50小節)
Alleluja
Resurrexit sicut dixit Alleluja
ora pro nobis Deum (展開部 第51小節〜第105小節)
Alleluja(再現部 第106小節〜)
調性は第15小節でGdurに転調し、以下のような新しい主題が現れる。すわ、これが第二主題と思われるが、この主題は再現部では出てこない(展開部で転調して現れる)ので、違うものと判断する。
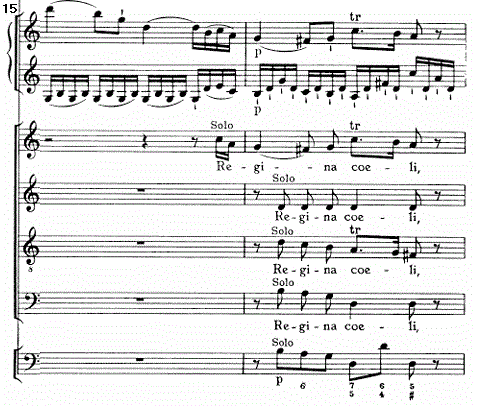
その後、第38小節から、Quia quem meruisti portare Allelujaの歌詞において、やはりGdurで以下のような別の主題が出現する。この主題も、展開部で(第92小節〜)で出てくるが、再現部でも第135小節から現れるので、、これが第二主題と判断する。
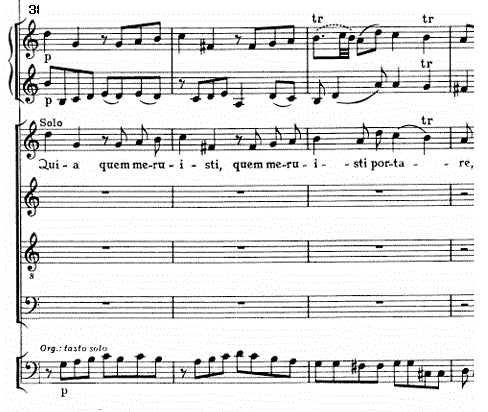
第51小節より、展開部に入ると考える。Edurの7の和音の第一転回で終始した後、曲のテーマである16分音符のAllelujaは、Amollで始まる。第61小節より、以下の新しい主題が入ってくる。これは、これまでにはない、下属調Fdurで入るので、何となく新鮮である。
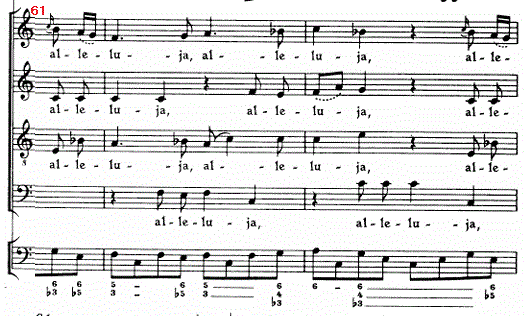
その後、ora, pronobisの歌詞とともに、新しい主題が入る。この主題は、同じ調性で、再現部の第124小節から再度入ってくる。この主題の扱いが、この曲の構造解析をわかりにくくしていると言える。なぜなら、提示部には出てこないで、展開部で初めて出てきて、かつ、まったく同じ形で再現部に出現するからである。
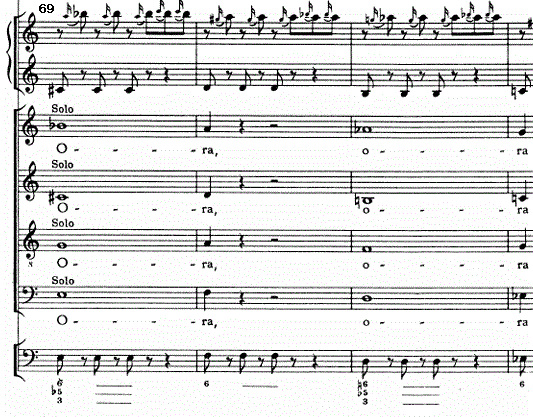
続いて、第81小節より、第15小節の主題が、特に変形されることなく、Cdurにて入ってくる。さらには第92小節から、第38小節からの主題が、やはりCdurで入ってくる。こうした展開が、展開部らしくなく、先の主題とともに、曲の構造をわかりにくくしている。通常ならば、こうしたやり方は、展開部ではなく、再現部で行われるものだから。
結局のところ、再現部は第106小節からと思われる。Regina coeli laetareの主題は省略され、allelujaの部分から入ってくる。なお、こうした、再現部における第一主題の頭切りは、わりとしばしば行われている。くどくなるのを避けるためで、有名なところでは、同じくモーツァルトの弦楽四重奏曲K387第四楽章、K165Exultate
Jubilate,シューベルトの交響曲第5番第一楽章、ブラームスの交響曲第4番第一楽章などがある。
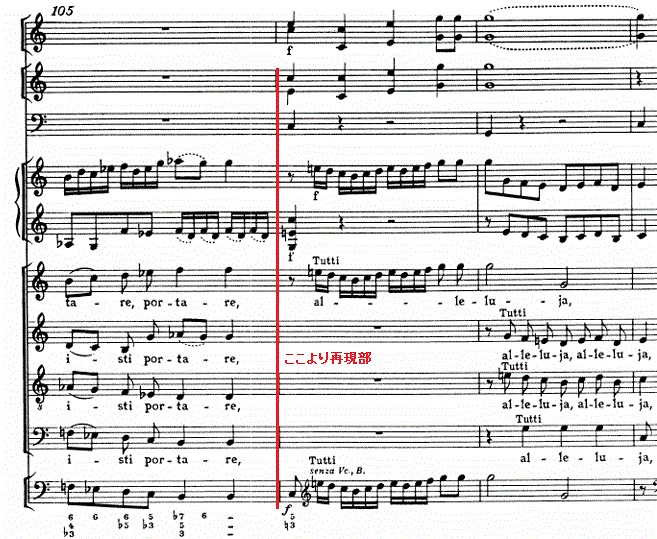
提示部→展開部の時とよく似たつながりになっているが、展開部→再現部では、Gdurの7の和音の第一転回で終始した後に、主調であるCdurで入ってくる。提示部と異なるのは、allelujaの主題がソプラノによってoctave高く入ってくるのと、逆に、Regina coeliの主題がアルトによってoctave低く入ってくることである。細かな配慮がなされている。
そして第二主題は、前述のように、第135小節より、主調にて入ってくる。その間、第124小節より、展開部で初めて入ってきた(第69小節〜)ora, pronobisのまったく同じ主題がはめ込まれているのが特徴的である。
この曲の魅力は何といってもAllelujaの扱いである。何度となく出てくるヘンデルのメサイヤの中のハレルヤコーラスのような「Alleluja,Alleluja」という叫びや最後のユニゾンのAllelujaなどは大変に印象的である。音楽的にはあまり深いとは言えないのかもしれないが、聴衆に訴える力という点ではヘンデルの作品群のような抜群のものがあるような気がする。