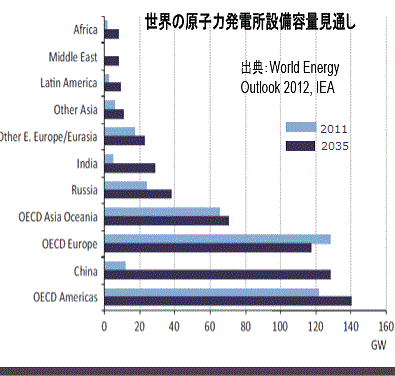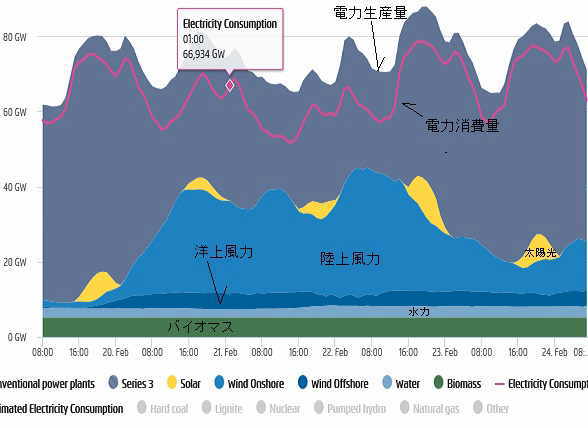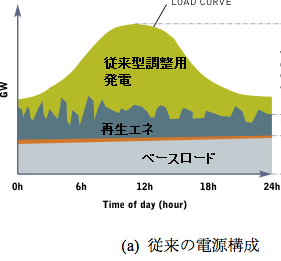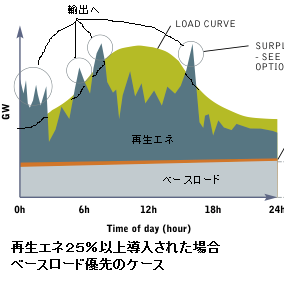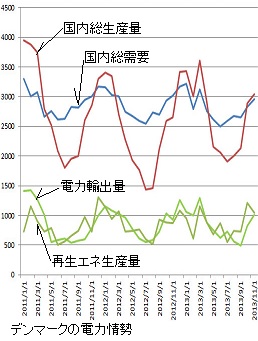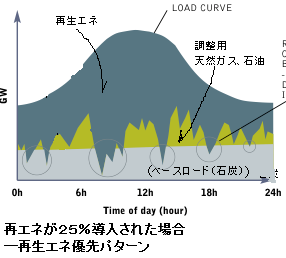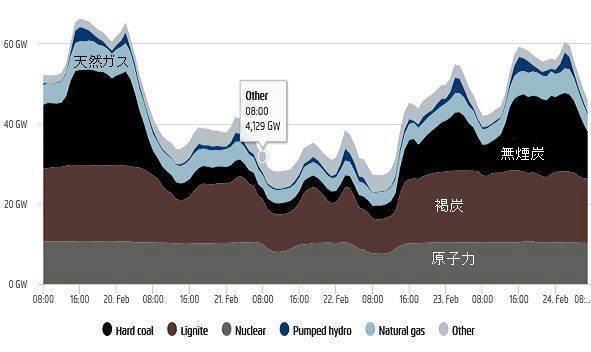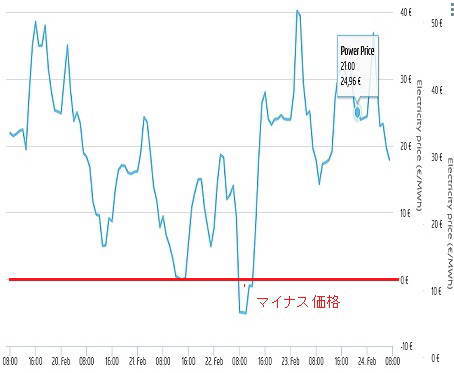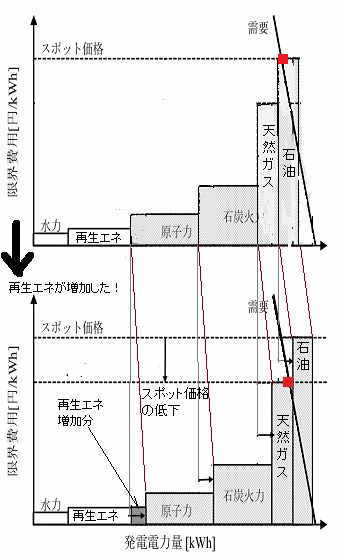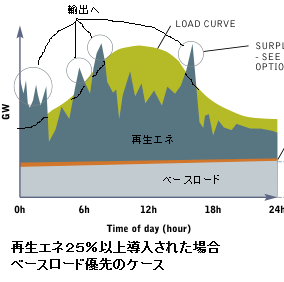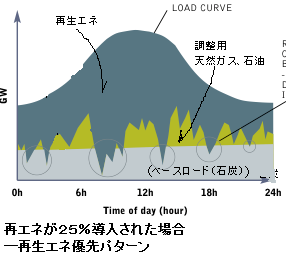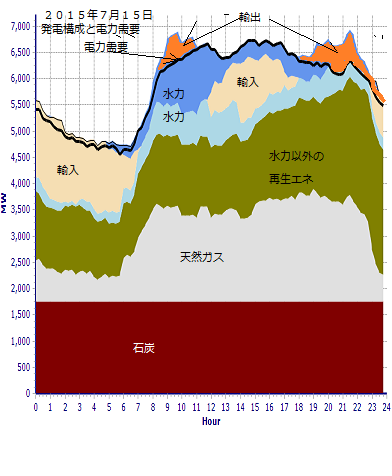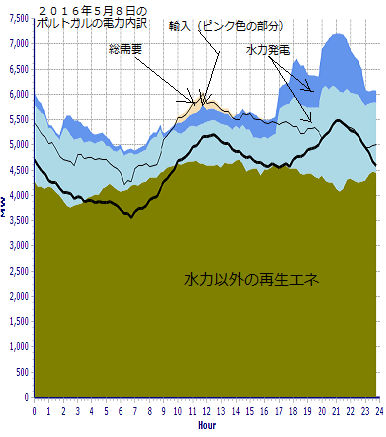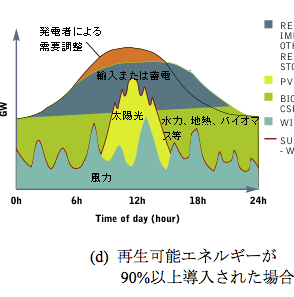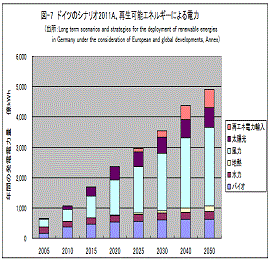◆「放射能心配 福島へは戻れない」
東京電力福島第一原発事故に伴って県東部に自主避難している女性(40)が、障害児を女手一つで抱えながら今後の生活に不安を募らせている。福島県が全国の自主避難者に続けてきた住宅の無償提供を、来年3月末で打ち切るためだ。群馬県は県営住宅の入居希望者に、定期募集の抽選番号を二つ与える支援策を提示。しかし、女性の不安解消にはつながりそうもない。 (菅原洋)
「小学生の長女は障害があるだけに、放射能の影響が大きいのではと心配してしまう。まだ心配は拭い去れず、福島県へは戻れない。これからどうしたらいいのか」。女性は途方に暮れた表情を浮かべる。
原発事故当時、福島県沿岸部に住んでいた女性は2012年1月、長女への影響を第一に考えて群馬県へ避難。現在は民間の賃貸住宅で暮らしている。
パートの職を得たが、月収は10万円余り。児童手当と母子手当は月に計数万円だ。ただ、家賃は約5万円で、住宅の無償提供が打ち切りになると、生活費などが加われば、家計は赤字になる恐れがある。
福島県は民間の賃貸住宅に入る自主避難者には、低所得者のみ家賃の一部を補助する方針。女性は対象になる可能性はあるが、打ち切り後の2年間限定だ。
「特別支援学級に通う長女は友達ができ、学校にもなじんできた。転校させたくはない」。女性が住む学区には、県営住宅を含めて適当な公営住宅は見当たらないという。
長女から目が離せないため、勤務時間を増やしたり、転職したりするのは難しい。県内には、親類などの頼れる人もいない。
「長女に障害があっても、(住宅の問題では)福祉制度にも助けてはもらえない」。母子の孤立感は、深まっている。
◆実効性ある定住支援策を
全国の自治体は、住宅の無償提供打ち切りに悩む自主避難者たちに対し、さまざまな支援策を打ち出している。
鳥取県は県費を充て、住宅の無償提供を2年間延長すると決定した。東京都は都営住宅に専用枠200戸、埼玉県は県営住宅に優先枠約100戸をそれぞれ設定した。山形県は約50戸の県職員公舎を無償提供する方針だ。
新潟県は公営住宅へ移る場合に転居費用を5万円まで支給する。民間住宅を借り、小中学生がいて転校できない場合には、1万円を補助する。
一方、県営住宅の入居希望者に抽選番号を二つ与えるという、群馬県の支援策はどうか。定期募集は年に4回あるが、利便性が高い人気の物件は倍率が数倍から10倍以上。実際にメリットがどの程度あるのかが不透明だ。
群馬県によると、住宅の無償提供が打ち切りとなる県内への自主避難者は、5月現在で100世帯、計約270人。このうち、民間住宅に62世帯、各市町を含む公営住宅に38世帯が住む。県は今春示した方針通り、転居先が未定などの約90世帯を各市町の協力も得て戸別訪問し、相談には乗っている。
県では大沢正明知事を旗振り役に、深刻化する人口減少社会への対策に各市町村が取り組んでいる。県内への定住を切望する自主避難者たちに、各自治体がどこまで包容力と寛容さを示せるのか。その真価が今、厳しく問われている。
(菅原洋)