■平成27年12月1日 「居於治忘乱」の東京新聞
この東京新聞社説で引用された吉田茂の言葉は、ある程度こうした分野を勉強したことのある人ならば、誰でも知っていることだ。
そうした知識から考えると、東京新聞は吉田茂の言葉を誤解しているように思える。吉田が防衛大1期生対して、「君たちが日陰者である時の方が国民や日本は幸せなのだ。耐えてもらいたい」と言ったことに関しては、やはり当時の情勢を知らねばならない。 親英米派吉田茂は、戦前はいわゆる軍部とは敵対していた。したがって、自衛隊の必要性は理解しつつも、旧軍幹部にそれを乗っ取られることを恐れていた。こうしたことから、そもそも吉田は、自衛権さえ放棄する答弁をしている。逆に、共産党の野坂参三が自衛権を主張するという、奇妙な時代だった。 吉田の「日陰者云々」発言は、こうした時代背景を踏まえてのことなのである。 つまり、旧軍の行動への反省期であったがゆえに、このような抑制的発言をしたものだと私は思う。当時、もしも自衛隊が、旧軍のように派手なドンパチをやれば、戦争で疲弊した国民からは、強い反感を持たれたことであろう。 だが戦後70年で、国際情勢は大きく変わり、自衛隊そのものの認知度も格段に高くなった。 自衛隊の一般への認知度の高まりは、主として国内の災害派遣におけるその活躍によるものであるが、1992年に成立したPKO法にもとづく海外派遣もまた、世界からの認知度の高まりには貢献していると言える。 当時、サヨク、リベラルどころか、危機管理を知り尽くしているはずのあの後藤田正晴でさえ、自衛隊の海外派遣には反対していた。後藤田でさえ、情勢の変化についていけなかったのである。 現在の”仮想敵国”は、なんと言っても中国である。中国は南シナ海のガン細胞で、この海域において、無秩序に増殖をし、日本を始めとする東~東南アジアの生命線を破壊しようとしている。 現在は、直接自らの生命には影響しない米国が抗がん剤の役割をしているが、それでよいのだろうか。 直接自らの生命を脅かされようとしている日本もまた、抗がん剤の役割をきちんとはたすべきではないのか。 吉田茂が言うように、「自衛隊が日陰者」であることは、確かに国にとっては平時を意味するわけだから、それに越したことはない。 しかし、吉田の頃には存在しなかった真っ赤赤な大国が、今、その野望をむき出しにしつつある中、もはや自衛隊は「日陰者」に甘んじているわけにはいかないだろう。堂々と太陽を浴びることもまた必要なのである。 「居於治不忘乱」と言った吉田が今生き返ったら、きっとこう言うことだろう。 岸の孫はよう頑張っとる。それでこそ「居於治不忘乱」だ。東京新聞たちの主張は逆だ。「居於治忘乱」だ。あいつら、オレの「日陰者」発言をいいように使っとる。そんなんじゃ、日本は生きて行けない! | |
| ■平成27年12月1日 劣化するネット
●ホームページの原点は”発信” 私がホームページを作りはじめたのは、今から約14年前、2002年2月のことだ。 パソコンを初めて扱ったのが2001年4月、1年近くネットサーフィンをしてきて、ホームページとやらを自分でも立ち上げてみよう、と思い立った。 当時はまだインターネットやヤフーの検索などが始まって5年ほどであったが、すでに山ほどのサイトがあった。その特徴は、以下の二つであった。 ①企業などの宣伝のための公式のホームページ ②個人が立ち上げた、知識、情報発信のためのホームページ ①に関しては現在もさほど概念は変わらずに脈々と続いているので、ここでは主として②について考えてみたい。(以後、ホームページをHPと略す) 当時のHPのパラダイムは、とどのつまり、”発信”だった。別に有名人ではなくとも、普通の人にはないが面白い知識や情報を持っているという自信がある人が、HPを開設し、その発信を始めた。 それまでは、著作をすることでしか、そうした発信方法はなかった。しかし、著作ができる人は限られるし、分野も限られる。たとえば、医者が音楽の本を書くなどということは、仮にその医者にそれだけの能力があったとしても、あり得ないことであった。最近、百田尚樹が音楽に関する本を出したが、彼が有名人だからこそなせるワザなのである。 HPはそうした”しばり”をなくした。誰もが、己が持っている知識、情報を平等に発信することが可能になった。その道の権威に素人が挑むことも可能になった。 また、内容の評価はHPの記述水準のみでなされた。とかくありがちな、”誰が”による発信重視(えらい人が書いた本はよく読まれる)ではなく、”何を”による発信が主体となった。 無名人であっても、それなりの内容があるHPを作れば、かなりに読まれることが可能だった。逆に、有名人発信であっても、内容のレベルが低ければ、たいして重視もされなかった。当時はまったくもって、内容重視のネット環境であった。 無名、あるいは専門外であっても、保持する知識、情報に自信があれば、それはかなり正当に評価されていたといってよいだろう。 HPは確かに玉石混交ではあった。本のように、編集者が介在しないし、公序良俗に反しない限り、誰もが何を語ろうが自由であったから、どうしても質の低い情報も出回ってしまう。 それでも、クリック一つで、百科事典と格闘するような調べ物ができる環境は、”受信者”にとってもきわめて有用であった。受信者には、手軽な検索ができる反面、玉と石を見分ける能力が要求されるようになった。 発信者の評価は、定量的には、アクセス数でなされていた。発信者に関わりなく、よい情報であれば、リンクも多く、アクセスも多い。これは、検索エンジンの思想でもあった。 なお、当時はまだ、発信者と受信者が分離していた。その意味で、書籍の延長的側面があった。無論、両者をつなぐデバイスもあった。掲示板である。両者はここで情報交換をしていた。 それでもおそらく、当時は、発信者が発信した情報への質疑応答的なことが掲示板の主流だった。少なくとも、発信者の権威は現在よりはかなり高かった。当時も掲示板荒らしのような存在はあったが、どうしてもの場合、掲示板のみ撤去し、HPの発信自体は続けることが可能であった。 だが、一定水準以上の知識、情報発信ができる個人はやはり限られており、その後、ネットの世界はあらぬ方向へと流れて行く。 ●ブログの登場 ネットにおけるパラダイムシフト第一弾は、2004年頃から普及したブログである。掲示板への投稿に飽き足らなくなった人たちが、これに飛びついた。これなら、HPよりも気軽に参加ができ、また掲示板主催者に気兼ねすることなく、自らの意思で発信できる。 ブログは、HPと比較して、”発信”よりは”交信”を目指したものと言える。すなわち、HPのような自らの薀蓄の披歴よりも、他者との交流に主眼を置くのである。 ブログの開始により、ネットへの情報発信が容易になったために、発信者は格段に増えた。しかし、誰もが発信をできるようになったがゆえに、さらには内容の充実よりも交信を重視したがゆえに、発信内容がどんどん貧弱になっていった。たとえば、今日食べた食べ物だの、見たことなど、はっきりいって他人にとってはどーでもいいような内容までが発信されるようになった。 こうなると、”誰が”発信するかよりも”何を”発信するかを重視したHPの良き特性が破壊されるようになった。 発信される内容がつまらないものばかりになると、結局のところ、失礼ながら、つまらない内容を発信しても読んでくれるような発信者が優位になる。 たとえば、無名のAさんが食べたものには誰も興味を抱かないが、羽生結弦くんが食べたものなら、多くの人は興味を持つことだろう。 こうして、残念ながら、ブログの登場によって、発信者による差別化がどんどん進むこととなり、有名人のブログとそうでない人のそれとでは、アクセス数に多大な差が生まれることとなった。 一般の人がブログを開設したところで、多くの人がそうしているのだから、お互いアクセス数が伸びるわけがない。読まれないからつまらないからやめる、ということになる。 結局、有名人の1人勝ち、という結果と相成ってしまった。 皮肉なことに、HPの参入障壁を下げたブログの発達が、逆に素人によるネットにおける発信の楽しみを大幅に奪い、発信者が白けてしまったことは間違いない。 また、ブログによる交信機能の重視は、皮肉にも逆にブロガー同士の交信を奪い、無名人→有名人という一方通行を生む結果となった。 ●さらにネットを破壊したツイッター 数年前から、ツィッターなるものが出現してきた。140字という短い字数で投稿ができるというのが売りであった。この程度の発信であれば、少なくとも母国語における発信なら、誰でもできるだろう。無論、内容は問わない。 空疎な内容であってもかまわないからどんどん短く発信してください、というわけだが、これがブログで明瞭になっていった有名人発信強化に拍車をかけることになった。 考えてもみてください。言葉が少なくなればなるほど、その内容が薄くなることは否めない。その結果、どういうことになるか。 結局は、”誰が”発信するか、に行き着くのである。そりゃそうでしょ。無名の人が何かつぶやいたところで、どうせ大した内容でもないわけだから、誰がそんなものを読もうとするか。 反して、有名人による発信ならば、あの人今度は何を言うのかな、と興味津々で見られることになる。 さらには、具体的なフォロワーの数が明らかになり、結局この数は、サイトの内容ではなく、サイト経営者の有名度に比例することになる。 たとえば橋下徹には100万人以上のフォロワーがいるが、一般人だと数人しかいない、とか。 これでは一般人はやる気がなくなって当たり前だろう。 結局のところ、ツィッターの普及によって、一般人はその発信力をますます奪われることになったのである。誰もが発信できるとして始まったHPは、20年を経ずして袋小路に入ってしまったと言えよう。 実は、ブログが普及していた頃、検索エンジンによる検索条件の中で、「ブログを除く」というものがあった。普通に検索すると、ブログばかりが出てくる。ブログでは個人的な感想のようなものばかりが書かれていて、必要な情報が得られない、とのことで、実は本当に検索をしたい人にとっては、ブログは邪魔だったのである。 ツィッターの普及はそうした検索の妨げ要因をさらに加速した。 私も当時、ブログは邪魔!、と感じた。だからこそ、HPにこだわった。時流に流されることなく、私が持っている知識を少しでも世に提供できたら、という思いで、かたくなにHPの形式を守ってきた。 | |
■平成27年12月2日 「社会問題ではなく”家庭”問題
結論を先に書きたい。小学低学年の暴力が増えてきているのだとしたら、その原因は間違いなくすべて家庭にある、と。この点は文科省の言うとおりだ。社会の問題ではない。
人間とはしょせんは動物である。幼い頃にきちんとしたしつけを受けていないと、あとから手がつけられなくなる。だから、幼時よりの家庭でのしつけこそが、あらゆる点における人間の基本原理となる。 幼児期までのしつけは家庭がほとんどだが、小学校に入学すれば、子供に対する影響は、学校での教育の方がメインになるだろう。ことに高学年になれば、1日の大半を学校で過ごすわけで、親よりも教師や友人の影響力が大きくなることは、多くの人が体験として理解できるだろう。 言い換えれば、小学低学年期においては、幼児期のしつけの影響が多大に現れることになる。だからこそ、暴力を振るうなどの問題児は、自閉症などの場合を除けば、家庭において作られるのである。 それでも、小学高学年くらいになれば、学校教育の成果も出てくる。家庭でいいかげんなしつけしか受けていなかった子供でも、学校教育である程度は矯正ができる。 逆に、小学校の間に友人などから悪影響を受け、”ワル”になっていく子もいるだろう。(昔はこっちがメインだった) こうした子供も無論、家庭内しつけの失敗がベースにあることが多いが、どちらかと言えば、学校環境からの影響の方が大きいだろう。(下図) 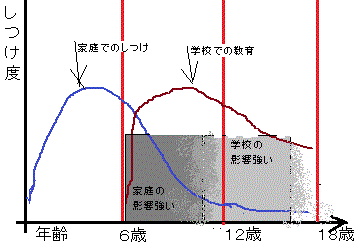 時代に関わらず、校内暴力のピークは中学生である。これは人間の発達心理学的に見るとだいたいこうなるのだろう。ある程度成熟すれば、逆に校内暴力は減ってくる。 結局、小学高学年~中学生の暴力はこれまで通り、人間の発育において必然的に一定数発生するものであり、主として学校教育の範囲において対処すべきであるが、小学低学年の暴力は、家庭環境が問題であるから、その是正が主眼にならなければいけないことになる。 したがって小学低学年の暴力の対策は、家庭環境の是正、につきる。ここを押さえないと、対策にならない。 この毎日新聞社説でもそうだが、どうしてもこの家庭の問題がぼかされがちになる。すなわち社会が悪いから、となる。 本来なら個人や家庭に帰すべき問題でも、マスコミなどからはとかく社会問題にされがちである。老人の貧困、生活保護、障害者問題etc。 こうして問題の焦点がぼけて、解決から遠のく。 社会が悪いから、と言えば、誰も責任を負う必要がなくなる。というか、みんな安倍が悪い、で済んでしまう。政治家をスケープゴートにして、マスコミは問題から逃げる。 無論、家庭問題の背景には確かに社会問題はある。正規雇用が減少して雇用者の平均所得が減少し、貧困が増える、お母さんも働かざるを得ない、子供に目がいかない、しつけがなおざり、といった連鎖は確かにある。 だが、どうもそんなことばかりがマスコミでは強調されがちである。 問題の核心はそこではない。暴力児童の家庭がどうなっているのかを冷静に分析し、共通の問題点などを見出し、家庭環境の具体的な改善を図らなければ、問題は解決しない。 そのためには、見たくないものも見なければ。男におぼれて子供をほったらかしのシングルマザー、DV,養育費の不払い、夫婦不和、毒親、離婚、虐待etc。家庭内のこうした問題に目を向けないと、小学低学年暴力の問題の解決には至らない。 マスコミは、問題を社会にすり変えるのではなく、正面から向かい合って欲しいと思う。こうした点で、この社説は不合格である。 | |
■平成27年12月2日 犯人はだいたい見当がつくが・・・
何か事件が起きたとき、犯人探しの基本は、その事件で一番得をするのは誰か、ということである。 人間は、相当危険なことをするのなら、相当の利益がなければやるわけがない。殺人にしても、平和な現代社会で、単なる気晴らしでやったなどというケースはきわめて稀なわけで、ほとんどの場合は、憎しみのあまりとか、多額の現金などが欲しい、などといった動機があるものである。 こうしてみていけば、果たして誰が米軍機や自衛隊にレーザーを当てているか、はだいたい推定できる。 こんなことをするのはまあ、”あっちの方”の人しかいないだろう。米軍や自衛隊が憎くてたまらない人たち。日本から原発をなくし、中国のいいなりになりたくてたまらない人たち。 当然警察も、犯人を挙げれば”あっちの方”の人たちには相当な打撃になるから、必死だろう。何せ、一部でもこのようなとんでもない犯罪者がいることがわかれば、”あっちの方”の人たちを十羽一からげで征伐できるから。 かつてのニューレフト退治がまさにそうだった。’60年安保頃までには結構国民の支持を得ていたニューレフトだったが、その後闘争が先鋭化し、凄惨なリンチなどが明るみに出たことによって、一気に国民の信頼を失っていった。 今もしも、レーザー照射の犯人が挙がれば、”あっちの方”の方々も、ニューレフト動揺、あっという間に一般国民の支持を失い、来年の参院選は、自公政権の圧勝になるだろう。自公政権としては、選挙直前に犯人を挙げたい? | |
■平成27年12月3日 「共産党アレルギー」ではない
自共共闘はやはり、マイナス面が強かった。自民候補が負けたのは、当然のことだ。
ただ、ここでどうしても指摘しておきたいことがある。それは、記事で使われている”共産党アレルギー”という言葉だ。 そもそもアレルギーとは? 通常では何でもないことが、一部の特異体質ないしは免疫上の後天的条件によっておこる過剰な反応である。要するに、”一部の”過剰な”がキーワードだ。 こうしてみると、”共産党アレルギー”という言葉の使い方がおかしいことがわかるだろう。なぜなら・・・ 共産党への反応は、「一部の人だけに起こる過剰なもの」ではないからだ。逆に、普通の感覚で生きている人ならばすべて一様に感じることが、共産党ではダメだ、ということなのである。 共産党を支持する人は、だいたい有権者の1割程度はいる。いいかえると、日本人の9割は共産党の主張には疑念を持っている。 これは、リベラルと言われる人たちも同様だろう。安倍保守政権はどうしても支持できないという人たち。こういう人たちの多くはしかし、共産党は支持しない。 共産党は、いかにうまく言い繕っているとはいえ、よくよく見てみると、本来の主張は変えていない。たとえば、安保や自衛隊に関しては、必ず”当面は”とかいう留保がつく。あるいは、最低限の維持程度のもので、要は「いやだけど国民がバカだからやむを得ず天皇制や安保、自衛隊はとりあえず維持してやる」という上から目線なのである。 さらに、社会体制に関しては、あくまでも将来は社会主義、共産主義を目指すと言う姿勢である。実際、11月19日付読売新聞のインタビューにおいて、志位委員長は、「社会主義・共産主義を目指す綱領を変える可能性はない」と言い切っている。 1991年にソ連が崩壊した時、当時の不破哲三委員長は、あれはスターリン以降のソ連が悪かったのであり、すなわち運用がまずかったのであり、社会主義自体の誤りではない」と言い切った。共産党は、以前のトップの発言は絶対に覆さないから、この思想は今でも共産党では生きている。 こうした政党なのであるから、日本人が健全である限り、その不支持者は常に9割に達しているわけである。したがって、共産党を支持しない人が大多数である以上、「共産党アレルギー」はあり得ない、という結論となる。 共産党は、一部の人だけに起こる過激な反応、ではなく、多くの人に普遍的に起こる正常な反応、を引き起こすのである。それが共産党への拒否反応である。 | |
■平成27年12月4日 情には情で?
いよいよ政府と沖縄県の法廷闘争となった。 純法律的には、沖縄県の勝ち目はまったくないらしい。だから、政府が理を通しているのに対して、沖縄県側は情で押し通そうとする。 理で追えば、沖縄県側の行動は矛盾だらけである。 ・辺野古の地元である名護市長は、キャンプハンセンの返還延長を申し入れていた→基地ができることに反対なのになぜ基地が戻ってくることに反対なのか? ・那覇空港拡張工事には何も言わない翁長知事→こちらも辺野古と条件が同じで、ジュゴンやサンゴ礁に影響があると言われ、瑕疵だってあるかもしれないのに、こちらには何も言わない。 ・那覇軍港への浦添市への移転には何も言わない ・本来の問題の基点であるはずの普天間基地への言及がまったくない ・自然破壊の極致であろう泡瀬干潟を進めているのがサヨクである ざっと以上のような矛盾がある。翁長知事の反対理由の大きな柱として、自然破壊があるのだから、知事は上記の事柄をわかりやすく説明する義務があるのだが、無視。 問題なのは、この毎日新聞社説のように、知事の言動の矛盾を突くどころか、知事と一緒になって国家を攻撃しようとするバカマスコミである。権力への批判さえしていればよいという、固陋な考えが新聞社上層部を支配しているからだろう。 だが、政府=悪、かわいそうな沖縄民衆=善などという、昭和時代の公害訴訟構図はもはや成り立たない。むしろ平成になると、民衆の側のエゴが目立つようになってきた。 マスコミはやはり、一方的に政府攻撃ばかりするのではなく、民衆側にある矛盾もまたきちんと報道しなければいけない。 私のimpressionであるが、安保法案反対以降、朝日よりむしろ、毎日や東京新聞の方が左っぽくなってきているように思う。何か取り違えているのだろうか。 翁長知事が情で訴えてくるのであれば、マスコミはやはり、賛否はさておいて、理においていったん受け止めなければならない。情をそのまま情として受け取って流して、では、無意味な存在である。 | |
■平成27年12月4日 2種類のヒューマンエラーを混同するな
●人は間違える
ヒューマンエラーとは、二種類に分けられる。これが大事。 ①人間なら誰しもが犯しうるエラー ②適性がない人間のみが犯すエラー 一般的な意味でのヒューマンエラーとは①である。つまり、通常の注意力を持っている人間が、ある一定の確率で犯しうるエラーである。 おそらくはどんなにすぐれた能力を持っている人であっても、ヒューマンエラーをただの一度も犯したことがない、という人はいないだろう。そんな人はそもそも人間ではない。化け物だ。 ●ヒューマンエラーを重視する欧米 人は誰もがミスをする。欧米では、こうした思想が古くからあった。したがってシステムを組むときには、相当なバカでも扱えるよう単純化する。社会全体が、ヒューマンエラーがあることを前提としているのだ。 たとえば大東亜戦争時、日本はベテランパイロットではないと扱えないゼロ戦を作ったが、米国は未熟パイロットでも扱えるグラマンを作った。当初はゼロ戦優位だったが、後半、ベテランパイロットが枯渇するとあっという間に日本の優位性が薄れた。物量の問題を除いても、危機管理思想の差において、日本は負けていた。 さらに、事故事件が起きた場合は、”who”よりも”how,why”を重視するのが欧米である。捜査は調査の下僕である。ロッキード事件の時にも、米国は証言者を刑事的に免責にして証言を引き出している。whoを重視する日本には、刑事訴訟法上、このような規定はない。 また、2000年にオーストリアで起きた大規模火災事故においては、結局スタッフは無罪とされたが、執拗にその刑事責任を負ったのは日本人だけで、欧米人は、当初より民事裁判を主眼にしていたとされる。彼らには"who”の発想はあまりなく、そもそも刑法において過失刑事責任を追及する原則がない。 このように欧米では、人は間違うもの、という意識が徹底され、だから間違った人は原則として処罰されないのである。 日本人はなかなかこういう発想ができない。病院でも、”How”の発想から、「ひやりはっと報告」を提出させているところが多いが、当事者にきちんとした自覚がないとどうしても”who"的土壌から個人責任への追及になりがちとなってしまい、本来の機能なかなか果たせない。 ●JR西はヒューマンエラーを混同 さて、JR西も、欧米的発想へ転換したわけで、それは危機管理において一歩前進として評価はできるが、どうも上記2種類のヒューマンエラーを同社が混同しているようであることが気になる。 正しい危機管理はまず、①と②のヒューマンエラーをきちんと峻別することである。そして、①のエラーに関しては、上記記事のごとく、懲罰的教育をやめることは正しいが、②のエラーに関しては、むしろ発想の大胆な転換が必要である。 脱線事故を起こした高見運転士は、私の分類でいえば、②のヒューマンエラーの典型例であった。それまでにもオーバーランを何度も繰り返しており、素人目で見ても、明らかに運転士としての適性を欠いていた。そして、こうしたエラーを犯す人物に対しては逆に、非懲罰的姿勢は危険なのである。 JR西も、本能的にその危険性は認識していた。だからこそ、懲罰的教育(日勤教育)を行っていたのである。 だが、本来、職業不適性は、教育訓練では是正はできない、という原則をJR西は忘れていた。適性のない人間は、いかに訓練したところで、必要なレベルには達しない。だから、②のヒューマンエラーに対する正しい対処法は、懲罰的教育ではなく、本人に引導を渡すことである。 ここにもう一つの日本人の欠陥が見える。すなわち、不適性な人間でも意欲があれば受け入れてしまうという情である。 やればできる。あいつはあんなに頑張っているんだから、もう少し見守ってやろう JR西の脱線事故は、実は一般に言われているような厳しすぎる日勤教育というよりは、こうした情による甘すぎる管理職の姿勢が原因だった。 JR西はしたがって、①と②のヒューマンエラーを峻別することが大事で、①のタイプのエラーの対処法はこれで一歩前進として評価できるが、②に関しては、このままではまずい。 飲酒運転がどーとかでごまかしているが、不適性とは、そのような道徳的レベルではなく、もっとシビアなものである。情に流されずに、厳しい適性評価を行い、明らかに不適性の者は退場させる勇気が、管理職には求められる。 私たち医療の世界でも、やはり適性評価に関しては米国が一歩先んじていると感じる。手術などでも、より適性のある少数の医師が数多く手がける傾向にある。 ノーベル賞の山中先生は、たとえば、普通なら10分程度でできる背部粉瘤切除に1時間以上もかかり、「ジャマ中」などと呼ばれていたという。失礼ながら、山中先生には明らかに外科手術の適性はなかった。しかし彼は、研究者という天分があって成功した。 もしも山中先生の上司が、いつまでも彼を手術に駆り出していたら、ノーベル賞研究者は三流の外科医で終わっていたことだろう。 JR西の脱線事故にしても、上司が高見運転士の適性をシビアに評価し、彼を別の仕事に廻していれば、あのような事故は起こらなかった。 その後この事故では、世間の関心は、いかにも日本的な、トップの個人責任追及や、JR西の日勤教育の現状の評価へと傾き、その本質が議論されることがなかったのは残念であった。 JR西の今回の方針は、そうした世間からの評価を考慮してのものではあろうが、もしもJR西が、①と②のヒューマンエラーを混同したままで、②のタイプのエラーをする人にも非懲罰的姿勢になっていくとしたら、それは非常に危険であるといえよう。 |
