愛子さまが不規則登校で転校計画浮上説 受験見据えた人事も
Newspostseven 2014.10.31
爽やかな秋晴れの空が広がった10月27日。この朝も、愛子さまが定刻通りに通学されることはなかった…。
「この日、愛子さまが登校されたのは午後1時頃です。大幅に遅刻されているのに、急ぐそぶりもなく、足取りも重く、夏服にマスク姿でのご登校でした」(皇室記者)
一学期後半から始まった愛子さまの“不規則登校”。二学期の始業式こそ、定刻前に元気に登校されたものの、その後は再び逆戻りされていた。
「9月末には一日の授業が終わる直前の午後2時過ぎに登校されたこともありました。
10月15日には二学期の中間テストが行われましたが、愛子さまは中間テストを欠席されています。一学期の期末テストも休まれているだけに、続けてのテスト欠席となりました」(学習院関係者)
10月24日にも欠席されており、遅刻もさることながら、このところは欠席も目立つようになってきている。
そんななか、『週刊文春』(10月30日号)は、愛子さまがおひとりだけの“特別授業”を受けている、またそのことを耳にされた美智子さまが胸を痛められ、心配されていると報じた。
こうした緊迫した状況下、東宮職周辺からはこんな声が聞こえてくる。かつて本誌は、雅子さまが、将来、愛子さまに学習院大学ではなく、東京大学やご自身が卒業されたハーバード大学に進学されることを望まれていると報じたことがあったが、今そのお気持ちに変化が…。
「雅子さまは愛子さまが“不規則登校”状態に陥ってしまったのは学習院側にも責任があるとお考えのようです。皇太子ご夫妻は“愛子さまを特別扱いしないで欲しい”と学習院側に希望されていました。しかし、女子中等科に入学されてから、“特別扱い”が目に余るようになったんです。
これによって、愛子さまと同級生との間に距離ができてしまったため、雅子さまの学習院への不信感が膨らんでいったようです。そこで雅子さまは現在の状況を打破されるために、大学進学を待たずに前倒しして高校受験をして、学習院以外の高校へ転校させる計画をお考えなのです」(東宮職関係者)
この受験計画を裏付けるように、10月16日にはこんな人事が宮内庁から発表された。宮内庁は御用掛として名門高校の元数学教師・大橋志津江さんを採用した。
「彼女は文科省の中央教育審議会の部会で算数・数学専門部会委員を務めた数学のエキスパートです。勉強がお得意な愛子さまですが、唯一数学が苦手なんです。そこで苦手克服のために、雅子さまが彼女を呼ばれたみたいなんです。しかも彼女は都立戸山高校在任中には、進路指導主任も経験していますから、雅子さまにとっても愛子さまにとっても将来を考える上で本当に頼りになる人物だと思いますよ」(前出・東宮職関係者)
※女性セブン2014年11月13日号
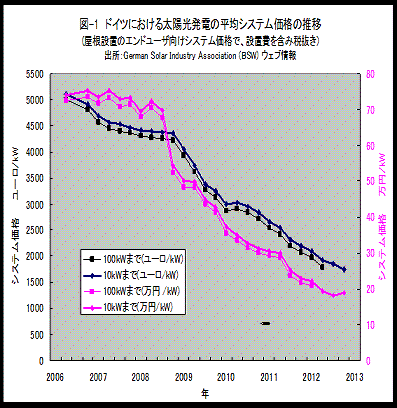
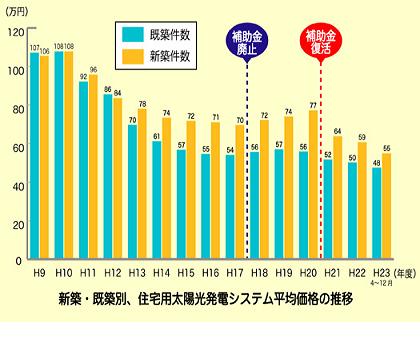
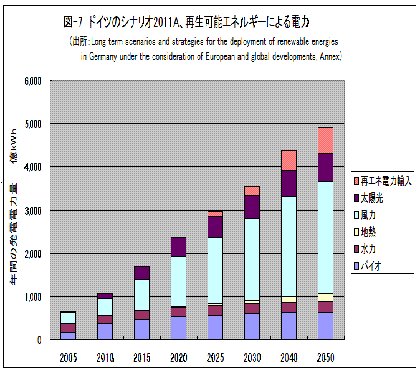
標高が高い場所に水をくみ上げることで余った電気を実質的にためることができる「揚水発電所」の設備利用率は昨年度、全国で3%にとどまり、太陽光発電などの再生可能エネルギーが余ったときに蓄電する受け皿としてはほとんど活用されていないことが、経済産業省の集計で1日、分かった。
九州電力など電力5社は再生エネの供給が増え過ぎて需給バランスが崩れる恐れがあるなどとして、新規受け入れを中断している。経産省は揚水発電を最大限活用すれば、再生エネの受け入れ可能量が増えるとみており、5社に試算の提出を求める。
変動の大きい再生エネの出力を平準化するために揚水発電を利用するというのは、実際ヨーロッパでは行われており、再生エネの利用のためには、必要欠くべからざるものである。
たとえば風力発電の割合が高いデンマークは、その電力を水力発電所が多いノルウェーやスウェーデンへ売電し、両国より水力発電や原発によって作られた安定した電力を買電している。
ノルウェーやスウェーデンでは、買電した不安定な再生エネによる電力を使って、自国の揚水発電所を動かし、蓄電しているわけである。
揚水発電の効率は一般的に約7割と言われているので、これを動かして蓄電するためには、輸入価格が安くなければならない。要するに、再生エネで作られた不安定電力は、市価において買いたたかれているわけである。
それでもデンマークが風力発電を続けているのは、この国がこの三国においては一番のその適地だからである。
デンマークは最高標高173m、ほぼ平坦な国である。風はほぼ一定方向で一定量吹いている。おそらくは、世界でも有数の風力発電適地。
ノルウェーは逆に、山や川が多く、落差も大きく、こちらは水力発電適地。だから発電構成の99%が水力発電である。
スウェーデンは、ノルウェーほどの水力適地でもなく、デンマークほどの風力適地でもない。いったんは国民投票で脱原発を決めたが、結局原発なしでは火力頼みとなってしまい、原発を続けている。現在、発電構成の半分近くは原発。
つまり、スウェーデンは原発+水力、ノルウェーは水力、デンマークは風力(実際は火力が一番)、というように、この三国において、リカードの言う貿易の比較優位の原則が成り立っているのである。
風力発電は原発、水力と比べると比較的に高コストではあるが、適地生産することにより、コスト高によるマイナスを少しでも補っているといえる。(それでも、デンマークの家庭用電気料金は世界一高いので、この国は風力発電を推進することにより、かなり割を食っていることになる)
つまり、再生エネ推進のための揚水発電所利用は、あくまでも比較優位の原則を利用して初めてある程度は経済的にペイするのであり、一国でこれを同時に行うことは、まったく経済性がない、ということである。
こう考えると、日本において、いくら揚水発電所の利用率を高めても、再生エネを推進させることはできない、ということがあきらかであろう。
一国の経済で揚水発電と再生エネが同時に成立するためには、つまりは再生エネを安定化させるためには、3割のロスを補うために、通常発電以上の効率化が必要となるわけであり、たとえば発電コスト5〜6円/kWhなどといったレベルにならないと、それは困難であろう。