![]() K49 ミサブレビス
K49 ミサブレビス
楽譜へのリンク
概要
「The complete Mozart」によればこの曲がどのような機会に演奏されたかは定かではないとのことだが、カルル・ドニの「モーツァルトの宗教音楽」によれば、この曲はK139が演奏されたウィーンの孤児院の聖堂の献堂式の直前の12月3日の聖フランシス・
ザビエルの祝日に演奏される予定であったという。ただし実際に演奏されたかどうかは私の調べた限りではよくわからなかった。
この曲の特徴はミサブレビスであるにもかかわらず、Et
in
Spiritum〜以下でバスの長大なソロが入っていることである。これは当時モーツァルト周辺にヨハンナ・ネポムツェーネというバスを歌う女性歌手!がいたために、何としてもこの歌手を起用したかったためにミサブレビスとしては例外的に組み込まれたものであるとのことである。(カルル・ドニ「モーツァルトの宗教音楽」p27より)形式はミサブレビスの形を取りながらもなんとかこの女性のバス歌手をどこかで長々と歌わせたいというモーツァルトの苦心のあとがうかがえるものである。
各論
1キリエ K49はト長調なのでキリエも明るく始まる。最初にやはり短い序唱がつき、三拍子の速い合唱となる。ここの部分の特徴は![]() という飛び跳ねるようなリズムである。これがためにこのキリエはト長調という調性と相俟って非常に明るくのびやかな曲となっている。Kyrie
EleisonとChriste
eleisonは交互に現れ、特に式文に忠実にはなっていない。このキリエは特定のリズムで統一されているために非常にまとまりのよい感じを受ける。
という飛び跳ねるようなリズムである。これがためにこのキリエはト長調という調性と相俟って非常に明るくのびやかな曲となっている。Kyrie
EleisonとChriste
eleisonは交互に現れ、特に式文に忠実にはなっていない。このキリエは特定のリズムで統一されているために非常にまとまりのよい感じを受ける。
2グロリア
ミサブレビスであるので、イッキに進んでいくが、変化をつけるために曲の構成はTutti→Solo→Tutti→Solo quartet→Tutti→Solo quartet→Tutti→Solo→Tutti(フーガ)という具合になっている。この構成は区切り方やソロと合唱のあてはめ方などからしてもそれぞれの部分を拡張すればそのままカンタータ形式になるようなきっちりとしたものである。最後のフーガは短いながらもヘンデルのオラトリオを想起させるような雰囲気を持っている。
3クレド
このクレドはミサブレビスとしては異様に長い。(通常はGloriaより幾分長い程度だが、このミサ曲においては、Gloriaの倍以上の長さである) そして前述のようにミサブレビスとしては異例のバスの長いアリアが入っているのが特徴である。またこのバスアリアを引き立たせるためか、この曲ではグロリアとは異なり合唱が中心であり、ソロは他には二箇所で短く現れるだけである。
曲はおおむねホモフォニックに進んでいく。descendit de coeliは定型どおり下降音型となるが、そのあとのEt incarnatus〜homo factus estまでの合唱とオーケストラではバスパートが消える。ここの部分の歌詞は「精霊によりて乙女マリアより肉体を受け、人となりたまえり」であるから、これはモーァルトがソプラノ、アルト、テノールの三声を三位一体説に見たてて書いたことはまちがいない。
続くCrucifix〜は通常短調に転調したりするものだが、ここではハ長調のまま突っ込む。そのために「十字架にかけられ」るのも何となく明るすぎる気がするが、そこは12歳とはいえ天才であるモーツァルトのこと、ぬかりはない。
続くpassus,et sepultus estのところはを各パートをバスラメント風の下降音型になっている。(下譜参照)これによりこのクレドにおけるキリストの受難の記述は十分に音楽的にも裏打ちされ、次のEt resurrext
terra die以下が際立つことになる。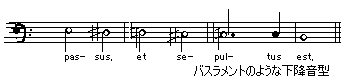
次のet ascendit in caelum,sedet ad dexteram Patris(旋律①とする。なお、この旋律はテキストの意味にあわせて上昇音型となっている)とet iterum venturus est cum Gloria(旋律②とする).の部分は対になって作られている。この両者の旋律を見てみると下譜のようにほとんど同じで、旋律②は旋律①を半分に短縮して始まっていることがわかる。
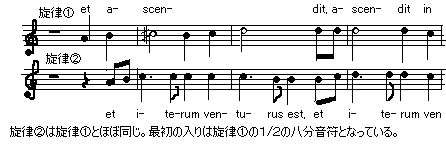
こうした主題の処理は後にベートーベンがよくやった手法で、モーツァルトはそれを先取りしているといえよう。ただここで不思議なのはクレドのテキストの次の段落に含まれるjudicareがこのフレーズの終わりに来ていることである。
このあとvivos et mortuosがAdagioとなり、続くcujus regini non erit finisが再度Allegro となっていよいよバスアリアとなる。通常モーツァルトの時代のミサ曲ではこのnonは何度も繰り返されることが多いが、このK49ではあっさり一回で終わっている。
このバスのアリアは通常のバスアリアに比べ、非常にまろやかな曲である。おそらくこの曲が作られるきっかけとなった女声バス歌手であるヨハンナ・ネポムツェーネの声が男声バス歌手では出せないようなまろやかさを持っていたのであろう。歌手の声に合わせた曲を作るモーツァルトの天才には敬服するばかりである。したがってこの曲をモーツァルトの意図通りに演奏するのは非常に困難であるといえよう。あまり張り上げて歌ってはいけないのである。ボーイソプラノをそのままバスにしたような声の持ち主(こんなバス歌手もあまりいないだろうが)にぜひ歌ってもらいたいものである。
さて次のEt unam sanctam catholicam(旋律③とする)〜とin remissionem(旋律④とする)のところはまた前述の旋律①と旋律②の関係のように対になっている。(ただしここではソプラノだけ) 今度はやや複雑で、旋律③は二つの旋律に分割されているが、この二つの部分が旋律④においては一つにまとめて現れるである。(下譜参照) こうした主題の処理のやり方は、テキストが長くてともすれば冗漫となりがちであるクレドを特定の主題を用いて関連のあるテキスト同士をまとめるという目的でなされていると思われる。
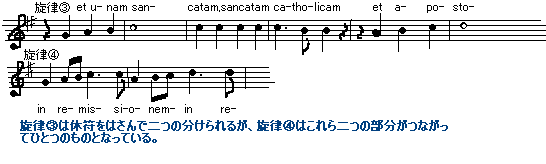
続いてAdagioとAllegroが交互にそれぞれのテキストにあわせて現れ、最後のフーガとなる。
et vitam
venturi Amenは伝統にのっとったフーガである。このフーガの主題の特徴はへクサコードになっていることである。(下譜参照)へクサコードというのは教会旋法が確立する以前より存在していた古い概念で、近代では音程というものを普通はオクターブ単位で考える(したがって8つの音の単位となる)のであるが、そうでなく、ド―ラのように6つの音の単位で考えるものである。(ヘクサはギリシャ語で6を表す) モーツァルトがヘクサコードをそのままなぞったような比較的単純な上昇音型をここで使用したのはどういう意味があるかはよくわからないが、テキストの意味は「来世の命を望む」であるから、K49としてはキリストの復活を記念してのことであろうと思われる。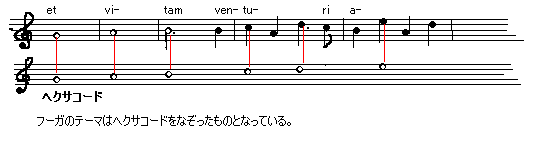
4サンクトゥス
Sanctus Dominus Deus Sabaoth Pleni sunt caeli et terra gloria tuaは特記すべきことはないが、Hosanna
in excelsis Deoではやはり主題にヘクサコードが使われており、さらにこれに対旋律として半音を単純に上下する旋律が絡み付いて簡単なフガート(フーガの小規模なもの)を作っており、何となく古風な感じを受ける次第である。(下譜参照)そして後半は完璧に古典派(モーツァルト時代では時代の最先端)の和声であり、Gdur,Ddurの和声に突然Emollのコードがフォルテで出現し、そのコントラストの妙は実にすばらしい。
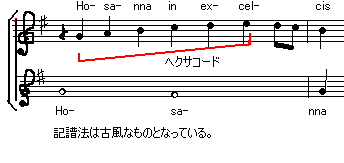
5アニュスデイ
ここはだいたい伝統にのっとって書かれており、あまり特記すべきことはない。Dona nobis pacemに入ると長調に転調し、リズムも三拍子となり、モーツァルトらしい明るい雰囲気にもどって、最後はアーメン終止で曲を終える。この部分を聴くとモーツァルトは完全に前時代のバロック期の音楽からは抜け出している、ということがよくわかる。
まとめ
このK49を聴いているとモーツァルトは自らの力量を示すために、本当はK139に引き続いてこの時点でもう一曲ミサソレムニスを書こうとしていたのではないかと思ってしまう。カンタータ形式をそのまま縮小したようなグロリアや、バスソロを伴った、ミサブレビスとしては大規模なクレドなどが、簡単に書かれたキリエ、サンクトゥス、アニュスデイに比べると突出しているのがその理由である。初演されるべき礼拝が通常のものでそれができなかったのではないのだろうか。
![]()