| K317 戴冠式ミサ |
| ようこそDr.町田のホームページへ モーツァルトの教会音楽のページへ |
楽譜へのリンク 概要 このミサ曲は従来1779年3月にザルツブルク近郊のマリア・クライン教会というところに聖母像の戴冠が行われる際に演奏するために書かれたとされてきたが(そのために「戴冠式」のニックネームがある)ザルツブルク大聖堂での復活祭のためのものとも言われている。またこのミサ曲の楽器構成に当時のザルツブルク大聖堂のオーケストラにはなかったホルンが含まれていることからまた別の機会のためとの説もあり、結局なんのために作曲されたか正確なところはわからないようである。 このK317はおそらくモーツァルトの書いたミサ曲の中ではもっとも有名なものであろう。有名なだけに確かに名曲である。グロリアとクレドがカンタータ形式でないので一応はミサブレビスなのであろうが全体の演奏時間は30分ほどかかるのでミサブレビスとミサソレムニスの中間くらいの規模の曲である。 このミサ曲を書いた時にモーツァルトはまだ弱冠23歳であるが、すでに大家の領域に達し、その筆は練達のものである。K139のような初期の名曲を除き、それまでのミサ曲とは別格という感じを受ける。このミサ曲では厳格なフーガはまったく使われておらず、イタリア的な明るく親しみやすい旋律が多数現われる。こうしたミサ曲らしからぬ親しみ易さがこの曲をポピュラーなものとした要因といえようか。それにしてもこのミサ曲では各楽章すべてがハ長調であるのに聴いていてまったく飽きがこないのは不思議である。 <”雀のミサ”との類似点> このミサ曲は、以下の点において、”雀のミサK220"との類似点がある。 ①ともにハ長調である ②Kyrieに対して、ミサ曲らしからぬ非常に明るい旋律が使われている ③Kyrieの主題が、Dona nobis pacemで回帰されて再び出てくる ④Kyrieの主題が、カノン的な組み合わせになっている。 ④について。K317において、Kyrieの以下の主題は最初はオーボエがカノン的に繰り返し、合唱では相互に繰り返される。  K220では、以下のソプラノによるKyrieの主題は、必ず五度ずれたバスがくっついている。 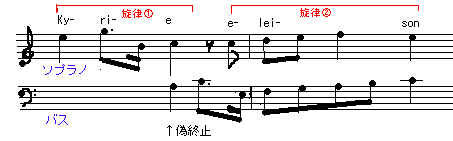 なお、これらのKyrieの主題がいずれも、Dona nobis pacemで回帰されるのである。 各論 1キリエ キリエは合唱→ソロカルテット→合唱という構成をとる。最初の緩徐な合唱のあとに大変魅力的な旋律をソプラノソロが歌い始める。単純ではあるが一度聴いたら忘れられないような旋律である。(下譜参照)  その和音構造から当然カノンのような形を取り、オーボエがソロを追いかけていく。この部分ではKyrie eleisonが長調で、Christe eleisonが短調でという風に書き分けられている。(通常はモーツァルトはこの二種類の歌詞は書き分けてはいない) この長調→短調→長調という転調(特にハ短調からハ長調への転調)が絶妙である。  このあとに再度合唱が入ってキリエを終わる。なお最後の短い後奏ではソプラノソロの旋律と合唱部の伴奏が同時になごり惜しむように入るのが印象的である。 2グロリア グロリアはおおざっぱに三部形式でできている。最初の主題の特徴はヘミオラである。ヘミオラというのはリズムを意識的にずらして曲を一時的に別の拍子のように変えてしまうことである。すなわちこのグロリアは三拍子の曲なのであるが、最初の入りはしばらく四拍子のようになるのである。(下譜参照。なおこの手のヘミオラはK65のミサ曲のサンクトゥスでもみられる)  この最初のテーマは、合唱とオーケストラが一体となって、形成してされている。すなわち、上譜のヘミオラの4小節でもって、一つのテーマとなっている。モーツァルトの宗教曲には、合唱がメインの曲、オーケストラが強い曲があるが、この曲はその中間的なもの、と言えようか。次のbonae voluntatisの部分では逆に、オーケストラ→合唱という掛け合いとなる。  ↑オーケストラからソプラノへと旋律が移る。 このあとから弦楽器ユニゾンによる Domine Deusよりソロが出てくる。この部分ではキリエと同様、イタリア的な陽気な旋律をソロカルテットが歌っているのも印象深い。(下譜)  Qui tollis peccata mundiからは短調系となる。ここからしばらくはテキストが悲しくなるのでどんなミサ曲でもここからは短調となるのが普通であるが、このK317では短調にはなるが、テンポはずっと変わらずに速いままである。 この部分は、グロリアのテキストにおいては、連祷のようになっている。 Qui tollis peccata mundi, misrere nobis.(世の罪を除きたもう主よ→我らをあわれみ給え) Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.(世の罪を除きたもう主よ→我らの願いを聞き入れたまえ) Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.(父の右に座したもう主よ→我らをあわれみ給え) 興味深いことに、モーツァルトはこの部分を調性を変えて、同じパターンを3回くりかえしている。この部分において、問いかけ部分は問いかけ部分で、応答部分は応答部分で、ほぼ同じ主題を繰り返す。モーツァルトは音楽を使って、擬似連祷を行っているのだ。しかもこの間の転調の見事さといったら! 短調系が終わると、またもや例の付点パターンが出現し、Quoniam tu solusの部分に入る。ここでまた、最初のGloriaのテーマが出現し、Amenへと突入する。最後の部分で、合唱が以下のように歌い、これまで度々出現してきた 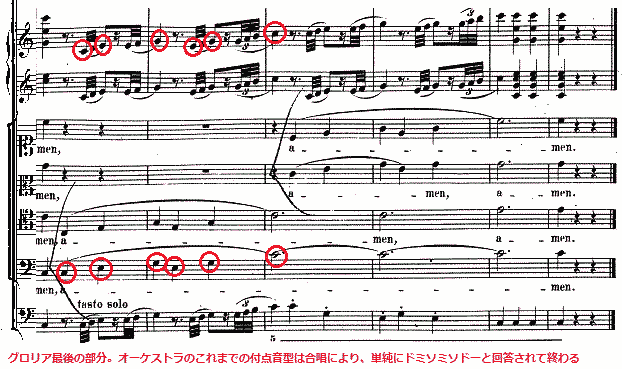 3クレド この楽章の入りもまた独特である。すなわち合唱はドの音の斉唱で入ってくるのである。伴奏がなければお経を読んでいるように聞こえるだろう。(そこでここではこの音型を「お経音型」と名付ける)  この部分のオーケストラと同じく、主としてオーボエが次のような旋律を奏でている。  したがって、クレドにおいては、メロディーはオーケストラが担当し、合唱はむしろお経音型を唱えることにより、脇役になっているわけである。このミサ曲はどちらかというと声楽がメインなのであるが、このクレドは例外で、K339のように、声楽とオーケストラが対決しており、どちらかというと、オーケストラが強い楽章であると言えよう。 こうしたお経音型はきわめて珍しく、こうした痛快な発想はこれまでのモーツァルトのミサ曲にはなく、この曲独自のものである。この”お経音型”はその後もクレドにおいてはたびたび現われ、曲全体の統一に一役買っている。 さらに第19小節のDominum Jesumのところでは,当時としてはきわめて大胆な不協和音が使われている。なんとバスとテノールがミとファで短九度となってまるまる一小節歌うのである。特にこの小節の第1拍ではソプラノからバスまで順にミ-ラ-ファ-ミという強烈な不協和音となっている。 ここの和音は本来はニ短調なのであるが、バスが係留されてミの音を出し続け、なおかつソプラノも係留されてミの音を出し続けるという二重の係留音となっているのである。(下譜参照) 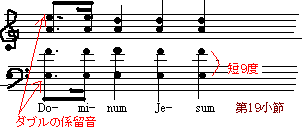 バスだけが係留されてオルガンポイントを形成することによって不協和音となることはよくあることであるが、こうした2パート同時の係留はめずらしいものである。(K276のRegina Coeliでも見られる) なお、descendit(下りる)のところが下降音型の繰り返しになっていることにも注目したい。単純といえば単純な技法で、すでにバッハの時代から頻繁にやられていたものではあるが、何といっても、ただ聴いていてもすぐにわかるように作られているのはさすがモーツァルトという感じがする。(下譜) 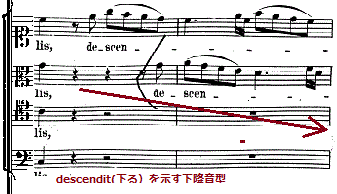 Genium,non factumより、クレドの最初の主題が繰り返され、Et incarnatus est より型通り緩徐楽章となる。この部分は他のミサ曲同様ゆっくりとした短調となる。オーケストラでは、弱音器付きの弦の下降音型が特徴的である。緩徐部分ではほぼ常にこの音型が合唱を縛っており、これが言わば、ライトモチーフとなっている。 Et resurrexitからは3度目のお経音型が始まるが、次に、実に不思議なことが起こる。すなわち、ascendit(上る)という歌詞に対して、descenditと同じ下降音型がつけられているのである。無論、descenditのところのように何回も繰り返されることはなく、ただの一回だけなのだが、本来なら上昇音型にすべきところが、なぜ下降音型となっているのか、理由はよくわからない。  この後は概ねCredoの最初の部分を再度なぞっていくが、最終的にFdurで終止し、et in Spiritumからは曲想ががらっと変わる。ソロカルテットとなり、弦がピチカートとなる。ここの転調はきわめて印象的である。その後、Et unam sanctamから4度目のお経音型が出現するが、ここでは合唱全体のユニゾンではなく、もともとの合唱部分はソプラノとテノールが担当し、アルトとバスはオーケストラの音型を歌うことになり、二部合唱となる。この効果はすでにK243のリタニアなどで実証済みである。一般に混声四部合唱がこうした形になると非常に力強く感じられるものである。またこの4回目では、ティンパニーとトランペットの音型も前3回より派手になっている。  その後、Et exspecto resurrectionem mortuorum.の部分はDominum Jesumの部分同様、調性を変えて二重係留音となる。 Et vitam以降は通常はフーガとなるが、このミサ曲においては、Gloria同様、フーガは使われず、そのままAmenになだれ込む。descenditとまったく同じ音型が出現するが、特に深い意味はないと思われる。 そして特筆すべきがこの繰り返されるAmen群に混じって最後に冒頭の「Credo in unum Deum」が再度ここで現われることである。  これまでのモーツァルトのミサ曲の中でもクレドの冒頭主題が最後に現われることはあった(K139など)が、言葉が回顧されることはなかった。私はこれこそがモーツァルトの信仰告白であると思う。ここで再度「我は唯一の神を信ず」の一言を繰り返すことによってモーツァルトはさりげなく自分の信仰を確認したのであろう。モーツァルトはあんまり信仰がなかったなどとよく言われるが、信仰がなければこうした芸当はできないと思う。 サンクトゥス この楽章でおもしろいのはBenedictusにおいて通常は最後にあらわれるHosanna inexcelsisがBenedictusの歌われている途中でもいったん現われることである。あとはだいたい型どおりといえようか。 アニュスデイ Agnus Deiのテーマがフィガロの結婚の第三幕のdove sono i bei momentiとよく似ているのは有名である。これがためにモーツァルトのミサ曲全体が特に19世紀などでは「オペラ的すぎる」だの「教会音楽としては派手すぎ」だのといった批判を受けてきた。まあ本当にそっくりなんで、ここでちょっと聴き比べてみましょう。 K317 Agnus Dei フィガロの結婚より さてソプラノソロが延々と続いたあと、調性は忽然とCdurに戻り、キリエで現われたあの華麗な旋律が回帰され、 Dona nobis pacemを歌いだす。雀のミサなどでもこうしたが回帰されることはあったが、こちらの方がより大規模である。また、こうした回帰は後の「モツレク」の最後のCommunioでも見出される。むろんこれはモーツァルトではなく、ジュスマイヤーの手によるものだが、おそらくはモーツァルトのこうした回帰指示はあったものと思われる。 この回帰はソプラノ→テノール→ソプラノと受け継がれ、急に長調から短調になり、ソロカルテットとなる。そして、キリエの時と同様、短調は一瞬で終わり、すぐにまたCdurへ戻る。Kyrieと違うのは、バスとアルトのソロがくっついていることで、より和声が充実した形となっている。 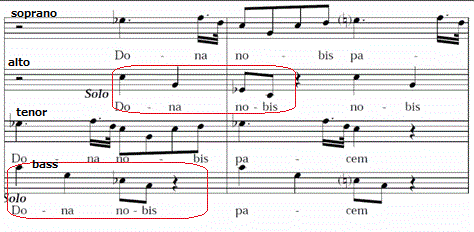 こちらにおいては、特に、キリエの時のような歌詞との対応は認めない。 最後はこの旋律はAllegroになって合唱で歌われ、新たな主題も加わり、合唱、ソロが入り混じっての大変感動的な終わりとなる。特に弦は最後はユニゾンとなり16分音符で細かく動く音型となる。声楽が強いこのミサ曲において、この部分は、Credoと並んで、オーケストラが自立している数少ない部分である。  |