妝晥傊偺儕儞僋丂
奣梫
丂偙偺俲俀俆俈偼丄埲壓偺揰偱丄摉帪偲偟偰偼偍偦傜偔攋揤峳側儈僒嬋偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅
嘆儗僔僞僥傿乕儃偺傛偆側僉儕僄偺崌彞偺擖傝
嘇僌儘儕傾偺儘儅儞攈晽偺擖傝丄
嘊CredoCredo偲壗搙傕孞傝曉偡僋儗僪
etc.
俲俀俆俈偼儌乕僣傽儖僩偺儈僒嬋偲偟偰偼柤嬋偲偼偄偊側偄偑丄斵偑偄傠偄傠側岺晇傪帋傒偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偦偆偟偨岺晇偼屻偺儈僒嬋傗僆儁儔側偳偱壴奐偔偺偱偁傞偑丄偙偺儈僒嬋偵偍偄偰偼傑偩偦偺偨傔偺夁搉婜揑抜奒偲偄偊傛偆丅
儌乕僣傽儖僩尋媶偺懽搇傾僀儞僔儏僞僀儞偼偙偺儈僒嬋傪乽儕乕僩儈僒乿偲屇傫偱偄傞丅僜儘傪娷傔偰暋嶨側僷僢僙乕僕偑側偔丄慡懱偑棳傟傞傛偆側傗偝偟偄暤埻婥傪帩偭偰偄傞偐傜偱偁傠偆丅側偍丄偙偺乽Lied乿偲偄偆僪僀僣岅偵偼乽俠倛倧倰倎倢乿偲偄偆堄枴傕偁傞偦偆偱偁傞丅偡側傢偪丄偙偺儈僒嬋偼昁偢偟傕扨慁棩偺壧嬋揑偲偄偆堄枴偩偗偱側偔丄僪僀僣僐儔乕儖偺桬憇側儂儌僼僅僯僢僋側僴乕儌僯乕揑枺椡傕偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅
丂偙偺儈僒嬋偼侾俈俈俇擭偺侾侾寧偵彂偐傟偰偄傞丅傎傏摨帪婜偵偼俲俀俆俉偺僔儏僷僂儖儈僒偑彂偐傟偰偄傞丅乽戝僋儗僪儈僒乿偲偄偆偁偩柤偑偮偄偰偄傞強埲偼偄偆傑偱傕側偔丄偙偺儈僒嬋偺僋儗僪偑旕忢偵摿挜揑偱偁傞偐傜偱偁傞丅
乽戝乿偑偁傞偐傜偵偼乽彫乿傕柍榑偁傞丅俲侾俋俀偑偦傟偱偁傞丅偙偺儈僒嬋傕傑偨僋儗僪偵偍偄偰乽Credo乿偑壗搙傕孞傝曉偝傟偰偍傝丄俲俀俆俈傛傝婯柾偑彫偝偄偺偱乽彫僋儗僪儈僒乿偲屇偽傟偰偄傞丅屄恖揑偵偼俲俀俆俈偺乽戝僋儗僪儈僒乿傛傝偼俲侾俋俀偺乽彫僋儗僪儈僒乿偺曽偑偼傞偐偵弌棃偑椙偄偲巚偆偟丄岲偒偱偁傞偑丄偙偙偱偼俲俀俆俈偺偍偼側偟丅
奺榑
侾僉儕僄
丂慜弎偺傛偆偵丄慜憈偵懕偄偰崌彞偑儗僔僞僥傿乕儃偺傛偆側宍偱擖偭偰偔傞偺偑旕忢偵報徾揑偱偁傞丅偡側傢偪榓惡妛偱偄偆僯挿挷偺榓壒偺戞堦揮夞宍偱擖偭偰偔傞偺偱偁傞丅乮僯挿挷偺摫壒偱偁傞僼傽侐偺壒偑僶僗偵棃偰偄傞乯丂偍偦傜偔偙傟傑偱偙傫側儈僒嬋偼側偐偭偨偺偱偼側偄偐丅

偙偺戞堦揮夞宍偼偟偽傜偔懕偒丄乮戞俁乣俆彫愡乯挳廜偼偟偽傜偔榓壒偺夝寛傑偱偺徟憞姶傪枴偁傢偝傟傞偙偲偵側傞丅
丂懕偔Allegro偱偼儂儌僼僅僯僢僋側崌彞乮A偲偡傞乯偺偁偲丄傑偝偵乽儕乕僩揑乿側旤偟偄儊儘僨傿乕
丂偙偺俙倢倢倕倗倰倧偺峔憿偼丄ABABA'偲偄偆宍偵側偭偰偄傞偑丄俀丄俁夞栚偺A,A'偵偍偄偰偼丄嵟弶偵Kyrie偲壧偆僪乕僪僪儈偺俀攺偑敳偗偰偄傞偺偑柺敀偄(壓晥嶲徠乯丅側偍丄B庡戣偼摨偠偱偁傞丅
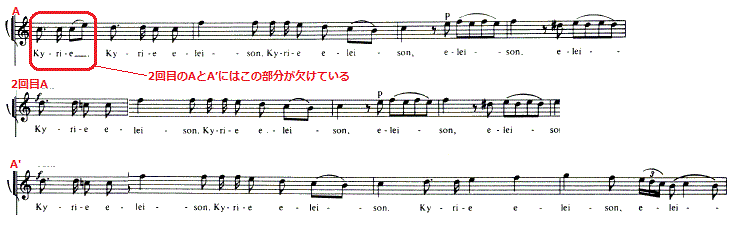
恖娫偼偩偄偨偄嬋偺摢傪挳偄偰偄傠偄傠敾抐傪偡傞傕偺偱偁傞丄偲偄偆偙偲傪儌乕僣傽儖僩偑抦傝敳偄偰偄偰傢偞偲摢傪偗偢偭偨偺偱偁傠偆偐丅偙偺傛偆偵儌乕僣傽儖僩偼僉儕僄偵偍偄偰丄偝傑偞傑側巃怴側帋傒傪偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偡側傢偪丒丒丒
嘆儗僔僞僥傿乕儃宍幃偺摫擖
嘇儕乕僩偺棙梡
嘊僼儗乕僘偺摢偺僇僢僩
偱偁傞丅
俀僌儘儕傾
丂偙傟傕慜弎偺傛偆偵偙傟傑偱偺儈僒嬋偵偼側偄巒傑傝曽偱偁傞丅偡側傢偪敽憈偼尫偺僩儗儌儘偱偁傞丅偙偆偟偨宍偼儘儅儞攈偺儈僒嬋偱偼傛偔尒傜傟傞偑丄儌乕僣傽儖僩偺帪戙偱偼捒偟偄丅
丂懕偄偰Et in terra偵擖傞偲丄宆偳偍傝丄terra(抧乯偵崌傢偣偨傛偆偵崌彞偼掅壒堟傪攪偆傛偆偵側傞丅搑拞偄偭偨傫丄Cdur偺幍偺榓壒偺戞嶰揮夞宍偱廔巭偟丄偙偺宍偱bonae 偲巒傑偭偰偄偔偺偑帹傪堷偔丅
丂laudamus te偐傜偼傑偨嬋憐偑柧傞偔曄傢傞丅懕偄偰Domine丂Deus偐傜偼丄僜儘偑愭摫偟偰僜儘僇儖僥僢僩偑僐儔乕儖晽偵崌偄偺庤傪擖傟傞偲偄偆宍偲側傞丅偙偺傗傝曽偼屻偵働儖價乕僯偑偐偺桳柤側僴抁挷偺儗僋僀僄儉偱傛傝暋嶨側宍偵偟偰摜廝偟偰偄傞丅
2暘係俆昩偐傜
qui tolis pecata mundi傛傝傑偨嬋憐偑曄傢傞丅偙偙偱偼丄僩儕儖偺擖偭偨尫偑帹偵偮偔丅
丂Quoniam tu solus sanctus埲壓偱偼嵟弶偺庡戣偑嵞搙弌尰偡傞偑丄崱搙偼怴偨側庡戣偱壧傢傟傞Jesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris偺僥僉僗僩偺晹暘偑偙偺嵟弶偺庡戣偺拞娫偵偼偝傑傟偰偄傞偺偑偍傕偟傠偄丅偡側傢偪嵟弶偺庡戣傪俙乮Gloria in excelsis Deo乯亄俛乮Et in terra pax hominibus乯偲偡傞偲丄俀夞栚偼俙乮Quoniam tu solus sanctus quoniam tu solus Dominus quoniam tu solus Altissimus乯亄俠乮Jesu Christe Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patoris Amen)亄俛乮俙倣倕値乯偲側傞偺偱偁傞丅
B庡戣乮嵟弶偺晹暘乯
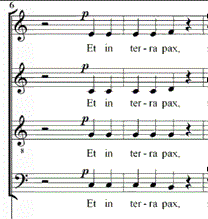
B庡戣乮偁偲偺晹暘乯

俠偑偼偝傑傟偨怴偨側傞庡戣偱偁傞丅偙偙偱偼捠忢偼僼乕僈偲側偭偰暿埖偄偝傟傞Cum Sancto乣埲壓偑嵟弶偺庡戣偵慻傒崬傑傟偰偟傑偭偰偄傞偺偑摿挜偱偁傞丅偟偐偟挳偄偰偄傞暘偵偼妋偐偵Cum Sancto乣埲壓偼偒偪傫偲栚棫偭偰挳偙偊傞偐傜傑偨偡偛偄丅
丂偙偺僌儘儕傾偼偙偺傛偆偵丄捠忢偼僼乕僈偱彂偐傟傞cum sanctus埲壓偺壧帉傕娷傔丄崌彞偼堦娧偟偰丄僜僾儔僲傪庡懱偲偟偨儂儌僼僅僯僢僋偵恑傫偱偄偔丅儕乕僩儈僒偲徧偝傟傞備偊偱偁傠偆丅
俁僋儗僪
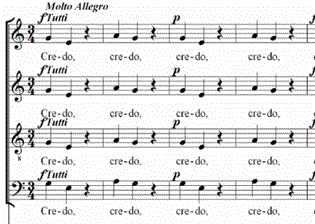
丂偙偺儈僒嬋偺偁偩柤偺傕偲偵側偭偨偺偑偙偺僋儗僪丅Credo,Credo,偲崌彞偑儐僯僝儞偱壗夞傕偗偨偨傑偟偔嫨傇丅偙偙偱慡壧帉偵偍偄偰丄乭Credo"偑偳偺傛偆偵擖偭偰偔傞偐傪尒偰傒傛偆丅
Credo
in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Credo
Et in unum Dominum,Jesum Christum.
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Credo
Deum de Deo,lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genium,non factum,consubstantialem Patri:
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem descendit de coelis. 丄
Credo
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine:
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
Credo
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum:sedet ad dexteram Patris.
Credo
Et interum venturus est cum gloria.
judicare vivos et mortuos:
Credo
cujus regni non erit finis.
Credo
Et in Spiritum sanctum,Dominum,
et vivificantem:
Credo
qui ex Patre Filioque procedit.
Credo
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur:
Credo
qui locutus est per Prophetas.
Credo
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma inremissionem
peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Credo
Amen.
偲偵偐偔傛偔偧偙偙傑偱乭Credo"傪浧傔崬傫偩傕偺偲巚偆丅偙傫側儈僒嬋偼丄偦傟傑偱傑偢側偐偭偨偼偢偱丄弶傔偰挳偄偨恖偼丄搙娞傪敳偐傟偨偺偱偼側偄偐丅偍偦傜偔儌乕僣傽儖僩偼丄偙偺嬋偱壗傜偐偺幚尡傪偟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅偁傞偄偼丄傛傎偳帺暘偺怣嬄傪傗偨傜屩帵偟偨偐偭偨偺偐丅
偟偐偟偙偺妝復偼丄偙傫側傆偞偗偨偙偲傪偟偰偄傞妱偵偼丄柤嬋側偺偱偁傝丄偦偙偑儌乕僣傽儖僩偺偡偛偄偲偙傠偩偲巚偆丅
偙偺妝復偼丄戝嶨攃偵偄偊偽丄Et incarnatus est de Spiritu Sancto 埲壓偺娚彊妝復傪嫴傓ABA乫偺嶰晹宍幃偱偁傞偑丄摿偵娫偺B偺晹暘偼慺惏傜偟偄丅
偙偺B偺娚彊晹暘偱晄巚媍側偺偑丄et homo factus丂est(恖偲側傝乯偺晹暘偱偁傞丅乮壓晥乯丂

戞96彫愡乣
偡側傢偪丄偙偺晹暘偱偼傾僋僙儞僩偑堄幆揑偵偢傜偝傟偰偄傞丅偝傜偵晄巚媍側偺偼丄壒妝揑傾僋僙儞僩偺傒側傜偢丄et homo factus丂est偺傛偆偵丄壧帉偺傾僋僙儞僩傑偱偢傜偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅偙偺堄恾偼晄柧偱偁傞丅偙偺偁偲偺僜僾儔僲偲傾儖僩偺儐僯僝儞傕丄摉帪偲偟偰偼曄懃揑偱栚棫偮丅
屻敿晹暘偺挳偒偳偙傠偼丄Et in Spiritum sancum乣qui locutus est per Prophetas傑偱偺僜儘僇儖僥僢僩晹暘偱丄僶僗僜儘偑Credo,Credo偱庡摫偟偰丄僜儘僇儖僥僢僩乮堦晹Tutti)偑僼僅儘乕偡傞偲偄偆宍偵側偭偰偄傞丅偙偺晹暘偼丄僆乕働僗僩儔傕慺惏傜偟偄丅
嵟屻偼丄乭Credo"偲乭Amen"偑崿嵼偟偰廔傢傞丅偙偺Credo偼丄K257偺拞偱偼丄堦斣偺柤嬋偩偲巚偆丅Cred偼壧帉偑挿偄偺偱丄偳偆偟偰傕偩傟傞偙偲偑懡偄偑丄丄偙偺妝復偵娭偟偰偼丄偦偆偱偼側偄丅
係僒儞僋僩僁僗丂
偙偺嬋偺慁棩偼偐偺桳柤側僕儏僺僞乕壒宆偱偁傞丅乮壓晥嶲徠丅偝傜偵傑偨僕儏僺僞乕壒宆偵娭偟偰偼儌乕僣傽儖僩偺揤嵥偺旈枾偺儁乕僕傪嶲徠偺偙偲乯

丂
丂偟偐偟巆擮側偑傜偙偺嬋偵偍偄偰偼偙偺柍尷偺敪揥偺壜擻惈偺偁傞壒宆偼俲侾俋俀傗岎嬁嬋戞33斣丄僕儏僺僞乕岎嬁嬋偺傛偆偵偼桳岠偵巊傢傟偰偄側偄丅扨偵儂儌僼僅僯僢僋偵張棟偝傟偰偄傞偩偗偱偁傞丅偩偐傜巹偼偙偺僒儞僋僩僁僗偼偦傟傎偳偄偄嬋偩偲偼巚傢側偄丅
側偍丄Hosanna in excelsis 偱偼僔儞僐儁乕僔儑儞偑栚棫偮丅偦偺偨傔偵壒妝揑傾僋僙儞僩偲岅妛揑傾僋僙儞僩偼堄幆揑偵偢傟偝偣傜傟偰偄傞丅儀僱僨傿僋僩儖僗偼揱摑偵偟偨偑偭偰僜儘僇儖僥僢僩偱壧傢傟傞丅暤埻婥揑偵儗僋僀僄儉偵帡偰偄傞偑丄偡傋偰僕儏僗儅僀儎乕偑嶌偭偨摨嬋偑榓惡揑偵偼暯斅偱偁傞偺偵懳偟偰丄偙偺嬋偼偝偡偑偵儌乕僣傽儖僩杮恖偺傕偺偩偗偁偭偰丄榓惡恑峴偵傕旕忢側岺晇偑巤偝傟偰偄傞丅
俆傾僯儏僗僨僀丂
偙偙偼摿偵戝偒側摿挜偼側偄偑丄戞係俋彫愡偺傾僂僼僞僋僩埲壓偺僜僾儔僲偲僥僲乕儖偺偙偩傑偡傞傛偆側妡偗崌偄偺晹暘側偳偼尒帠偩偲巚偆丅傑偨戞俈俋彫愡偲戞俉俉彫愡偺dona偺偲偙傠偱偼僜僾儔僲僜儘偲傾儖僩僜儘偑儐僯僝儞偲側偭偰偄傞丅偙偆偟偨僜儘偺巊偄曽偼屻偺斵偺僆儁儔偱偼偟偽偟偽尰傟傞偑丄儈僒嬋偲偟偰偼偍偦傜偔弶傔偰偺偙偲偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅偟偨偑偭偰偙偺晹暘偼屻偺僆儁儔偺嶌朄傊偺帋峴偲傒偨偄丅
傑偲傔
丂埲忋偺傛偆偵偙偺俲俀俆俈偱偼偄傠偄傠巃怴側傾僀僨傾偑偨偔偝傫惙傝崬傑傟偰偄傞偑丄儌乕僣傽儖僩傪戙昞偡傞儈僒嬋偲偼偄偄偑偨偄丅偨偩丄Credo偼暿奿偱偄偄嬋偩偲巚偆丅屻偺斵偺僆儁儔偺寙嶌孮偺偨傔偺帋嶌昳揑懚嵼偱偁傞丄偲偄偭偨傜彮乆尵偄偡偓偩傠偆偐丅
丂