| ようこそDr.町田のホームページへ モーツァルトの教会音楽のページへ |
楽譜へのリンク 概要 この曲は全演奏時間約20分の小規模なミサ曲である。モーツァルトが1775年一月に「偽りの女庭師」の上演のために滞在していたミュンヘンで作曲された。ヴィオラが入っていないのでおそらくザルツブルク大聖堂で演奏する予定だったのであろう。(ザルツブルクのオーケストラにはヴィオラがなかった) この曲はまさにコロレド大司教の注文を意識した苦心の作といえる。コロレド大司教は①ミサは手短か(45分以内)に終わらなければならない。②ミサ曲は簡素であらねばならない、という鉄則をモーツァルトに示した。 当時コロレド大司教のもとでミサ曲を作曲していたモーツァルトはこの注文通りにミサ曲を書かなければならなかった。このK220はミサ全体を45分以内に押さえるには十分な演奏時間であり、また対位法をほとんど用いていない、などコロレド大司教の注文に沿ってはいる。しかし冒頭のキリエから金管楽器やティンパニががんがん鳴るあたりはモーツァルトがあえてコロレド大司教の注文に応じながらも自己主張を押し通している感じがする。 このK220が「雀のミサ」といわれる所以はサンクトゥスにおけるヴァイオリンの装飾音がいかにも雀のさえずりのように聞こえるために19世紀に入ってからつけられたあだ名である。この雀のさえずりに限らず、K220ではグロリア、クレド、ベネディクトゥスなどでもそれぞれに特有の伴奏音型がつけられているのが特徴である。また曲の一番最後のdona nobis pacemでは冒頭のキリエの主題を再度用いている。(この手法は有名な「戴冠式ミサ」でも用いられる) このK220を書いた時点でモーツァルトは19歳であるが、すでに何曲ものミサ曲を手がけており、ミサ曲全体の統一性ということを念頭において作曲を続けてきたモーツァルトの一つの到達点を示しているものであるといえよう。すなわちミサブレビスであることの特性をいかして、特にテキストの長いグロリア、クレドを特定の伴奏音型がつらぬくことによりそれぞれの曲が統一のとれたものとなるのである。また最終曲への冒頭主題の回帰はミサ曲全体にあたかも3部形式のような統一性を与えるのである。 各論 1キリエ キリエは短いながらもソナタ形式を取っている。冒頭からトランペットとティンパニが明るく響き渡る。一通りの前奏のあとに提示部の第一主題ともいうべき合唱が入ってくるが、一度聴いたら忘れられないような明るく印象的なソプラノ旋律である。この第一主題の旋律は下譜のように旋律①と旋律②にわけられるが、この旋律①がバスで完全五度下でソプラノに引き続いて再度出るのがここの特徴である。 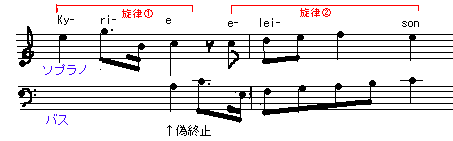 そのためにこの旋律①の終止は偽終止となるのである。この偽終止はサンサンと輝く太陽のもと、明るさ極まりないこのキリエに一風のそよ風を送っているように思える。そしてそのあとに出る旋律②はキリエ全体をつらぬく音型である。モーツァルトがこの音型でキリエ全体を統一しようと企図していたことがわかる。 その後、第13小節からは第二主題というべきChriste eleisonがGdurで出てくる。 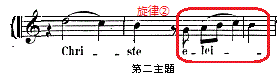 この主題ではしかし、後半においてやはり第一主題の旋律②が使われているのは興味深い。この主題が曲の心棒になっていることがわかる。 その後シンコペーションが入り、なんとなく展開部っぽくなって第20小節からが再現部となる。第35小節からは締結部ともいうべき部分であるが、最後にまた第一主題が繰り返される。結局この非常に印象に残る第一主題は3回現れることになるのである。このキリエが非常に統一感があるのは、ソナタ形式の採用と、特定の主題の繰り返しの使用によるためである。 2グロリア グロリアの特徴は曲全体が また最後のamenでQuoniam tu solus sanctusの旋律が回想されるのもおもしろいやり方である。なお、この曲は最後のCum sancto spiritu以下はフーガとして作曲されておらず、冒頭の 3 クレド 最初この雀のミサ曲を聴いたとき、クレドのチャチャチャチャというヴァイオリンの16分音符のトレモロが雀のさえずりだと思っていた。この弦のトレモロ この冒頭旋律が二回目に現れるのはキリストの復活を祝うテキストであるet resurrexit tertia die~以下であり、三回目は通常はフーガとして書かれる最後のet vitam venturis saeculi,amenである。クレドのように長いテキストの場合、こうした特定の伴奏音型や旋律を繰り返し用いることにより、曲全体が引き締まるのである。 4サンクトゥス 始まりは平凡であるが、Plenisunt coeli et terraの開始直前よりのヴァイオリンの 5アニュスデイ 前半部分は特に特徴は見受けないが、ソロカルテットの このK220のアニュスデイは何と言っても後半のdona nobis pacemが特徴的である。Allegroとなっていきなり「キリエ」の第二主題が現れる。そして、その後あらたな第三の主題が出現する。 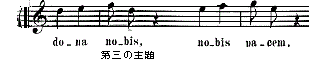 この第三の主題のリズムは まとめ 以上のようにこのK220では曲全体の統一性に綿密な考慮がなされている。モーツァルトの初期のミサ曲の中ではこのK220はおそらく一番有名な曲ではないかと思われるが、その理由はあだ名がついている、という他にこうした曲全体の統一性もまたあげられるであろう。またこの曲は明るい曲の多いモーツァルトのミサ曲の中でもひときわその明るさの輝いているものであるといえる。 |
| ようこそDr.町田のホームページへ モーツァルトの教会音楽のページへ |