音楽エッセイのページへ戻る
ベートーベンの影響力その1へ戻る
前ページで紹介しきれなかったベートーベンならではの音楽的工夫としては以下の事柄があげられよう。
①メヌエットに代わるスケルツォの採用
ハイドン、モーツァルトの時代、交響曲の第二楽章といえばメヌエットだった。メヌエットはもともとは舞曲であり、ゆったりとした三拍子である。第一楽章のソナタ形式で聴衆が少し疲れたところでメヌエットで少しゆっくりしてもらおう、とのことで古典派の作曲家が交響曲の第二楽章に取り入れたのである。
ところがベートーベンは何を思ったか、交響曲からメヌエットを排し、代わりにスケルツォを置くことを考えた。それは第一交響曲第三楽章ではやくも採用され(ベートーベンは一応”メヌエット”としているが、明らかにその内容はスケルツォである)、「英雄」にいたってそれは完成した。「英雄」のスケルツォにより、交響曲の形式は一変してしまったといってよかろう。
スケルツォという曲種はその後ショパン、ブルックナーをはじめさまざまな作曲家により発展させられ、一つの独立した作品群を形成するようになった。その意味でベートーベンが交響曲にスケルツォという曲種を取り入れたことは後世への影響力は大きかったといえよう。
②「第九」におけるレシタティーボと声楽の採用
「第九」第四楽章においてベートーベンはレシタティーボと声楽を採用した。第四楽章においてはチェロバスが”語り”を始める。ベートーベンはそれまでの作曲活動を通してオーケストラにおけるチェロやコントラバスを単なる和音の支えから解放し、その地位を飛躍的に高めたが、最後になんとチェロとコントラバスを曲の主役据えて、しかもあたかも人声のように”語らせて”しまった。
こんな曲を書き始めたからにはどうしてもホンモノのの人声を入れねばなるまい、とのことでついに交響曲という分野に声楽が入ることになった。
交響曲に声楽を取り入れたのはベートーベンが最初であり、むろんこれは特筆すべきことではある。しかし私はそれよりも重要なことはチェロバスを”語らせた”ことだと思う。
オーケストラと声楽の組合せ自体はすでにバロック時代からあり、オラトリオなどといった形式で「第九」ほどではないにしてもかなり大規模なものが作られていた。だから交響曲に声楽を取り入れるという斬新性はあるにしても声楽とオーケストラの共存自体は特に珍しいことではない。
しかしチェロとバスがレシタティーボで”語る”というのは奇抜だ。こんな曲はそれまでどこにも存在しなかった。さらにそれに続くアリアともいうべきかの有名な旋律もまたチェロバスのみで開始される。地の底で這うように始まるあの旋律!
バロック時代にオペラやオラトリオの中で始まったレシタティーボであるが、当時語るのは歌い手であり、チェロバスは通奏低音という脇役に甘んじていた。「第九」の第四楽章に至ってチェロバスは歌い手に取って代わってしまった。そしてかつてチェロバスがやっていた役割はオーケストラ全体が担当することになった。
要するに「第九」第四楽章の最大の眼目はチェロバスによる”語り”なのであり、声楽ではないのである。声楽の付加はあくまでもチェロバスによる”語り”の延長線上のことで、成り行き上、入れざるを得なくなっただけなのだ。
交響曲にレシタティーボを入れるという奇抜なやり方はしかし「第九」が最初で最後であった。したがってこれは空前にして絶後のことだといえる。こうしたオーケストラの扱いは「第九」第四楽章で完璧に完成してしまい、後世の作曲家には発展させる余地がなかったのである。
しかしながらベートーベンが始めたチェロバスの独創的扱いや、交響曲への声楽の採用はその後の作曲家にも引き継がれ、発展していった。
③後期弦楽四重奏曲やピアノソナタにおける前衛的な作曲様式
たとえば弦楽四重奏曲やピアノソナタそれぞれの分野における最終期の作品において、ベートーベンはそれまでのメロディ+伴奏という古典派のワク組みを超え、音楽をそれまでの旋律+伴奏の単純なものから音の坩堝のような世界に変えていき、独自の世界に嵌まり込んでいた。(耳が聞こえていなかったせいもあるのだろう)
こうした曲は当時の聴衆にはきわめて奇異なものに聴こえたであろう。しかしここで気をつけなければならないことは、ベートーベンは音楽の形式を変えたのであって、和声学を変えたのではない、ということである。すなわち形式がいかに複雑怪奇になろうとも、そこで使われている和声は古典的和声学の域を出ず、きわめてオーソドックスなものなのだ。ベートーベンは和声を変革することには手をつけなかったのであって、それは19世紀後半に活躍するワーグナーやチャイコフスキーなどの手にゆだねられることになる。
④ヘミオラを始めとする独特なリズムの使用
ヘミオラというのは本来のリズムをくずして一時的に独特のリズムを形成することである。すでにモンテヴェルディの頃からあり、ベートーベン以前にもかなり多くの作曲家がその作品にヘミオラを取り入れている。
ベートーベンの書いたヘミオラの例として有名なのがたとえば「英雄」の第28小節以下の部分である。ここでは本来の三拍子が一時的に二拍子のようにリズムが変形されていることがわかる。

↑「英雄」第一楽章。スフォルツァンドフォルテがあたかも二拍子の如く書かれている。
ヘミオラ以外にもベートーベンはリズムを本来の音楽上のそれから意識的にずらすことをよくやっている。こうしたベートーベンの作り出した新しい概念の一つであるリズムの変形はその後普遍的となり、さまざまな作曲家によって発展させられることになった。
⑤標題音楽の発展
標題のついた音楽の歴史は意外と古い。たとえば16世紀後半に活躍したジョスカン・デ・プレなどは「こおろぎ」と名づけたア・カペラ曲を書き、その中でこおろぎの鳴き声を擬声した表現を用いている。バロック期に入ると、たとえばモンテヴェルディなどは嵐の描写ではじめてヴァイオリンのトレモロなどを用いている。また超有名なヴィヴァルディの「四季」などは典型的標題音楽である。さらに古典派になるとハイドンのオラトリオ「四季」などのような標題音楽的曲も現れている。
このように標題音楽(あるいは標題音楽的なもの)は古くからあり、ベートーベンの創始になるものではない。が、交響曲ではっきりと風景描写を行ったのはベートーベンの「田園」が最初であり、この曲が名曲で、その後有名になったためか(ヴィヴァルディの「四季」は19世紀にはほとんど知られていなかった)ベートーベンの死後は交響曲のような絶対音楽よりも名前のついた標題音楽の方がむしろ発達していった。この分野に関してはベルリオーズがその最大の後継者であろうが、ともかく19世紀後半の標題音楽全盛の先鞭をつけたのが「田園」であることはまちがいないであろう。(なお、「田園」はそれ自体は標題音楽ではなく、標題的な絶対音楽であるという説もあるが、確かにそれは一理あると思う)
⑥その他ベートーベン独特の一般的作曲様式
いろいろ挙げるときりがないのだが、ベートーベンに特有な書き方というものを譜例などをあげながら見ていきたいと思う。
その1 巧みなクレッシェンド、デクレッシェンドの使用
pからfへ徐々にクレッシェンドしていくやり方はハイドン、モーツァルトではまだあまり見られず、ベートーベンにおいて初めてその効用が花開いた。
たとえば「第九」の第四楽章の第92小節以下の有名な「歓喜の歌」がチェロバスではじめて出てくるところ。(下譜参照)
この主題はこの部分では徐々にクレッシェンドされることを要求している。聴こえるか聴こえないかといった音量から次第にクレッシェンドし、ついに頂点に達して次第にデクレッシェンドして終る。主題そのものをこうしたクレッシェンド、デクレッシェンドを前提に書いたのはベートーベンが始めてではないか。
クレッシェンド、デクレシェンドという音楽のアナログ的概念は古典派において初めて出現した。それまでのバロック期においてはこうした概念はなく、単にpとfのデジタル的交代のみだったのである。(バロック音楽はデジタルであるのページ参照のこと)ベートーベンが推し進めた音楽のアナログ化はその後の作曲家たちにも大きな影響を与え、譜面における<、>といった記号を当たり前のものとした。(ちなみにモーツァルト時代まではこうした記号そのものが存在しなかった)
その2 ベートーベンの音楽は興奮の極地に達すると単純化する
ベートーベンは長いクレッシェンドを経て音楽が頂点に達するという形式を好んだが、その際に特徴的なのはその頂点が意外にも全体のユニゾンや三和音の単純ななぞりなどというきわめて簡素な構造になっていることである。
こうした例は「運命」第四楽章や、ピアノソナタテンペスト第三楽章、「第九」第一楽章その他いろいろなところで認められる。たとえば「第九」第一楽章の第297小節以下では怒涛のように再現部になだれ込んでいく部分がほぼユニゾンとなっている。
このような書き方は実は人間の生理に合っている。人間は極端にハイになるとめんどくさいことは考えないものだ。バカになる。ベートーベンはそういった人間の生理を本能的に知っていて、興奮の頂点はわざと単純な構造にしたのである。
こうしたベートーベンのやり方はたとえばチャイコフスキーの「1812年」第337小節以下などでも踏襲されている。この部分もやはりロシアが戦争に勝って頂点に達したところで、チャイコフスキーはベートーベンばりにフルオーケストラをすべてユニゾンにするというユニークなやり方をしている。
その3 積み木細工のような曲の作り方
これは大変有名なことなので詳述はしないが、とにかくシューベルトのように流麗な旋律が流れないのがベートーベンである。ぶちぶちに切れた主題をつぎはぎ細工のように加工して大きな建築物にするのがベートーベンの真骨頂である。(ただし例外もあってたとえばロマンスヘ長調や弦楽四重奏曲第15番の最終楽章などはベートーベンにしてはめずらしくロマンティックな旋律が流れる)
しかしベートーベンのこうした作曲法はある意味で危うさも持っている。積み木細工はうまく組み上げられば大変な名曲になるが、失敗すると積み木がばらばらに散らばっているようなつまらない曲になる。ベートーベンの曲に意外と駄作が多いのはこうした作曲のやり方のためなのかもしれない。
シューベルトなどはその点あまり駄作がないが、ベートーベンの書法を参考にして書いたと思われる「ザ・グレート」などは駄作とまでは言えないが、冗長すぎて退屈である。
この手の積み木細工として成功したのが有名な「運命」第一楽章であり、失敗したのが第七交響曲第一楽章である。こう書くと第七交響曲のファンは怒り狂うであろうが、私はこの曲は何度聴いてもいい曲だと思わない。なぜかといえば、この両曲はともに単純なリズムの積み木細工として構成されているが、第七交響曲第一楽章の場合は全体を貫く
その4 ワーグナーが真似した「第九」
「第九」の第四楽章は最初にオーケストラのみで演奏され、同じテーマを今度は合唱とソロが歌うという形式を取る。ワーグナーはタンホイザーの有名な「大行進曲」でこのやり方をそっくり真似している。途中長いクレッシェンドがあるところまでよく似ている。
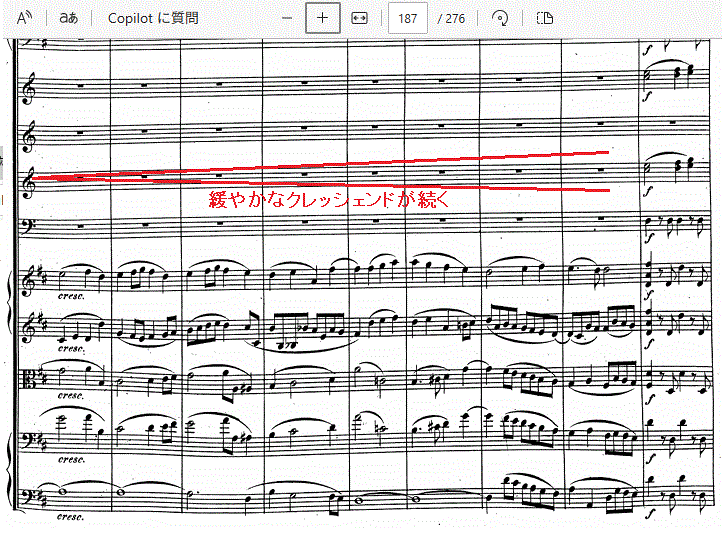
第九第四楽章
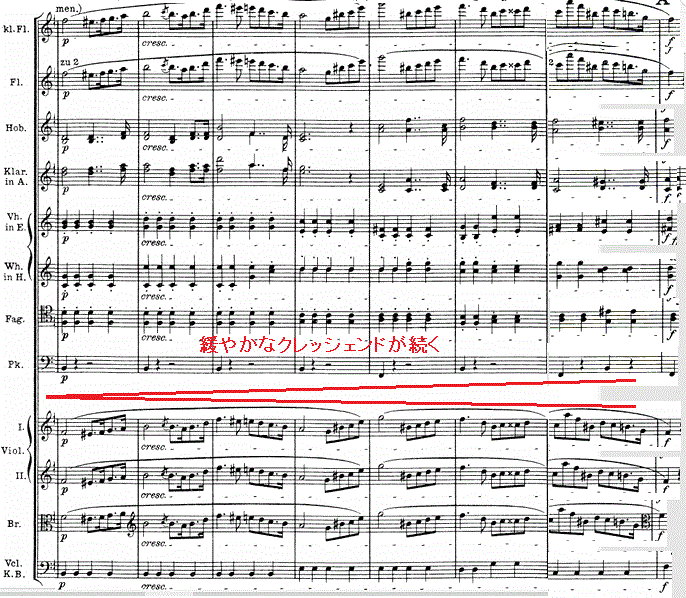
ワーグナー タンホイザーより大行進曲
その5ブラームスが真似したベートーベンのホルンの音型
ブラームスはベートーベンを敬愛していた。そのために、40歳過ぎまで、第一交響曲を完成できなかった。彼の作品には、おそらくはあえて必要もないのに、、わざわざベートーベンの真似をしたと思われる部分がある。ドイツレクイエムの第4曲”Wie lieblich sind deine Wohnungen”の中の以下の部分である。

ブラームス「ドイツレクイエム」第四曲より
ここはベートーベンの第九第三楽章に以下のホルンパートの三連符を必要もないのに真似ているのである。
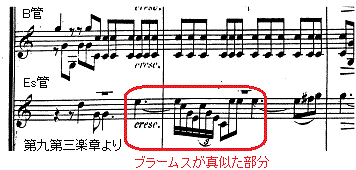
ベートーベン「第九」第三楽章kより