| K65 ミサブレビス 楽譜へのリンク 概要 この曲は1769年1月14日に完成し、2月5日のザルツブルク大学の教会での「40時間の祈り」の祈りの際に演奏されている。ザルツブルクで演奏されたため、ヴィオラパートはない。(ザルツブルクのオーケストラには当時ヴィオラがなかった)この「40時間の祈り」というのは四旬節(キリストの復活までの6週間のことを指し、イエスが荒野で40日間悪魔の誘惑に耐えたことにちなんでいる。)の最初の日の「灰の水曜日(Ash Wednesday)」の前に行われていた儀式で、キリストの復活の前に罪の償いをするというものであった。そのためにモーツァルトにしては珍しいニ短調という調性を選んでいる。(ニ短調はまたかの「レクイエム」の調性でもある) 各論 1キリエ この曲は変形したソナタ形式で書かれている。最初にハイドン風の短いAdagioがつく。これがフリギア終止でトニックで終止するとソナタ形式の提示部にあたるAllegroが始まる。 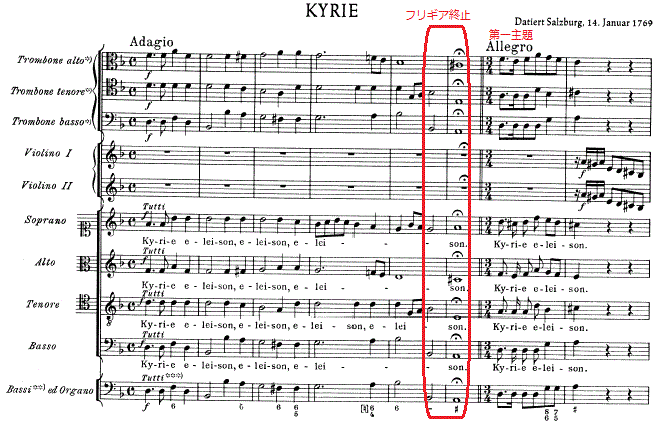 序奏と第1主題 第11小節からバスが半音下降していくさまは往年のバスラメントを彷彿させるものである。Kyrie eleisonが三回繰り返される間、調性はずっとニ短調であるが、第二主題であるChriste eleisonが次にヘ長調に転調して入ってくる。このあたりの持っていき方は後年の「レクイエム」の入祭唱を思わせるものである。 Christe eleisonは一貫して長調系であり、Kyrie eleisonとのコントラストがはっきりしている。 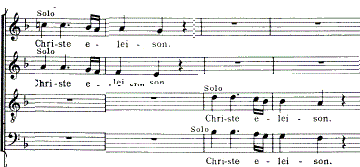 第2主題 続いて展開部にあたる短いKyrie eleisonが一回ト短調で歌われると、第28小節から早くも再現部である。ただ、その後の第二主題にあたる部分がない。あまりに曲が短いため、ここでそれを出すとくどくなるために、モーツァルトは本能的にカットしたのだろう。 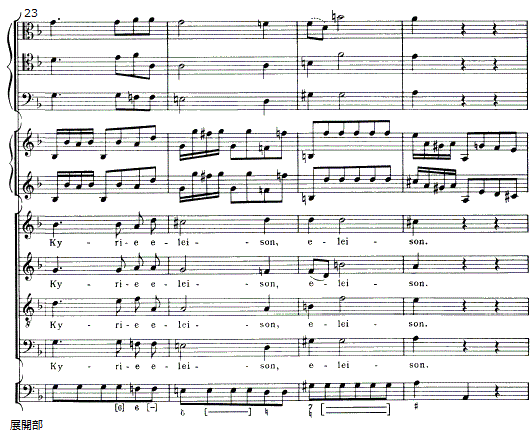 2グロリア 最初のGloria inexcelsis Deoは先唱者によって歌われる。 このグロリアの特徴は、合唱とオーケストラのほぼ完全な分離である。モーツァルトの中〜後期の作品ではしばしば見られるが、この作品のような初期では珍しい。(下譜) 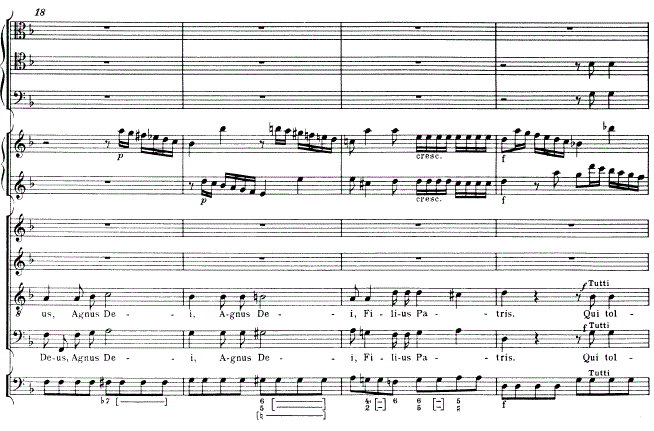 第38小節からのCum Sancto Spiritu〜は伝統にのっとったフーガとなる。このフーガの主題は下譜のように教会旋法の第1旋法であるドーリア旋法である。実際はシの音が♭されているので実質上は自然短音階と変わらないが、やはりこの主題にはなんとなく教会旋法の素朴な響きを感じないだろうか。そして12歳にしては練達の腕でフーガが展開され、最後のAmenでは一部シンコペーションとなって曲が終わる。このシンコペーションは次のクレドにおいてはもっと大規模に現れるので、ここはいわばそのための布石となっているのである。 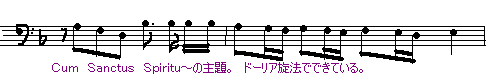 なお、このフーガも、合唱とオーケストラの分離が著しい。 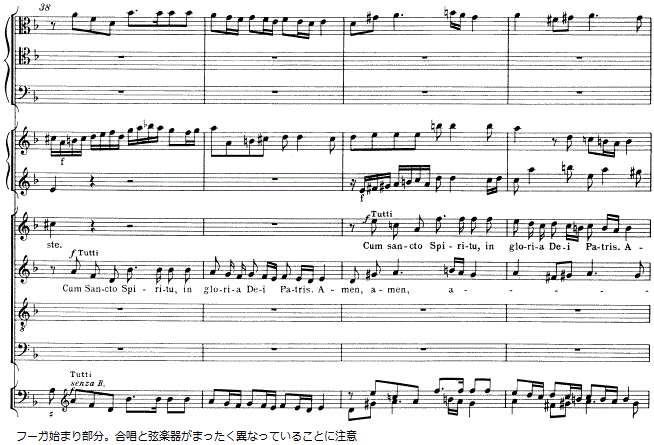 3クレド ここもまたグロリア同様、最初のCredo in unum deumは先唱者によって歌われる。K65はミサブレビスではあるが、クレドの歌詞はさすがに長いので、曲は3つのパート+最後のフーガという風に分れている。 第一のパートはdecendit de coelisまでで、この部分は合唱とソロカルテットが交互に現れるのが特徴である。合唱はほとんどホモフォニックに歌われるが、ソロカルテットは掛け合いのような形で歌われ、そのコントラストは見事である。descenditの歌詞が来ると伝統にしたがって、下降音型となる。ソプラノが先導してバスがこれに答えるという形を取っている。 第二のパートは第40小節Et incarnates est〜よりet sepultus estまでであるが、個々の部分は合唱のみでおおむねホモフォニックに進んでゆく。興味深いのは第43−44小節にわたってのバスの部分ex Mariaである。ここはバスのみとなるのであるが、これはこの部分のバスがいわゆる十字架音型を形成しているためである。(下譜参照)あとからでてくるCrucifixを音型にて先取りしているのである。 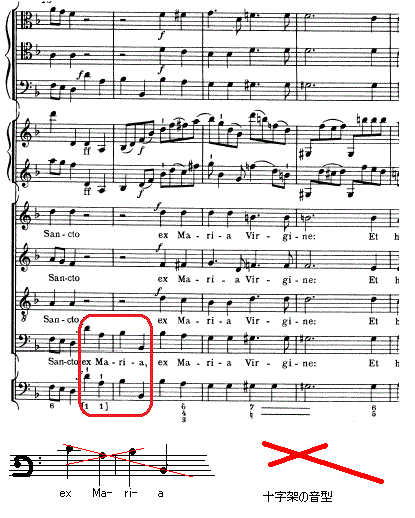 クレド 第43小節〜 第三のパートは第58小節Et resurrexit tertia die〜よりフーガの直前のresurrectionem mortuorumまでの長い部分である。キリストの復活をのべるEt resurrexitの部分は伝統にしたがって明るい出だしとなっている。ホモフォニックな合唱が続いた後にソロカルテットの掛け合いが入り、再度また合唱が続いてくる構成となっている。そして第122小節でいったんアーメン終止で明確に終止した後、第四のパートであるフーガが入ってくる。 クレドの最後のEt vitam venturi saeculi Amenのところは伝統的にフーガで書かれるが、K65においても例外ではなく、やはりフーガで書かれている。ただここのフーガは面白いことにシンコペーションを多用しているのである。これはおそらくモーツァルトの時代にはめずらしいことであると思う。(ベートーベンとなるとこうしたシンコペーションやヘミオラをよく用いているが) すなわち下譜のようにフーガの第一拍をあえて休符としているのである。しかし聴いている方はそれには絶対気がつかないから、どこかで聴衆が?と思うところがでてくる。ここがミソである。この主題では第126小節がそうしたつじつま合わせの場所となっており、ET viTAM VENtuRI VENtuRI SAEculi AMEN(大文字がアクセントのある部分、小文字はアクセントのない部分を示す)という歌詞がタン・タン・タン・タン・タン・タ・タン・タン・タンというリズムになる。こうしたリズムの扱いを見ると12歳の天才作曲家はすでに同時代の作曲水準をはるかに抜いていたことがわかるのである。 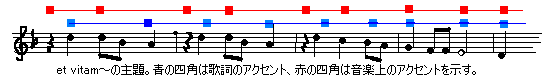 こうしたシンコペーションによる音楽上のアクセントと歌詞のアクセントとのずれはずっと続き、最後のAmenのホモフォニーにおいてなお、ずれたままである。(聴きなれるとズレはなくなってくる) 第141小節でとりあえずこのずれがおさまったかと思いきや、またシンコペーションとなり、第144小節にいたってやっとこれらが一致して安定した終止をむかえることになるのである。 4サンクトゥス サンクトゥスは神を賛美する部分なので大抵のミサ曲では(レクイエムにおいてさえも)長調で明るく書かれるのが通常であるが、K65ではこの部分でさえもニ短調で書かれている。Hosanna inexcelsis Deoのところではヘミオラが使われており、やはり音楽上のアクセントと歌詞のそれとがずらしてあるのが興味深い。(下譜参照) 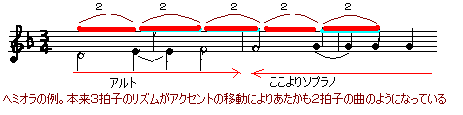 ベネディクトゥスではソプラノソロとアルトソロのデュエットによる半音階の下降音型が使われている。ここもまた通常は「ほむべきかな」という賛美の歌詞なので明るく書かれるのが普通であるのにモーツァルトはあえてバスラメントを思わせるような下降音型としたのである。やはりこれは演奏される機会(前述のようなキリストの復活の前での罪の償いの儀式「40時間の祈り」)を考慮してのことだと思われる。 5アニュスデイ 前半のMiserere までは通常のミサ同様、短調の暗い感じである。四部合唱で、ホモフォニックに進んでいく。後半のDona nobis pacemは通常は明るくはなやかな感じになるのだが、このK65においてはこの部分までもニ短調で開始され、リズムは三拍子で速くなるが、途中で長調系に転調してもこの傾向はあまり変わらない。そして最後まで何となく浮かない雰囲気のままにK65全体は終了する。 まとめ このK65はモーツァルトにしては珍しく徹頭徹尾短調系のくすんだ雰囲気を持ったミサ曲である。曲の完成度の高さで忘れがちになるが、この曲もまたモーツァルトが13歳になんなんとする年頃の作品なのである。今の日本でいえば中学一年生がこんなメランコリックな曲を書いたことになるが、やはりこれは信じがたいことである。 K65は曲の規模も小さく、K139などに比べるとやや見劣りがするのは否めないが、よくよく分析するとやはりモーツァルトならではの書法がところどころに見てとれる。また、シンコペーションやヘミオラの使い方も興味深い。さらに、特にGloriaにおける合唱とオーケストラの分離傾向など、後年の曲を先取りする書法も認められる。モーツァルトのミサ曲の代表作とまではいえないが、K139などと組み合わせてもっともっと演奏されてほしいと思う曲である。 |