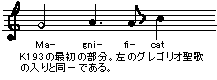���e�b�g�@K47 Veni�@Sancte�@Spiritus�i�����A�����肽�܂��j ���[�c�@���g�̋���y�̃y�[�W�� �y���ւ̃����N VIDEO Veni Sancte Spiritus �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A�����苋���B �����̃e�L�X�g�͐���~�Փ��̃Z�N�G���`�A�̈�Ƃ��ėL���ȁuVeni Sante Spiritus�v�ł͂Ȃ��AAd
invocandum Spiritum Sanctum�Ƃ����A���e�B�t�H���̈�߂ł��� ���̋Ȃ͂P�V�U�W�N�̐���~�ՍՂ̍��i���������U���B�C�[�X�^�[�̓����犷�Z�����̂Ŗ��N�قȂ�j�ɏ����ꂽ���̂Ƃ���Ă������A�ŋ߂̐��ɂ��Όǎ��@�t����q���ł̌������̂��߂ɏ����ꂽK�P�R�X�̂��߂̘r�Ȃ炵�Ƃ��ď����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ̂��Ƃł���B�`���̃I�[�P�X�g���� K141�@Te�@Deum �@�@�y���ւ̃����N VIDEO �e�E�f�E���͂��Ƃ��Ƃ͐������ۂ̈�ł��钩�ۂɂ����Ď��ё�X�T�҂ȂǂƂƂ��ɉ̂��Ă������̂ł���B���̃e�L�X�g���e�͂S���I�̃~���m�̎i���A���A���u���V�E�X�ɂ����̂Ƃ���Ă���B�_���^�����钷���e�L�X�g�ł���B���̓��e����A�Â����炳�܂��܂ȏj�T�Ȃǂ̂��߂ɂ��܂��܂ȍ�ȉƂ��Ȃ����Ă����B
K34�@Scande�@Coeli�@Limina(�o��A�V�ւ̓��j VIDEO �̎� Scande coeli limina,
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�肽�܂��A�V�ւ̓� ���̋Ȃ�1766�N�A�Ȃ�ƃ��[�c�@���g���܂��X��10�̎��̍�i�ł���B�̎���۰ϋ���̌����̓T�當�ł͂Ȃ��A�U���c�u���N�n���ɏZ�ރx�l�f�B�N�g��̈�C���m����������̂Ƃ����Ă���A���[�c�@���g�����̔N�Ƀp�����s����A���ăo�C�G�����̃[�[�I���̃x�l�f�B�N�g�C���@��K�ꂽ�ۂɏ��������̂Ƃ����Ă���B���e�͂R���Q�P���̐��x�l�f�B�N�g�̏j���̂��߂̃I�b�t�F���g���E���ł���B �Ȃ͑O���̃\�v���m�A���A�ƌ㔼�̍����Ƃɕ�������B�O���̃A���A��ABA�̃_�E�J�[�|�`���̃o���b�N�I�ȗv�f���������̂ł��邪�A���ԕ���B�̕����̔��t�Ȃǂł͒P���ȌJ��Ԃ����^�������A�ÓT�h�I�ȗv�f���_�Ԍ�����B�܂����̕����̒����̕ω��������ł���B�㔼�̍����͂͂����肢���đʍ�ł���B�����瑁�n�̑�V�˃��[�c�@���g�Ƃ͂����A�킸��9�̎��̍�i�ł��邩���ނȂ��Ƃ͂����邪�B���������t�Ȃǂ��e�ׂɂ݂�ƁA���NJy��̎g�����͓��R�ÓT�h�I�ɂȂ��Ă��邵�A���Ƃ��Α�Q�Q���߈ȉ����T�P���߈ȉ��̉��^�Ȃǂ͊��S�Ƀo���b�N�I�v�f�𗣂�A�ÓT�h�ɓ����I�ȉ��^���łĂ���B �|���t�H�j�[�ƃz���t�H�j�[�̗Z��
K223�@Osanna ���̋Ȃ͋U��Ƃ̂��Ƃł��� �B
K222�@Misericordias�@Domini VIDEO Misericoridias�@Domini�iA�j�@�@�@�@�@�@�@�@��������݁i�z���t�H�j�[�j ���̋Ȃ�1775�N�Ƀ��[�c�@���g���I�y���u����������t�v����Ȓ��ɋC���]���ƑΈʖ@�̏K�n�����˂ď��������̂ł���B�����Ďt�ł���}���e�B�[�j�_���ɑ����𑗕t���A��^���ꂽ�Ȃł���B�̎��͏�L�̂悤�ɂ���߂ĒZ�����̂ŁA���ё�W�W�҂̖`���̈�߂ł���B���̉̎������X��11��J��Ԃ����̂ł���B�y��\���͌��y��i���@�C�I�����Q�p�[�g�{�`�F���o�X�j�ƃI���K���ł��邪�A��Ƀz�����ƃI�[�{�G�����̐l�Ԃɂ��lj�����Ă���B�i�����e�[�}�@�j �������t�ł�̂������ł���B�e�[�}�@�@ A1(1-)B(4-)A1(15-)B(17-)A2(23-)B(27-)A1(37-)B(39-)A2(49-)B(53-)A1(64-)B(67-) �ȉ��A���ꂼ������B�e�[�}�A �e�[�}�B �@���̌�A��T3���߈ȉ��ł̓~���[�C���[�W�ɂ���A�ƇB���������m�ł��悢�挃�����A���ڂԂ��邱�ƂɂȂ�B����ɂ́A�����ɁA�ό`���Ă���e�[�}�E�̐����������A�O�d�t�[�K�̂悤�ɂȂ�i�����B�A���A�e�[�}�E�͑����A�������ł͓����Ă��Ȃ��j�B���̋Ȃ͂��Z�p�ɜ��݂����Ă��邫�炢�͂�����̂́A���[�c�@���g�̏@���ȂƂ��Ă͍ŏ�ʂ̕��ʂɈʒu����� �Ƃ����悤�B
K260�@Venite�@Populi�i���l��A������j �y���ւ̃����N VIDEO
Venite populi, venite �@�@ ����A�������̍��̖��旈��A
�i���� ������ TELDEC
WPCS-4459 �j
�@���̋Ȃ͑������̂̃I�b�t�F���g���E���ƌĂ�A���̂̓T��̂��߂̋ȂƂ̂��Ƃł���B�������̎��͓���̓T�當�ł͂Ȃ��A�쎌�҂��s���ł���B��Ƀu���[���X�����̋Ȃ������]�����A����w�����ĉ��t�������ƂŗL���ł���B���t�͌��݂̂ł���B
�@ �y���ւ̃����N VIDEO �PDixit�@Dominus �Q�@Magnificat K341�@�L���G �y���ւ̃����N VIDEO ���_ �e�_ �܂Ƃ� ���[�c�@���g�̋���y�̃y�[�W��
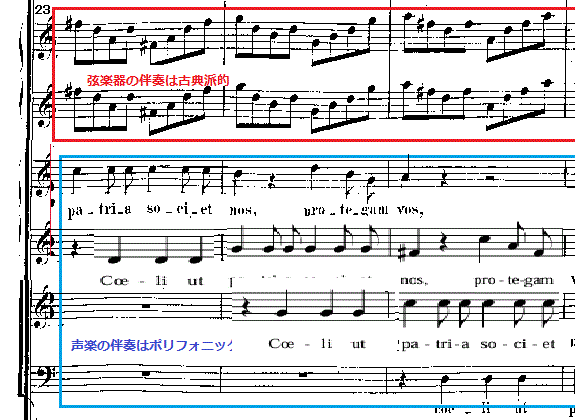
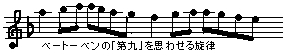 �e�[�}�@�@
�e�[�}�@�@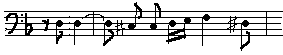 �e�[�}�A
�e�[�}�A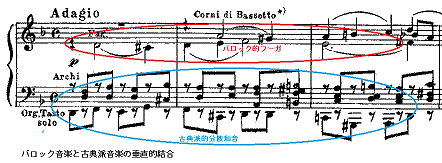 ���N�C�G��introit�̃e�[�}
���N�C�G��introit�̃e�[�}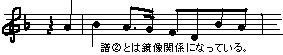 �e�[�}�B
�e�[�}�B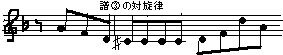 �e�[�}�C
�e�[�}�C �e�[�}�D
�e�[�}�D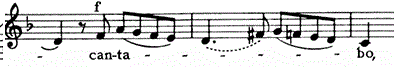 �e�[�}�E
�e�[�}�E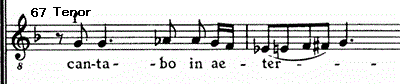 �e�[�}�F
�e�[�}�F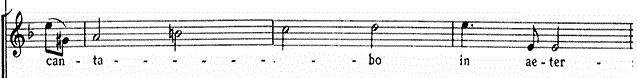
 �@
�@
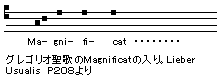 �@�@
�@�@