|
丂1780擭偵嶌嬋偝傟偨丄儌乕僣傽儖僩偺姰惉偝傟偨儈僒嬋偲偟偰偼嵟屻偺嶌昳丅傑偨僓儖僣僽儖僋戝惞摪偱墘憈偝傟偨儌乕僣傽儖僩偺儈僒嬋偲偟偰傕嵟屻偺嶌昳偱偁傞丅側偍丄偙偺儈僒嬋傪乽憫尩儈僒乿偲偟偨偺偼働僢僿儖偱偁傞偑丄捠忢憫尩儈僒偱庢傜傟傞僌儘儕傾傗僋儗僪側偳偺僇儞僞乕僞宍幃偼偙偺儈僒嬋偱偼庢傜傟偰偄側偄丅偟偨偑偭偰嬋偺挿偝偱偼側偔暤埻婥偱傕偭偰働僢僿儖偼偙偺儈僒嬋傪乽憫尩儈僒乿偲偟偨偺偱偁傠偆丅
丂偨偟偐偵偦偆偣偞傞傪偊側偄暤埻婥偑偙偺嬋偵偼偁傞丅僐儘儔僪戝巌嫵偺梫惪偱慡懱偑愗傝媗傔偰彂偐傟偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄偦偺枾搙偼擹偔丄屻偵彂偐傟傞戝儈僒嬋偵傕晧偗偢楎傜側偄傕偺傪帩偭偰偄傞姶偠偑偡傞丅
丂偙偺儈僒嬋偼僼傽僑僢僩偑岠壥揑偵巊傢傟偰偄傞偺偑摿挜偱偁傞丅偨偲偊偽僋儗僪偺Ex丂Maria丂Virgine側偳偺売強偱偼偙偺僼傽僑僢僩偑岠壥揑偵巊傢傟丄撈摿偺尪憐揑側暤埻婥傪忴偟弌偡偺偵堦栶攦偭偰偄傞丅
侾僉儕僄丂摿掕偺宍幃傪庢傜偢儕乕僩偺傛偆側棳傟傞慁棩傪帩偭偰偄傞丅慜憈傕傑偨偙偺慁棩傪扨弮偵棳偡偩偗偱偁傞丅搑拞偙偭偨榓惡側偳傕側偔偦傟偩偗偵嵟屻偺戞俆侽彫愡偺尭幍偑栚棫偮丅
俀僌儘儕傾丂僇儞僞乕僞宍幃偱偼側偔丄憫尩儈僒偵偼傆偝傢偟偐傜偸娙扨側峔惉偱偁傞偑丄傛偔挳偔偲楢懕偟偰偄傞偲偼偄偊丄偒偪傫偲僇儞僞乕僞宍幃傪摜傑偊偰嬋偑嶌傜傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偙偙偱偼偦傟偧傟偺晹暘傪暘偗偰尒偰傒傛偆丅
嘆Gloria in excelsis Deo乣僴挿挷丂崌彞
嘇Laudamus te乣丂僩挿挷丂崌彞
嘆偲嘇偼僇儞僞乕僞宍幃偱偼彂偒暘偗傜傟傞偺偱偁傞偑丄儌乕僣傽儖僩偼懕偗偰偄傞丅偟偐偟丄Laudamus
te偵擖傞偲僩挿挷偵揮挷偡傞偨傔偵丄偙偙偱壧帉偑曄傢傞偙偲偑報徾偯偗傜傟傞丅
嘊Domine Deus rex coelestis乣丂僩挿挷丂僜儘僇儖僥僢僩亄崌彞
偙偙偐傜偼僜儘僇儖僥僢僩偑擖偭偰偔傞偑丄崌彞偑儐僯僝儞偵傛傞僀儞僩乕儞偱墳彞偡傞宍偲側偭偰偄傞丅埲壓偺擛偔丅
Domine deus,Rex coelestis,乮僜儘僇儖僥僢僩乯仺Deus Pater omnipotens乮崌彞乯
Domine Fili unigenite,乮僜儘僇儖僥僢僩乯仺Jesu Christe乮崌彞乯
Domine deus,Agnus dei,乮僜儘僇儖僥僢僩乯仺Filius Patris.乮崌彞乯
擔杮岅偩偲埲壓偺傛偆偵側傞丅
恄側傞庡丄揤偺墹仺慡擻側傞晝側傞恄傛
庡側傞傂偲傝巕仺僀僄僗僉儕僗僩傛
恄側傞庡丄恄偺彫梤仺晝偺屼巕傛
偙偆偟偨敪憐偵偼儌乕僣傽儖僩偺偙傟傑偱偺儈僒嬋偵偼偁傑傝尒傜傟側偐偭偨傕偺偱偁傞丅乮慜擭偵彂偐傟偨乽懻姤儈僒乿偺僋儗僪側偳偵傕摨條偺敪憐偑尒傜傟傞丅傑偨弶婜偺嶌昳偱偁傞K侾侾俈偺乽Benedictus丂sit
Deus乿偵帡偨傛偆側帊曆彞偑尒傜傟傞乯
嘋Qui tllis peccata Mundi乣
偙偺晹暘偺幃暥偼墳彞宍幃偲側偭偰偄傞偑丄儌乕僣傽儖僩偼偙偺晹暘偼愭傎偳偲偼媡偵丄崌彞仺僜儘僇儖僥僢僩偲偄偆宍幃偲偟偰偄傞丅
Qui tollis peccata mundi,乮崌彞乯仺misrere nobis乮僜儘僇儖僥僢僩乯
Qui tollis peccata mundi,乮崌彞乯仺suscipe deprecationem nostram.乮僜儘僇儖僥僢僩乯
Qui sedes ad dexteram Patris,乮崌彞乯仺miserere nobis.乮僜儘僇儖僥僢僩乯
嘍Quoniam tu solus乣丂擇挿挷丂崌彞
堦墳挷惈偼擇挿挷側偺偩傠偆偑丄僠僃儘僶僗丄僩儔儞儁僢僩丄僥傿儞僷僯偑慜彫愡偺G傪攚晧偭偰偄傞偺偱丄G亄Ddur偺晄嫤榓壒偱巒傑傞丅嵟屻偺戞俇俀乣俇係彫愡偺乽Jesu丂Christe乿偺偲偙傠偱偼堦弖僆乕働僗僩儔偑徚偊丄僀僄僗僉儕僗僩偲偄偆尵梩傪晜偒棫偨偣偰偄傞丅
嘐Cum sancto spiritu乣丂僴挿挷丂崌彞亄僜儘僇儖僥僢僩
偙偙傛傝嘆偲摨宍偵側傞偑丄偡偖偵Amen偵堏峴偡傞丅
亙慡懱島昡亜
丂慡懱揑偵偼儌乕僣傽儖僩摼堄偺崌彞偲僆乕働僗僩儔偺暘棧偑擣傔傜傟傞丅偙傟偼杴梖側嶌嬋壠偱偼偳偆偟偰傕僆乕働僗僩儗乕僔儑儞偑崌彞捛悘偵側傝偑偪偵側傞偺偵懳偟偰儌乕僣傽儖僩偺嬋偱偼崌彞偲偲傕偵僆乕働僗僩儔偑撈帺偺庡戣側偳傪忴偟弌偟偰偍屳偄偑傇偮偐傝崌偄傪偡傞偺偱偁傞丅乮壓晥乯

丂偙偺儈僒嬋偲傎傏摨偠崰偵彂偐傟偨償僃僗儁儗側偳偱偙偺孹岦偑尠挊偱丄偙偺崌彞偲僆乕働僗僩儔偺傇偮偐傝崌偄偺僟僀僫儈僘儉偑儌乕僣傽儖僩偺嫵夛壒妝偺枺椡偲傕偄偭偰傛偄丅
偙偺僌儘儕傾偱偼戞侾俉彫愡埲壓傛傝尫妝婍偱憈偱傜傟傞撈摿偺壓崀壒宆偑偦偺徾挜偱丄偙偙傛傝偟偽傜偔偼傑偝偵崌彞偲僆乕働僗僩儔偺傇偮偐傝崌偄偺応偲側偭偰偄傞丅偙偺壓崀壒宆偼丄Amen偵擖傞偲嵞弌尰偡傞丅
俁僋儗僪丂
偙偺妝復傕丄僌儘儕傾傎偳僋儕傾僇僢僩偱偼側偄偑丄僇儞僞乕僞宍幃偵弨偢傞宍偱彂偐傟偰偄傞丅埲壓偺偛偲偔偵暘偗傜傟傞丅
嘆Credo in unum Deum乣
儂儌僼僅僯僢僋側丄嶰攺巕偺棳傟傞傛偆側慁棩偱偁傞丅偨偲偊偽傾儖僩埲壓偺惡晹傪徚偟偰偟傑偭偨偲偟偰傕廫暘挳偗傞傛偆側慁棩偱偁傞丅
嘇Et incarnatus est de Spiritu Sancto乣
僙僆儕乕捠傝丄偙偺壧帉偐傜偼嬋偑Andante偲側傞偑丄偙偙偱摿昅偡傋偒偼丄僆乕儃僄偲僼傽僑僢僩偺巐廳憈偱偁傞丅
Crucifixus埲壓偱偼丄崌彞偑僜仺僼傽侐仺僼傽仺儈仺儈侒仺儗偲敿壒壓崀偟偰偍傝丄僶僗儔儊儞僩偲帡偨傛偆側暤埻婥傪嶌傝忋偘偰偄傞丅
嘊Et resurrexit tertia die,乣
偙偙傕僙僆儕乕捠傝丄偙偙傛傝Allegro偲側傞偑丄婎杮揑偵嘆偺僷僞乕儞偑巊傢傟偰偄傞丅偙偙偱拲栚偡傋偒偼丄mortuos乮巰偣傞恖乯偺晹暘偱丄偙偙偺傒壧帉傪斀塮偟偰丄抁挷偵側偭偰偄傞丅乮壓晥乯

嘋Et in Spiritum sanctum,Dominum乣
偙偙傛傝僜儘僇儖僥僢僩偲側傞偑丄挷惈偼壓懏挷偱偁傞僿挿挷偑懕偔偙偲偵側傞丅堦斒揑偵儌乕僣傽儖僩偺帪戙偵偼懏挷傊偺揮挷偼捒偟偔側偄偑丄壓懏挷傊偺偙傟偩偗偺挿偄揮挷偼捒偟偄丅
側偍偙偙偱偼僼傽僑僢僩偑嵞搙戝妶桇傪偡傞丅偡側傢偪丄僜僾儔僲偺慁棩傪側偧偭偰偄偔丅
嘍Et unam sanctam catholicam乣
柧傞偄3攺巕偐傜丄et exspecto偐傜偼抁挷偲側傞丅偙偺晹暘偵mortuorum乮巰幰偺乯偺壧帉偑擖偭偰偄傞偙偲傊偺攝椂偱偁傠偆丅傑偨丄傾儖僩偺宷棷偑偡偽傜偟偄丅
嘐Et vitam venturi saeculi.Amen
捠忢戝偒側儈僒嬋偱偼僼乕僈偲側傞晹暘偱偁傞偑丄偙偺嬋偼柍榑丄偦偆偼側傜偢丄Gloria摨條丄嵟弶偺庡戣偵夞婣偡傞丅側偍丄Amen偱偼戞俆係乣俆彫愡偱朑夎揑偵弌偰偒偨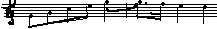 偲偄偆慁棩偑孞傝曉偟敪揥偝偣偰巊傢傟偰偄傞丅偙傟傕傑偨崱傑偱偵偼偁傑傝尒傜傟側偐偭偨敪憐偱偁傞丅 偲偄偆慁棩偑孞傝曉偟敪揥偝偣偰巊傢傟偰偄傞丅偙傟傕傑偨崱傑偱偵偼偁傑傝尒傜傟側偐偭偨敪憐偱偁傞丅
係僒儞僋僩僁僗丂僒儞僋僩僁僗偼偙偺儈僒嬋偵偍偄偰偼捠忢偲媡偺嶌嬋朄傪庢偭偰偄傞丅偡側傢偪捠忢偼Hosanna丂in丂exce倢sis
Deo偺偲偙傠偑僼僈乕僩偵傛傝億儕僼僅僯僢僋偵丄Benedictus偑僜儘僇儖僥僢僩傪拞怱偵儂儌僼僅僯僢僋偵嶌傜傟傞偙偲偑懡偄偑丄偙偺儈僒嬋偵偍偄偰偼媡偵慜幰偑儂儌僼僅僯僢僋偵丄屻幰偑僼乕僈偱峔惉偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂摿偵僼乕僈偱嶌傜傟偨Benedictus偲偄偆偺偼捒偟偄丅傑偨慜幰偼摿偵儕乕僩偺傛偆側戝曄旤偟偄慁棩傪帩偭偰偄傞丅Benedictus偱偼偙偺儈僒嬋桞堦偺抁挷偱偁傝丄偍偦傜偔偙偺儈僒嬋偱堦斣栚棫偮偲偙傠偱偁傞丅偟偨偑偭偰偙偙傛傝擇夞栚偺Hosanna傊偲堏傞晹暘偼傑傞偱僶儘僢僋婜偐傜偄偒側傝儘儅儞攈壒妝傊僕儍儞僾偡傞傛偆側嶖妎傪偍傏偊傞丅偲偵偐偔偙偺懳徠偼尒帠偱偁傞丅
俆傾僯儏僗僨僀丂僀僞儕傾傾儕傾傪巚傢偣傞僜僾儔僲偺挿偄僜儘偑懕偔丅挷惈偼曄儂挿挷偲側偭偰偄傞丅傑偨僆儖僈儞偺僆僽儕僈乕僩偑偮偄偰偄傞偺傕摿挜偱偁傞丅傑偨戞俀俁彫愡偱偼僫億儕偺榋傕巊傢傟丄傑偝偵僀僞儕傾揑偱偁傞丅崌彞偼嵟屻偵抁偔擖傞偩偗偱偁傞偑丄揮挷傪孞傝曉偟丄曄宍偟偨僼儕僊傾廔巭偵傛傝師偺Dona丂nobis丂pacem傊偲懕偔丅
丂嵟屻偺Dona丂nobis
pacem偱傕偄傠偄傠偍傕偟傠偄岺晇偑偁傞丅偨偲偊偽戞俇俆彫愡偐傜俇俇彫愡傊偼僩挿挷偐傜曄僀挿挷偲偄偆旕忢偵栚棫偮榓惡恑峴偑偁傞丅傑偨戞俉俉彫愡偐傜偼僪乕僫乕乕乕乕乕乕乕乕丄僷乕僠僃乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕儉偲偄偆姶偠偱摿掕偺壒偑堷偒怢偽偝傟傞丅偙偆偟偨偙偲傕偙傟傑偱偵偼側偐偭偨偙偲偱偁傞丅
丂埲忋偺傛偆偵偙偺儈僒嬋偱儌乕僣傽儖僩偼偝傑偞傑側怴偟偄帋傒傪峴偄丄偦傟偵尒帠偵惉岟偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅偦偺揰偱摨偠傛偆側怴偟偄帋傒偑懡偄妱傝偵偼偄傑偄偪惉岟偟偰偄側偄俲俀俈俆偺戝僋儗僪儈僒偲斾妑偟偰傒傞偲柺敀偄丅傑偨偙偺儈僒嬋偼偝傑偞傑側儊儘僨傿偵晉傫偱偍傝丄屻偺儘儅儞攈偺儈僒嬋乮摿偵僔儏乕儀儖僩側偳偺儈僒嬋乯傪梊尒偡傞傛偆側傕偺偩偲傕偄偊傛偆丅
|