儌乕僣傽儖僩偺嫵夛壒妝偺儁乕僕傊
K117丂僆僢僼僃儖僩儕僂儉Benedicitus sit Deus
(恄偼梍傔偨偨偨偊傜傟傛)
妝晥傊偺儕儞僋
丂壧帉
侾 崌彞
丂Benedictus sit Deus Pater 丂丂丂丂丂丂丂偨偨偊傜傟偰偁傟丄晝側傞恄偲丄
Unigenitusque Dei Filius丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恄偺傂偲傝巕偲丄
Sanctus quoque Spiritus丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惛楈偲偼丄
quia fecit
nobiscum丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺帨斶傪
misericoridiam
suam丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傢傟傜偵尰偟偨傕偆備偊偵
Benedictus sit Deus Pater丂丂丂丂丂丂丂丂丂偨偨偊傜傟偰偁傟丄晝側傞恄偼丄
benedictus sit Deus
Filius丂丂丂丂丂丂丂丂丂偨偨偊傜傟偰偁傟丄屼巕側傞恄偼丄
benedictus sit Sanctus Spiritus丂丂丂丂丂偨偨偊傜傟偰偁傟丄惛楈偼
2 僜僾儔僲僜儘丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
Introibo domum
tuam,Domine,丂丂丂丂丂丂丂巹偼屼恎偺壠偵擖偭偰偄偙偆丄偍偍庡傛丄
inholocaustis, reddam
tibi丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵳傝偺拞偵巹偼
vota mea,丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂巹偺惥偄傪曺偘傛偆丄
quae
distinxerunt labia
mea.丂丂丂丂丂丂丂丂巹偑偙偺怬偱栺懇偟偨傕偺傪丅
3丂崌彞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丄
嘆Jubilate 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂婌傃偨偨偊傛丄
嘇Deo omnis terra. 丂丂丂丂丂丂丂丂恄傪丄偡傋偰偺悽傪丄丂丂丂丂丂
嘇Psalmum dicite nomini ejus,丂斵偺柤偵偍偄偰帊曆傪岅傟丄丄
奣梫
丂偙偺嬋偼屒帣堾晅懏惞摪偱偺專摪幃偺嵺偵俲侾俁俋偲偲傕偵墘憈偝傟偨偲偄傢傟偰偄傞丅乮巹偑帩偭偰偄傞俲侾俁俋偺俠俢偵偼偙偺嬋偑僋儗僪偲僒儞僋僩僁僗偺娫偵擖偭偰偄傞乯偙偺嬋偼Allegro乗andante乗allegro偲偄偆僀僞儕傾晽彉嬋偺宍幃偱嶌傜傟偰偍傝丄僜僾儔僲僜儘傪娫偵偼偝傫偱擇偮偺崌彞偑偁傞丅
1嵟弶偺崌彞丂偙偺晹暘偺壧帉偼僇儖儖丒僪僯挊乽儌乕僣傽儖僩偺廆嫵壒妝乿倫俀侽偵傛傟偽乽專摪幃偵捈愙梡偄傜傟傞婩摌暥偵傛偭偰偍傝丄儘乕儅嫵夛偺揟楃偱嵟傕昗弨揑偵梡偄傜傟偰偒偨儈僒揟楃彂偵忔偭偰偄傞專摪幃偺儈僒偺曭擺彞偲偼堎側傞乿偲彂偄偰偁傞偑丄Liber丂Usuali偺倫俋侾侾偵摨偠壧帉偑嵹偭偰偄傞丅偙偺LiberUsualis偺奩摉儁乕僕偺偲偙傠偼嶰埵堦懱庡擔偺偨傔偺僆僢僼僃儖僩儕僂儉偱偁傞丅
偙偺崌彞偼丄傎傏僜僫僞宍幃偱彂偐傟偰偄傞丅Benedictus乣Dei filius傑偱偑戞堦庡戣丅戞7彫愡埲崀偑戞擇庡戣偲側傞乮Sanctus quoque Spiritus乯丅
懏挷偱廔巭偟偨戞16彫愡Benedictus sit Deus Pater偐傜偑揥奐晹偱丄嵞尰晹偺巒傑傝偼傢偐傝偵偔偄偑丄戞28彫愡偱丄採帵晹偺Unigenitusque Dei Filius偺庡戣偑擖偭偰偔傞偲偙傠偐傜丄偲峫偊傞傋偒偩傠偆丅偮傑傝丄採帵晹偺朻摢乮戞1乣係彫愡敿偽乯偑僇僢僩偝傟偰擖偭偰偔傞偺偩乮偙偆偟偨椺偼儌乕僣傽儖僩偱偼帪愜尒傜傟傞偟丄屻偺嶌嬋壠偱傕尒傜傟傞乯丅偁傞偄偼丄偦傕偦傕戞1乣4彫愡敿偽傑偱偼戞堦庡戣偱偼側偄丄戞堦庡戣偼戞4彫愡屻敿偐傜巒傑傞偺偩丄偲尒傞偙偲傕偱偒傞丅偦偺屻丄戞31彫愡傛傝丄尨挷偵偰丄Sanctus quoque Spiritus偵偍偄偰丄戞擇庡戣偑弌偰偔傞丅
俀僜僾儔僲傾儕傾丂僿挿挷偺柧傞偄嬋丅廆嫵嬋傜偟偐傜偸暤埻婥偑偁傝丄偙偆偄偭偨嬋側偳偑摿偵侾俋悽婭側偳偵偼嫵夛壒妝偲偟偰偼傆偝傢偟偔側偄偲敾抐偝傟偰偄偨偺偩傠偆丅
俁擇斣栚偺崌彞丂偙偺嬋偺壧帉偼丄壧帉偵墳偠偰壓婰偺傛偆偵丄嶰庬椶偵暘偗傜傟傞丅乮扐偟丄偙偺弴偱弌尰偡傞偺偱偼側偄乯丂偦偟偰偦傟偧傟偺壧帉偵憡墳偟偄庡戣偑梌偊傜傟偰偍傝丄俁偮偺庡戣偑戙傢傞戙傢傞搊応偡傞偺偑摿挜偱偁傞丅嘆仺嘇仺嘆仺嘊仺嘆仺嘊仺嘆仺嘇仺嘆仺嘊仺嘆仺嘊仺嘆
嘆Jubilate丂

丂偙偺壧帉偵偼乽恄傪婌傃偨偨偊傛丄偡傋偰偺悽傛乿偲偄偆堄枴偵傆偝傢偟偔丄嬥娗妝婍偲僥傿儞僷僯傪敽偭偨柧傞偄僴乕儌僯乕傪敽偭偨巐惡崌彞偑偮偗傜傟偰偄傞丅摿掕偺慁棩傪帩偭偰偄傞偺偱偼側偔丄崌彞丄僆乕働僗僩儔偑壒偺偐偨傑傝偲側偭偰抐懕揑尰傟傞偺偑摿挜偱偁傞丅僩乕僞儖偱6夞弌尰偡傞偑丄偦傟偧傟挿偝傕庡戣傕僶儔僶儔偱偁傞丅
嘊Deo omnis terra偺庡戣乮壓晥乯
丂偙偺庡戣偼2夞尰傟丄嵟弶偼抝惡丄彈惡偑儁傾偲側偭偰嶌傜傟傞偑丄俀夞栚偼僜僾儔僲亄僥僲乕儖丄傾儖僩亄僶僗偺慻傒崌傢偣偱尰傟傞丅

嘊Psalmum dicite nomini ejus丂date gloriam laudi ejus偺庡戣
丂忋婰偺傛偆偵乽斵(恄乯偺柤偵偍偄偰帊曆傪岅傟乿偲偄偆堄枴偱偁傞偑丄杮摉偵僾僒儖儌僨傿乮帊曆彞乯偑偱偰偒偰偟傑偆丅乮壓晥乯丂偙偺庡戣偼3夞尰傟傞丅
丂偙偺帊曆彞偼嫵夛慁朄偵偍偗傞戞敧慁朄偱偁傞丅側偤戞敧慁朄傪巊梡偟偨偐偲偄偊偽丄曭擺偺巀壧偺儗僗億儞僜儕僂儉偱偁傞乽Zachaee,festinans descende(僓働僆丄憗偔崀傝傛乯乿傪憐婲偝偣傞偨傔偵丄偙偺儗僗億儞僜儕僂儉偺慁朄偱偁傞戞敧慁朄傪嵦梡偟偨偲偺偙偲偱偁傞丅乮僇儖儖丒僪僯挊丂憡椙寷徍栿丂乽儌乕僣傽儖僩偺廆嫵壒妝乿倫21嶲徠乯丅側偍丄偙偺晹暘偼挿抁壒奒偱偼側偔丄慁朄偱偁傞偨傔偐丄偨偲偊偽丄僆僀儗儞僶乕僋偺斉偱偼丄偙偺晹暘偩偗丄榓壒傪帵偡悢帤偑彂偐傟偰偄側偄丅
丂戞敧慁朄偼壓晥偺擛偔丄僜偺壒偑廔巭壒偲側傝丄僪偺壒偑曐帩壒偲側傞慁朄偱偁傞丅偙偺婎弨偱偄偗偽忋晥偼傑偝偵戞敧慁朄偱偁傞丅
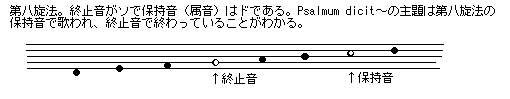
丂偙偺庡戣偼懠偺擇偮偺庡戣傪娫偵嫴傒側偑傜丄僜僾儔僲仺僥僲乕儖仺僶僗仺傾儖僩偲奺惡晹偱壧傢傟偰備偔丅嵟屻偺傾儖僩偩偗偼Gis偲側傞傋偒偲偙傠偑側偤偐俧偲側偭偰偄傞偨傔丄捠忢偺偳偺慁朄偵傕偁偰偼傑傜偢丄抁壒奒偲側偭偰偄傞丅

傑偲傔
丂埲忋偺傛偆偵偙偺嬋偼彫嬋側偑傜傕巈嵶偵傒傟偽12嵨偺揤嵥儌乕僣傽儖僩偺楈姶傪偁偪偙偪偵尒弌偡偙偲偑弌棃傞丅壧帉偺摿挜偵崌偭偨庡戣偺嶌惉丄偦偟偰偦傟傜偺庡戣摨巑偺娭楢丄彫婯柾側崌彞嬋偱傕僜僫僞宍幃偵傑偲傔偰偟傑偆擻椡摍丄偡偱偵12嵨偵偟偰摨帪戙偺嶌嬋壠孮偺拞偐傜堦摢抧敳偒傫弌偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅彮擭帪戙偺儌乕僣傽儖僩偺戙昞嶌偲偟偰俲139偲偲傕偵傕偭偲昡壙偝傟偰傛偄嶌昳偱偁傞丅丂
丂